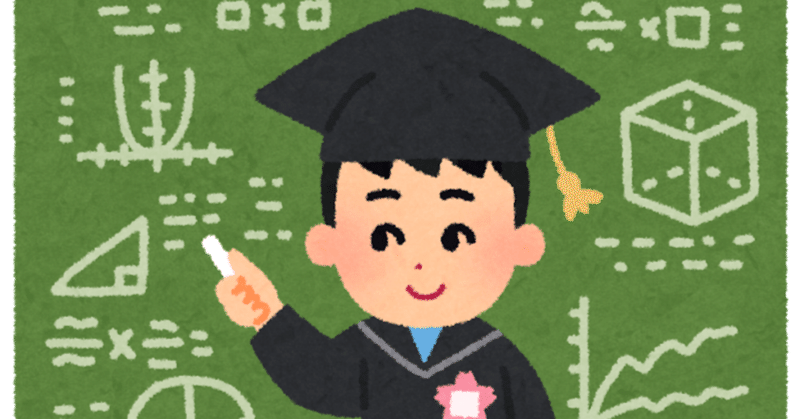
「学歴」について考えてみた
「学歴」とは何か
先日、こちらの記事を拝読しました。
特に興味深かったのが、「学歴」には3種類ある、ということ。
まず、「学歴」という言葉について考えよう。おもに3つの意味があり、1〜3の順に細かい情報になる。
1)学歴 = 資格歴:「中卒」「高卒」「大卒」など、資格を問う場合
2)学歴 = 学校歴:「〇〇大学卒業」など、資格に加えて学校名を問う場合
3)学歴 = 学修歴: さらに(2)での勉学の内容や成果を問う場合
普段何気なく使用している「学歴」という言葉ですが、なるほど確かに、かなり文脈依存的な性質を持つのですね。
指摘されているように、現代日本においては(1)または(2)で使用されることが多く、(3)は理系大学院生に限られる場合がほとんどだと感じます。
また、海外では(3)が主だというのは知りませんでした。MBAなど、確かにその傾向が強いのでしょうね。
前掲の記事を拝読するきっかけとなったのは、先日投稿した私の記事(親として子どもに学歴=学校歴主義を強いたくないよね、といった趣旨)に対し、著者の「ささきとおる」さんからコメントをいただいたことでした。
こうした繋がりをもって、新しい知見に出会えるのも、noteの良いところですね。
日本はなぜ、学校歴主義が根強いのか?
ところで、日本は学校歴主義が特に根強い(※)ように感じますが、それはなぜでしょうか。かなり粗めですが、以下考えてみました。
※先に挙げた理系大学院や、文系の中でも資格性の強い学科等もあります。ここでは多数を占める一般的な文系を想定していること、ご了承ください。
かなり粗い推測ですが、戦後日本における時代的要請がその一因と言えるのではないでしょうか。
欧米へのキャッチアップを目指すうえで、専門性以上に、勤勉で代替性の高い労働力が大量に必要とされました。そのため、就職の際には専門性を示さない「学校歴」で十分。
むしろ、入社後教育で自社色に染め上げる(転職できないため、労働者は立場が弱くなる)にあたり、「学校歴」が都合が良かったのかもしれませんね。
学校歴主義のメリットはある?~「学問」の観点から~
参照した記事では、学校歴主義に対する是非の明言は避けているものの、学習歴主義に立ったプランニングを推奨しています。(私も賛成です!)
そこで考えてみたいのが、「学校歴主義にはどのようなメリットが考えられるのだろうか?」ということ。
そもそも「学歴」というものは、学校歴にしても学習歴にしても、自己表現手段としての側面が強いと思います。
「私はこんな大学を出ているぞ」「私はこんな学問を習得したぞ」と、他者にアピールしているわけですね。
なぜ「学歴」を用いて、他者にアピールする必要があるのか?
それは、現在の資本主義社会において、私たちの多くは生活費を稼ぐため、自らを他者(会社など)に売り込む必要があるからではないでしょうか。
要するに、現代日本において求められる学歴は、「他者にアピールできる学歴」ということになります。
しかし、ここで立ち止まって考えてみたいのです。
何かを学び探求するということは、本来もっと自由なはずです。
あらゆる学問の基礎である哲学(philosophy)の語源は、「知を愛する(philosophia)」です。また、その哲学が登場した古代ギリシアでは、市民は奴隷を所有して生活に不自由ない人々でした。schoolの語源が「余暇(scholē)」であることにも、そうした背景があります。
これまでも多くの先人たちがその関心の赴くままに研究し、思いもよらぬ様々な成果がもたらされてきたわけです。
しかし近年では、我が国が「すぐに成果の出る研究」を求めるあまり、国際競争力が低下しているとの指摘もあります。
研究者は、何かの役に立つから研究するのではありません。とにかく明らかにしたいこと、知りたいことがあるから研究しています。自分の興味に基づいて研究を進めるからこそ、世界で誰も知らないことを明らかにできるのです
政府は04年の国立大学法人化以降、全体として経営の基盤となる運営費交付金を削減してきた。人件費が減り、不安定な任期付き雇用が増えた結果、若手研究者にしわ寄せがいっている。
何を言いたいのかというと、学歴社会において多くの人が、卒業後に「食える」学問を選択している現状があるのではないか、ということです。
実際、文系では大学受験の時点で就活を意識し、文学部などが避けられる傾向があります。また理系でも、研究費の獲得につながりやすい研究が当然好まれます。
それは真に学問と呼べるのか。
将来につながる基礎研究等をおろそかにしていないか。
こうした現状が、「学習歴主義」の社会では一層加速するのではないか、というのが私の考えた懸念点です。
大学入学さえ果たすことができれば、「学校歴」で事足りる(またはサークル活動などで代替できる)就職活動を想定する学生たちは、学ぶ対象について、学習歴主義社会と比較した場合に、多少なりとも裁量が与えられていると言えるのではないでしょうか。
(もちろん、どのような業界に就きたいか、どの研究室に属するか等、十分な裁量ではないと思います。)
要するに、現在の学校歴主義社会においては、大学入学後に何を学ぶかについては、多少なりとも裁量(自らの興味に従った研究を行える可能性)が残されている。しかし学習歴主義社会においては、真に学問にいそしむことは、それが他者へのアピールに欠ける場合、大多数の人において選択されにくいのではなか、ということです。
もちろん、現在の学校歴主義のままでいい、とは到底考えていません!
事実、日本の国際的地位(研究や経済など)は確実に低下しています。
私の言いたいことは、上記のような学校歴主義におけるメリットがあったことをしっかりと認識し、より適切な「学習歴主義」への移行を目指すべきではないか、ということです。
以上、かなり粗い私見ですが、お読みいただきありがとうございました。
