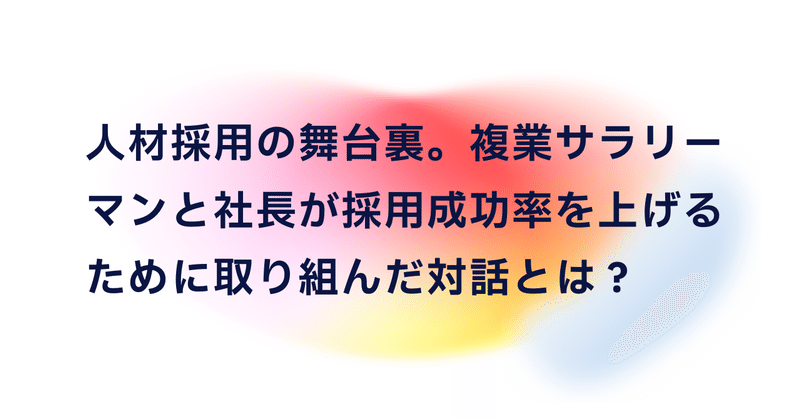
人材採用の舞台裏。複業サラリーマンと社長が採用成功率を上げるために取り組んだ対話とは?
こんにちは。阿部です。
2023年から複業を始め、ほぼ1年が経ちました。
通信会社でデザイナーとして働く傍ら、複業で障がい福祉・介護業界に足を踏み入れ始めました。経緯は前回のnote記事にまとめています。もしご興味持っていただけたら、読んでもらえると嬉しいです!!!
複業先の障がい福祉・介護の一般社団法人では、非常勤理事として「人材採用」に力を入れてきました。
ただ、最初から採用に注力しようと思っていた訳ではありません。
金曜の夜にヘトヘトになった表情で「人が足りない」と言う代表といまこそ「人材採用」に取り組まなければならないと意を決したのを覚えています。
そこで今回のnoteでは「複業先の代表と一緒に、喫緊の課題である人材採用に取り組んだ話」について書いてみたいと思います。また、実践のなかで考えた「複業ならではのメリット」もあわせてお伝えできればと思っています。
今回もお付き合いいただけると嬉しいです!
背景:”近づきづらい”介護
まずは、「介護って、案外、身近じゃないよね」という話から。
「いつかは自分も介護に関わるだろうな」という考えを誰しもが頭の片隅でぼんやりと持ちつつも、さて真剣に考えだすのは「ことが必要」になってからが多かったりします。

ドラマ「おっさんずラブ」のワンシーン。
主人公(田中圭)のパートナーのお義父さんがぎっくり腰になり、主人公がお義父さんのお尻を拭くまでの悪戦苦闘が描かれてます。何とかして排泄ケアしたいと歩み寄る主人公と、頑なに拒むお義父さん。
コメディ調に描かれる二人の掛け合いを笑って見ながら、はたと気づきました。どこかで自分ごとで捉えられていないことに。自分が主人公の立場になる可能性を頭の中では理解しつつも、介護を身近に捉えることの難しさを感じます。
課題:事業の命運を分ける人材採用
そんな身近に捉えづらい介護業界は、慢性的な人手不足です。これはよくニュースとかでも言われている話ですね。
複業先の一般社団法人もまさにそうで「人材採用」は喫緊の課題です。いま、グループホーム2棟を運営しており、嬉しいことに利用者さんや自治体からの引き合いも強く、更なる事業拡大を考えると人材採用は超重要な経営課題です。
とはいえ、うまれたてのベンチャー企業。他にも多くの課題が山積みで、ついつい場当たり的な対応になってしまっていました。
そんな折にジョインした私は、代表の課題感を聞き出していきました。質問しながら課題に共感していくスタイルです。
「課題が山積みでどこから手をつければいいかわからない」
「応募が増えても応募者とのマッチングがうまくいかない」
「採用活動の仮説検証ができておらず、ノウハウがたまっていきづらい」
ヒアリングの結果、企業理念に共感してくれる・質の高い人材を中長期的に採用し定着していくことの重要性を再確認することができました。切迫する人手不足での経営の難しさを肌身で感じながら、採用計画設計プロジェクトが始まりました。
打ち手:採用計画設計への5ステップ
主に取り組んだことは、以下の5ステップです。
代表と私で、月2回のミーティングを、3か月ほど繰り返していきました。以下、取り組んだ5ステップを振り返っていきます。
(1)採用課題の定義
どういう採用をしていきたいのか”ありたい姿”を明確にし、現状、何がボトルネックになっているのか、課題を定義していきました。
(2)採用ターゲットの設定
採用する側・される側の視点で整理していきました。
まずは採用する側の視点から。採用したい人物像として「組織のらしさ・求める能力やスキル」を洗い出していきました。そしてステークホルダーを整理し、コアターゲットを設定しました。
つぎに採用される側の視点で、応募者ターゲットのベネフィット(本音やなりたい姿)を掘り起こしました。最終的に2つのターゲットを軸に解像度を上げていきました。
(3)”ならでは”の価値明確化
ターゲットのベネフィットから、組織”ならでは”の価値を明確化していきました。始まる前は”ならでは”の価値が見つかるのか代表が心配してましたが、対話を重ねていくことで無事に明確化することができました。
(4)採用戦略の統一
ターゲットの採用までの理想フローと、それを実現する施策を検討していきました。まずは、ターゲットの「現状→課題認知→興味→応募→採用」と区切りながら理想フローを明確化していきました。資源が無限にあるなら手当たり次第に施策を打っていけばいいですが、そんな状況ではもちろんありません。限られた資源の中で何に集中し、どう資源を活かせば理想フローを実現していけるか。具体的な施策に落とし込んでいきました。
(5)採用計画の策定
具体的な施策に優先順位をつけて採用計画を策定していきました。詰め込みすぎることなく、いまある資源で実現可能な施策を素早く実行&検証できるように計画をしました。採用戦略が絶対に正しいと捉えるのではなく、あくまで仮説と捉えて検証していきます。
振り返り:複業ならではのメリット
ここまで、複業で人材採用に取り組んできた話をさせていただきました。
採用計画設計プロジェクトはひと区切りし、今まさに実行&検証に取り組んでいる最中です。具体的には、ポスティング用のスタッフ応募チラシを作ったり、イベントへの登壇準備などを進めています。機会があればこちらのことも書いていければと思っています。
最後に活動を通じて考えた「複業ならではのメリット」を振り返って、お話をしめたいと思います。
複業メリット①よりシャープに再現する力の獲得
複業ならではのメリットとして、これまで何気なく口にしてきたことを丁寧に言語化するところにあると考えています。
本業で何気なく用いてきた横文字(ブランディングやデザインなど)が複業先ではほとんど伝わらないことがありました。そこで、言葉の定義から本質に立ち帰って言語化し、ミーティング始めに確認し合うようにしました。すると議論が噛み合い、うまくファシリテートできるようになりました。
新たな概念に初めて接する人に伝わるように言語化するのは時間がかかります。しかし、それはこれまでのノウハウや経験を本質から振り返る機会となり、よりシャープに効果的に再現する力を高めることに繋がっているなと感じています。
複業メリット②経営者視点と思考スペースの獲得
本業への向き合い方の変化も、複業ならではのメリットだと考えています。二つほど紹介させてください。
一つは、経営者視点で考えやすくなったこと。
複業先では経営者と会話することがほとんどです。経営者視点で考えることが当たり前になっていきます。この経験は本業への向き合い方に変化を及ぼします。例えば、本業で取り組むプロジェクトやミーティングの発言一つとっても、会社の経営課題と紐づけて考えるのが習慣になりました。
もう一つは、頭を切り替える思考スペースができたこと。
複業をはじめる当初は、複数のことを同時にやって頭がパンクするのではないかと心配していました。しかし実はその逆で、頭の中に新しく考えられるスペースができたように感じています。本業で行き詰ったときに複業のことを思い出したり、逆もまた然りで。新たな思考スペースができたことで、頭を切り替え、考えを進めていくことができるようになりました。
次回は、複業先で働く人との関係作り
ここまで「大企業で働く私が、複業先の一般社団法人の代表と一緒に、喫緊の課題である人材採用に取り組んだ話」を振り返ってきました。
次回は「複業先の働く人との関係作りや中長期的に付き合っていくためのポイント」を書いていこうと思います。
皆さん、よい一日を。
