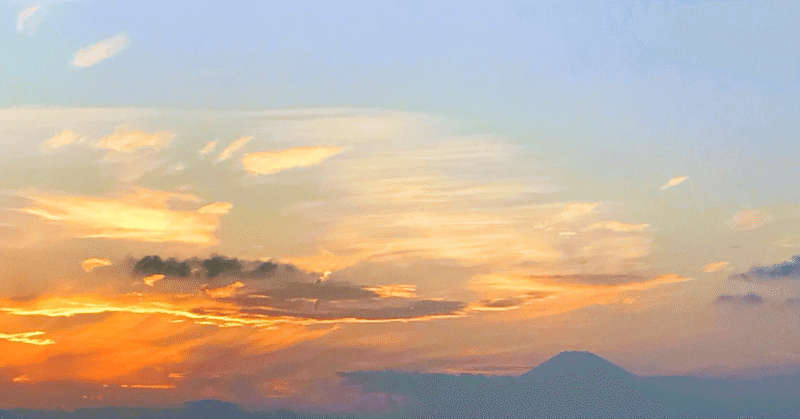
脱テレビの時代〜中央集権の学校から自立分散の独学へ〜
もう「先生」は必要ない
若者はテレビも見なければ、新聞も読まない。私が印象的であったのは、ジャーナリズム研究の権威ある人々が、学生に対して「新聞を読みないさいと言うことを諦めた」という話を聞いたことである。確かに、特に新聞は読んでおいた方が良いと私も思う。それでも、もう新聞が多くの人に読まれることはないだろう。私たちは、これから個人化された情報社会を生きていかなければならない運命なのだ。それは、テレビや新聞のような「みんなが同じ情報をある程度共有している社会」から次の社会に移っていく脱テレビの社会である。
テレビも新聞も、視聴者は発言することができない。せいぜい読者投稿欄に投稿した文章が新聞に載る程度であろう。結局、報道する側とそれを見る人々という構造は変わることはない。これは学校制度とよく似ている。つまり、テレビも学校も中央集権的でなのである。権威を持つものにしか発言を認めない。
しかし、何度も言われたことだろうが、ネット社会は情報発信を(ある程度)民主化した。これは大手テレビ局や新聞社を介さなくとも、情報発信(人にものを教えること)ができるようになったということであった。だからこそ、私たちは学校でなくとも好きなことを学べるようになったし、ネット社会に「先生」はいなかった。なぜなら、誰もが教える者になることができたし、そこに参入障壁や権威はなかったからである。知識のある者たちが集い、ない者も議論に加わり、激しく衝突しながらもみんなが参加者になれるのがネット社会だった。
「分断」を前提とした社会へ
ネット社会では明らかに文化や好きなものが分断している。テレビを見ない若者は、社会一般で今何が起こっているのかあまりわからない。いや、逆に政治的にどのようなことが問題になっているのかを、関心のある者はとても詳しく知っている一方で、そうでない者のタイムラインには一切流れてこない。このような時代だからこそ、信頼性が高く網羅的なテレビや新聞は重要だという論調もあり得るが、それは無理だと個人的に思う。テレビや新聞に若者は戻らない(というか知らない)。私たちは、この情報が分断された社会を前提にして生きていかなえればならないと思う。これを私は脱テレビの社会と思っている。
「予測不可能な社会」で学ぶべきことを先生は教えられない
変化が激しいとか、予測不可能とか、これからの何十年かをそのように表現することが多い。そのような社会において、「先生」はどのような役割を担うのか、そんな議論が学校で働く人々によって好んで行われている。これはポジショントークであるように思う。つまり、「先生」の職や存在意義がありきで話が進んでいる。「先生」という職自体が必要ない可能性は考慮に入れていない。先生の役割が何かを考えるということは、先生には必ずどんな時代も何かの役割があるはずだという慢心が含まれている。
しかし、必要な能力が予測不可能だとするならば、それは先生が予測できるようなことではない。したがって、変化の激しい社会では先生の役割があるにしてもないにしても、その役割が何であるかを予測することもできない。必要な人材や能力と呼ばれるものは、社会状況や労働市場、自由市場がそれを決めるからである。これだけ求められる能力が流動的な社会で、学校で勤務するいわゆる権威ある「先生」に教えられることはほとんどないであろう。あるいは、あるにしてもネットで学ぶ方が何十倍も意味のある学習になるだろう。だから、先生の役割を考えるだけ無駄であり、様々な人が情報をネットにアップし、学習者がそれを独学するという「先生がいない社会」に移行することにならざるを得ない。
「教える」という概念がない情報社会〜プラットフォームに話しかける〜
ネットには別に「教える」という概念がちゃんとあるわけではない。それぞれ知っていることをブログに書いたり、自分の考えについて表現することはあっても、それを直接誰かに「教育」しているという感覚はないだろう。それは、情報社会の中に記事や動画や写真を「アップしている」という感覚だからだ。だから情報社会では誰もに学びが開かれている一方で、誰も教育してやろうとは思っていない。
また、いわゆる教育コンテンツと呼ばれる動画や文章であっても、直接教育している感覚はかなり薄いであろうし、学習者も教育されているという感覚はかなり薄いのではないかと思う。それはyoutubeであったり、googleであったりというプラットフォームを介して学習が行われているからであり、教育系のyoutuberは(少なくとも物理的には)所詮は、学習者に話かかているのではなく、カメラに向かって、あるいはyoutubeというプラットフォームに向かって話しかけているだけだからである。
このことは、学習動画をみるには当然学習者のクリック(同意)が必要ということになる。このシステムは学校制度にあった学習者の自由を奪う機能を排除する画期的なものであり、要するに好きなものを好きなだけ学べるようになったということだろう。
脱テレビの学校
このように今では自分の好きなものだけを好きなだけ学べる環境が整っている。そして、テレビのように中央集権的な学校から、自立分散した(広い意味での)ネット独学へと方針転換しなければならない時が必ずやってくるだろう。社会が流動化すればするほど、政府主導の学校制度は社会経済トレンドを追えないという(ケインズ政策的な)構造上の課題があるのだから。
ネットやブロックチェーンなどの民主的で自立分散的な空間は、学校制度に変わる新たな学びの場になる。私たちは今、ネットで物事を調べる時に「学んでいる」という感覚はないし、記事を書く時に「教育している」という感覚もないが、確かに多くのことを感じ、思想を形成し、ネットに大きく影響されながら(学校よりもあるかに大きな影響を受けながら)生きている。
「教育する」という概念がない情報社会の中で、人々はこれからどう独学していくのだろうか。学習の脱テレビの時代、つまり「先生」が消え、「教育」という概念さえもなくなるネット独学の時代がもう来ている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
