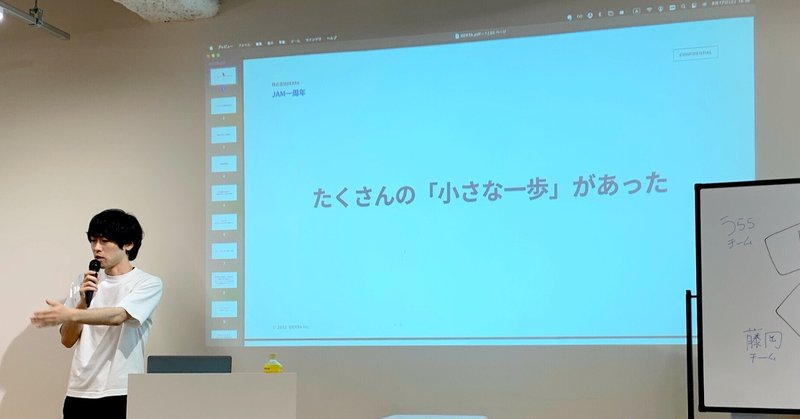
「UPDATE LOCAL」で僕らはどんな未来を実現するのか
こんにちは、代表の坂井です。
先日は「DERTA JAM with BEECL1周年記念イベント」を開催し、「cos DERTA(コサインデルタ)」コミュニティメンバーのみんなとDERTA JAMの一年を振り返りながら、改めてコミュニティの真価に触れる有意義な時間を過ごせました。
元々デルタはコミュニティから派生した組織で、「デジタル」「デザイン」「共創コミュニティ」の力で「UPDATE LOCAL」を目指している会社です。
当社のコーポレートサイトでも真っ先に目に飛び込んでくる「UPDATE LOCAL」の文字。今回はそんな「UPDATE LOCAL」とはなんなのか。コミュニティや事業活動を通して僕らは何を実現したいのか。
DERTAが描く未来の姿をお伝えできたらと思います。
僕らの「小さな一歩」で熱量ある人たちが集まった
冒頭で触れたDERTA JAMのイベントですが、年齢・立場関係なく、チャレンジしている大人たちがいて、ありたい姿を目指して積極的に動いている学生たちがいる。
その場に流れるエネルギーのバランスがとても心地よく、「これこそ10年前の自分が見たかった光景だ」と感慨深い気持ちになりました。

「10年前」とは僕がまだ学生だった時代です。少しだけ僕の学生時代の話に触れると、進学・就職のタイミングで「県外に出る」という選択肢が取りづらい状況でした。そんな中で友人たちは「ここには何もないから」とどんどんと県外へ出ていってしまう。
友人たちの決断に対して、羨ましさと寂しさの入り混じった何とも言えない気持ちが芽生えていました。
なぜ地方は「何もない」と言われてしまうんだろう。
お恥ずかしい話ですが、当時は社会との接点が薄く、そもそも身近にどんな大人がいるのかも知らず、誰に聞いたらいいかもわからない。どんな仕事に就いて、どんな風に生きていくのかの検討もついていませんでした。
漠然と社会の分断や現状維持の閉塞感のようなものだけを感じており、「年齢・立場関係なく、もっとフラットに集まれる場」のようなものに憧れていました。
その後、就職や起業、合併など様々な変化を経ながらも地域に軸足を置いてきた理由は、この辺りにあるように思います。
現在のDERTAの動きに繋がる直接のきっかけとなったのは、起業5年目の時でした。
首都圏で日常的に開催されているIT・WEB系のミートアップが新潟にはほとんど無かったことから、「無いならまずは自分たちで何かやってみよう」ということで現・DERTA CDOの美智子さん(@mity)と開催。
いざやってみると、同じように「現状を変えたい」ともどかしさを抱えた方々が続々と集まってくれて、第2回目にして100名規模の取り組みへと成長。首都圏の人気イベントとのコラボなどを経て、行政からも声がかかるようになりました。
その過程で緩やかに形成されたコミュニティでは、新たな事業創出の動きが生まれるなど、人と人とが出会い、同じ時間を過ごすことの大切さを知りました。
この時、地方は何も無いわけじゃない。熱量がある人たちはこんなにいる。ただ一歩を踏み出す場所がなかっただけだと痛感しました。熱量がある人が集まることによって、大きなエネルギーが生まれることを目の当たりにしたのです。
この灯火を絶やさず維持していきたい。
そんな思いが募り、コミュニティからスピンオフする形で会社を設立しました。
キーワードは「デジタル」「デザイン」「共創コミュニティ」
DERTAは「デジタル」「デザイン」「共創コミュニティ」の3つのキーワードを軸に、「UPDATE LOCAL」を目指しています。では、なぜこのキーワードの掛け合わせが「UPDATE LOCAL」に結びつくのかをお伝えします。
まず、「デジタル」に関しては大前提です。現代では誰もが電気を使い、意識をすることなく活用して当たり前に生活をしています。デジタルもやがて「電気」のような位置付けになるはずです。
地方で暮らしている私の目線では「デジタル化」自体は進んでいるものの、本質的な恩恵を受けられているケースはまだまだ少ないと感じています。単純に紙でやっていたことをデジタルに置き換えてみたものの使いづらさが勝ってしまい、「デジタルなんか意味がない」という印象を持っている方もたくさんいます。
実際、多くの会社で「DX」が叫ばれてはいるものの、デジタルに重きが置かれてしまっており「デジタルは意味があるのか無いのか」のような話になってしまってる節もあります。本質的に目を向けるべきはD(デジタル)ではなく、X(トランスフォーメーション=変革)の方なんですよね。「大前提としてのデジタル社会に対して、物事の向き合い方を変革しよう」という営みがDXです。
デジタルの力は本来、圧倒的なスピードを生み出します。新しく何かを立ち上げるコストは低くなり、コミュニケーションの速度も上がったことから、様々なサービスが乱立しています。ChatGPTは信じられない精度で「答え」を出してくれるようになり、ガストに行けばネコ型配膳ロボットが仕事をしてくれています。
このように仕事のやり方や物事の捉え方が一変してしまうようなサービスは日々生まれており、誰もが予測困難な世の中に突入しています。「自分はIT業界じゃないから関係ない」と言っている人も含めて、断続的な変化はほとんどすべての仕事を飲み込んでいくはずです。
そんな時代を生きていくために必要となるのは「デザイン」の考え方です。デザインとは本来「設計」という意味を持っており、色や形といった表面的な話に止まりません。
激しい変化のなかで多様な価値観が生まれ、誰も答えを持っていない世の中において、デザインが本質的に持っている「目の前にいるユーザーだけが答えを持っている。ユーザーと向き合い、ユーザーのためにもの・ことを作ろう」というスタンスが必要ですし、これは人間だからこそできる営みです。
そして最後に、「UPDATE LOCAL」を実現する上で欠かせないのが「共創コミュニティ」の存在だと考えています。変革を試みる動きはまだまだ少なく、特に地方においては顕著です。夢を語れば「意識高い」と笑われるし、一歩進んだら「そんなの上手くいかない」「和を乱すな」と現状維持勢力がマウントをしてきます。
物事を変えるためには、とてつもない負荷がかかります。勇気を振り絞って踏み出したその一歩は、「小さな一歩」に見えるかもしれませんが、当人以外では想像もつかないような渾身の一歩なのです。
それに対して批判のコストは非常に低い。どんな物事でも何かしら粗はあるものだし、新しく始めることに粗があるのは至極当然のこと。
挑戦者はこうした構造上、孤独になりやすいし、「小さな一歩」はあまりにも儚い。
だからこそ、そんな「小さな一歩」は大切に守らなきゃいけない。お互いに賞賛し、共に学び合い、支え合える環境としての「コミュニティ」が重要だと考えています。

一人では不可能なことも、意志のある人たちが集まるコミュニティの力で成し遂げることができる。もしくは、コミュニティ内でスキルや知見をアップデートし、持ち帰って変革を起こしていける。
その熱量が伝播し、また新たな挑戦者の「小さな一歩」を生むことで、地域全体の気運が変わると信じています。
「デジタル」「デザイン」「共創コミュニティ」こそ、「UPDATE LOCAL」を実現するにあたって欠かすことのできない大切な要素です。
DERTAは人と企業を繋ぐ社会装置に
DERTAでは、「地域の中で人や企業を繋ぐ社会装置」となって企業・自治体・大学・研究機関を繋ぎ、イノベーションの可能性を広げていくという役割を掲げています。地域の中であらゆる連携を生み出すためのハブになろう、というスタンスです。

地方においては割と「内に閉じてしまう傾向」があり、見えない分断が生まれています。
なぜそうなるのか話を聞いてみると、実はシンプルに「一歩の踏み出し方がよくわからない」というケースが多いのです。
DERTAの中には、環境の変化を恐れないフロントランナーたちが集まっています。
みんな利他の精神に溢れていて、主語が自分ではなく「社会や地域にとって何が良いか」という議論になるんです。
そんな僕らがハブとなってフラットに関わることで、「社会をより良くする」という共通のゴールを見据えて人と企業を繋げ、育てていくことを使命としています。
希望の物語が一つずつ増えていく「UPDATE LOCAL」
「最終的にUPDATE LOCALが実現するとして、それってどんな未来なの?」を自分なりの言葉で表すと、「地域の中に希望の物語が増えていること」だと思っています。
以下は現時点でのビジョンを図で表したものです。(これからさらにアップデートを重ねていきます)

共創コミュニティでの人と人との出会いを通して物語のタネが生まれ、そこに共感した仲間たちが集まり、みんなで支え合いながら1ページずつ紡いでいくことで、地域に新たな価値を生み出す。
物語には人の心を動かし、未来を照らすパワーがあります。
希望の物語が増えれば、もう「地方は何もない」とは誰も思わない。若者たちも地域の中でこうなりたいという大人の姿を見つけ、憧れつつ、世界中の情報に触れながら、自分の未来を作っていくことができると思います。
これからもDERTAは、「小さな一歩」を讃え、守る居場所となり、地域のハブとなり、希望の物語を増やし続けていきたいと思います。
