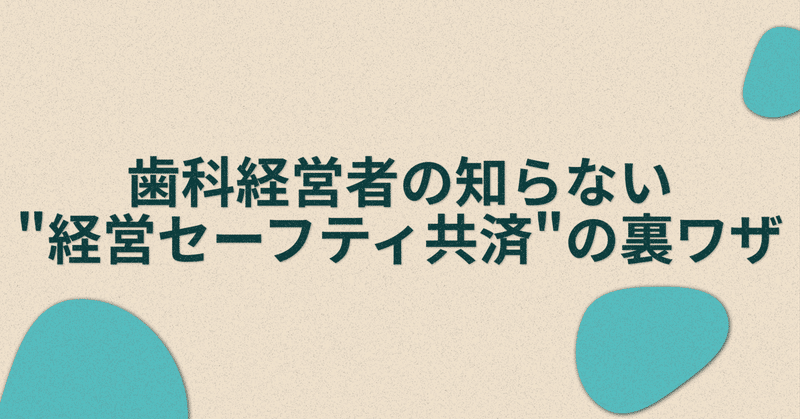
歯科経営者の知らない"経営セーフティ共済"の裏ワザ
皆さん、開業医の皆様は、売り上げは順調でも、税金の支払いで手元に残るお金が少ないことに悩まれたことはありませんか?特に新しく開業した歯科医院の先生方にとって、これは頭の痛い問題ですよね。
そこで今回は、歯科経営者にとっての救世主とも言える"経営セーフティ共済"にフォーカスして、その活用法や裏話についてお話ししていこうと思います。
経営セーフティ共済とは?
まず初めに、"経営セーフティ共済"って何か知っていますか?正確には「中小企業倒産防止共済制度」のことです。取引先が倒産した場合、最大で掛金の10倍までの金額を借り入れられるスグレものです。運営は中小企業基盤整備機構が担当し、中小企業の連鎖倒産を防ぐのが狙いです。ただし、医療法人は対象外なのでご注意ください。
経営セーフティ共済の節税メリットとは?
経営セーフティ共済の節税メリットは非常に大きいです。支払った掛金全額を経費に算入できるため、その年の課税所得を減らせるんです。ただし、注意が必要で、解約時には課税の繰り延べがあるため、タイミングや場合によっては逆に痛手になることもあるんです。
節税のコツと解約タイミング
経営セーフティ共済を上手に活用して節税するためには、解約するタイミングがポイントです。利益の多い年に積み立て、利益の少ない年に解約手当金をもらうことで、ちょっとした節税が可能です。経営が安定している場合は退職時が一般的ですが、経営が不安定な時や設備投資が必要な時、解約が有利な場合もあるので慎重に検討しましょう。
前納制度を利用した節税効果
経営セーフティ共済には前納制度があります。これを使えば、掛金を一気に前払いして、その年の経費に算入できます。初めて前納制度を利用する場合、ある事業年度の初月から月20万円の掛金を一括で支払えます。これによって、最大で23ヶ月分(最大460万円)をその年の経費として計上でき、ちょっとした節税効果が期待できます。
経営セーフティ共済を使って節税に成功するために
経営セーフティ共済を活用して節税するためには、計画的な使い方が必要です。解約時のタイミングや月々の掛金の見直し、解約手当金の受け取り時期などを慎重に考え、賢く経営セーフティ共済を利用していくことが重要です。
まとめ
経営セーフティ共済は、積み立てつつも経費として算入でき、共済金貸付で医院の防衛もできる素晴らしい仕組みです。ただし、節税方法として使う場合、最終的には“課税の繰り延べ”をしていることを理解しておくことが必要です。税金対策で使ったつもりが逆に痛手にならないよう、経営状態やキャッシュフローを分析し、毎月の掛金を見直したり、解約手当金のタイミングを考えたりして、賢く経営セーフティ共済を使いましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
