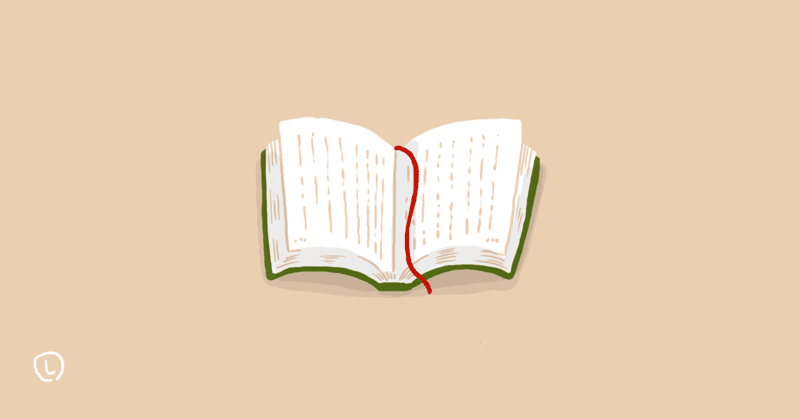
45歳から身に着けた 「本を読むこと」読書習慣をつけるためにしたことしなかったこと「持たない」編
5年前、言葉を覚えることを目的に本を読み始め、気が付けば毎日読んでいます。2022年後半からは、小説も読めるようになりました。
2023年ようやく「そこそこ読んでいるのでは?」ということに気が付き、noteで記録してみることにしました。
それから1年が経った今、読書の習慣を振り返って
45歳から身に着いた「本を読む」こと、を書いてみます。
このnoteは
から始まる、45歳から身に着けた 「本を読むこと」についてのお話です。
2つ前に書いた「本を読むために決めていること」
の中から今日は
「持たない」について解説します。
わたしが「持たない」と心掛けていることは2つあります。
ひとつはこれまでにも登場した「罪悪感」です。
罪悪感に関しては主に前々回の「買わない編」に書いていますので、そちらをお読みください。
そして今回のメインとなる「持たない」が何かと言えば
目標 や 目的
読書をすることによって何かを得ようと考える
その思考や行動です。
本を読もうと決めたときに思いつく目標や目的は
・毎月一冊本を買う
・一週間に一冊読む
・一日30分は読む
・感想をSNSに残す
・知識を増やし 学びを深める
・集中力を高める
などなどです。でも
思い出してみてください。
夏休み前日や初日のことを。
わくわくしながら1日のスケジュールを立てたあの日のことを。
あれって実は勘違いだったんです。
ほんとうは
夏休みの始まりにわくわくした気持ちを「やる気」と勘違いした思考が、1日のスケジュールを組み立ててみようと思いついた。
ということだったんです。
作りませんでしたか?
円グラフ。
わたしは時間とスケジュールを縦型に書く、羅列派でした。空いたスペースに歯ブラシの絵なんか描いちゃって色まで塗ってました。
計画を立てること「だけが」楽しかったんです。
7時に起きる。トイレ。顔を洗う。ラジオ体操。ご飯。歯磨き。宿題。休憩。縄跳び。麦茶を飲む。
それはそれは事細かく書き、その間ずっとわくわくしています。
でもそのわくわくは、本当は夏休みにだらだらできるわくわくだったんです。カラフルな計画表を作ることが、計画通りに動く自分を妄想することだけが楽しかったんです。
それを思考が「お、このわくわくは計画を立てているからこそ生まれている!絶対やりきるぞ!」とまで言うんです。
で、3日後。いやもう翌日です。母にたたき起こされてかろうじてラジオ体操には行くものの、気づけば11時。
で
わっくわくで書ききった計画書を、視界に入れることすら嫌ぁぁ・・
になった経験、ないとしても ですね、それに似た経験はあるんじゃないですか?
高い目標を立て、挫折し、期待通りに動けない自分に落胆し、ただただ楽しく過ごすことにすらチクチクと罪悪感を感じてしまう。
話を戻しまして読書の場合、立てた目標が達成できないと、本を読むことすら嫌になるということになる。
そのループを断ちきるには
目標 や 目的 を立てない。それを 意識的にする のです。
子供のころ学校の教室には「クラスの目標」が掲げられ、仕事で何かを成し遂げるために、その先にある目的を常に考えてきました。
そうしてうまくいった経験からしみ込んじゃってます。
計画を立て目的や目標を考え、それに向かって努力する。
それが物事を進める時の、最善の方法である。と。
でもその方法、苦手なことに向かうときには逆効果だったんです。
(あくまでも「わたしにとっては」という話です。)
本が読書が好きな人が、その楽しみ方を広げようという試みのもと、目標や目的を持つならばいいんです。でも
今書いているのは
3Y(読めない・読まない・読みたくない)だったわたしが
どうして読書が好きになったのか
ではなく
どうやって読書の習慣を身につけたか、の解説のつもりです。
目標や目的を考えることが楽しいということなら、それだけを楽しむ。
その後の行動とはしっかり分ける。でもそれは難しい。
立てたら動かねば、と思ってしまいます。そう形状記憶されています。
それでも、本を読めない人がもしも目標を持つとしたら
「本を読む」(読み切らなくても可)それだけ。
図書館へ行く。それだけ。
それができたら
図書カードを作る。それだけ。
それができたら
本を借りる。それだけ。
それができたら
本を開く。それだけ。
目の前のことを1つだけ です。
ただそれだけでいいのです。
本を読んだ先の何かを目指せば、読めなかったとき「読めなかった」以上の落胆を抱えることになります。
感想が書けなかった
続けられなかった
何も得られていない
変われない
読書のあとに何か する 得る ではなく
読む行為そのもの、それが目的
それでいいのです。
でも読み始める動機が欲しい。
という気持ち、よくわかります。
わたしは手荒れを治す食生活の改善をきっかけに本を読み始めました。
何もないところから「そうだ本を読んでみよう。」と思い付いたとしても、あともう一押し!
はじめることに勢いをつけたい。と考えることは当たり前のことです。
だからやっぱり最初の動機や、読み続けるための理由は必要だと感じます。
わたしにとってそれが何かといえば、その答えはすでに書いていて
言葉を覚える。
なんです。
言葉を覚えると言っても(やはり以前書いていますが)辞書を調べたりパンに書いて食べたりしなくてもいい、ただ読むだけで良いという方法です。
そして新しく覚えた言葉を思考の材料にすること。
それは服や髪形を変えるように、目に見える明らかな変化(成長)をもたらすわけではないけれど、だからこそ挫折のしようがないという安心感があるのです。
わたしが「読んだ本を記録する」ということをはじめたのも、本を読み始めて何年か経ち「読む以外のこともできそうだ」という余力を認めてからのことでした。
それまではそれすら負担になるかもと思い「読む」以外のことはしていませんでした。
今も面倒になったらすぐにやめるつもりでいます。
このページの最初に書いている
「5年前、言葉を覚えることを目的に本を読み始め」
も実は読みながら得たもので、読む前に立てた目的ではありませんでした。
目標や目的は読書ができるようになった余力のその先にあること、と実感しています。
続きはこちらから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
