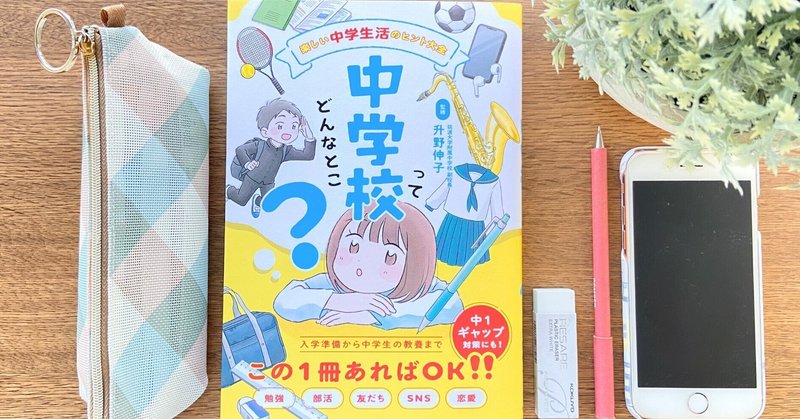
重版出来!児童養護施設の「お母さん」が語る、子育ての秘訣『中学校ってどんなとこ?』刊行記念コラム③
児童養護施設に勤めるKさんの「中学校は小学校の延長じゃなかった」という言葉をきっかけに、小学5~6年生・新中学1年生向け書籍『中学校ってどんなとこ?』が、誕生しました。
*おかげさまでご好評いただき、このたび重版が決定しました!
⇒ 本書誕生の経緯や、いただいた感想をまとめた
連載第1回記事はこちら。
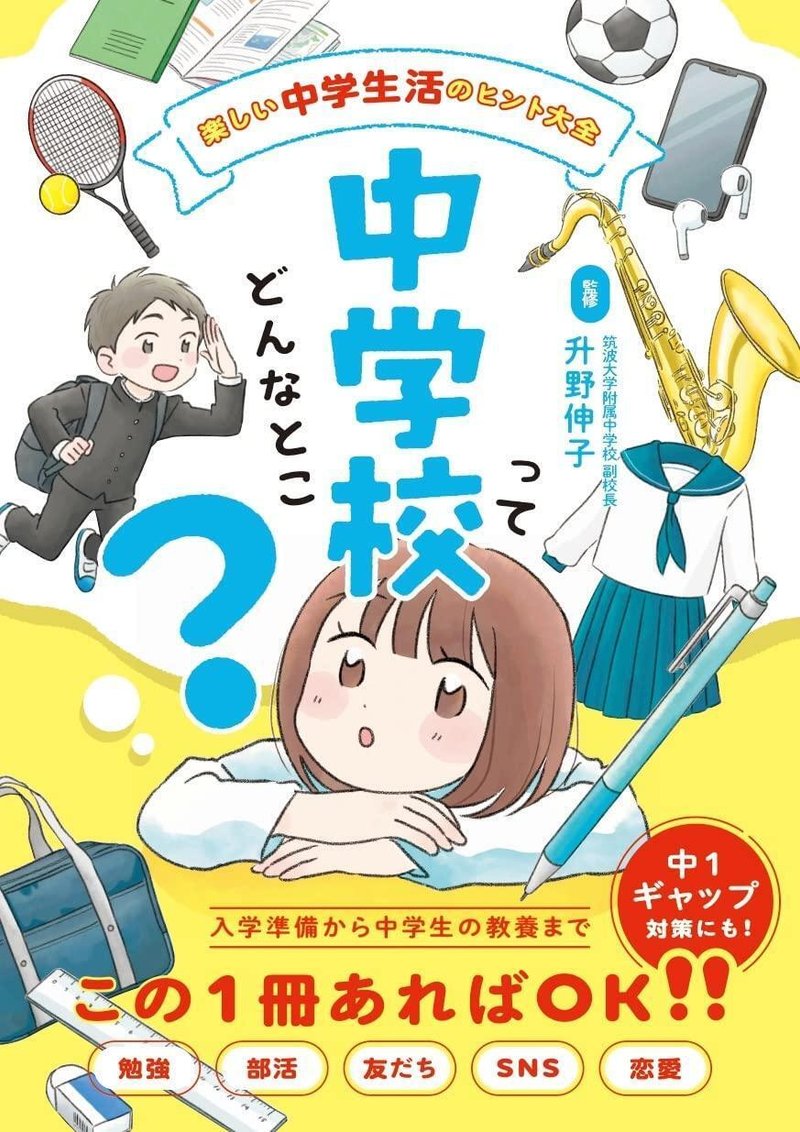
連載最終回の今回は、本から少し離れて、Kさんの児童養護施設でのお仕事の内容について伺います。
児童養護施設、その存在はもちろん知っていますが、実態をよく知りませんでした。
施設で暮らす子と職員さんたちが、どんなところに住んで、だれとごはんを食べて、食卓ではどんな話をするのか――?
そもそもKさんは、なぜ児童養護施設の職員を志したのか。
「中学入学準備の本が欲しい」とKさんが考え続けたその背景に、どのような日常や思いがあるのか、この機会にぜひお聞きしてみたいと思いました。
【お話を伺った施設の概要】
●子どもの年齢:2~18歳
●子どもの人数:施設全体で60人強。6~7人×11棟に分かれて生活している
●職員の人数:施設全体で70人強。1棟を4人の職員で担当する。日勤・宿直のシフト制
●建物:本園には事務所、庭、一軒家(棟)が数件。そのほかにも「グループホーム」と呼ばれる2階建ての一軒家が住宅街に点在する
●1棟の構成:幼児グループは男女混合、それ以降は男女で棟を分ける。年度ごとに相性を見て子どもたちの構成を入れ替える
●Kさんの職歴:勤続14年目。これまでに55人のお子さんを担当
「いるだけで、何かできるのかもしれない」と感じた夜
―――勝手なイメージかもしれませんが、魂を削るようなすごく大変なお仕事じゃないかと思うんです。児童養護施設の職員になろうと思われたきっかけから、伺えますか?
私自身が、あまり勉強しなかったほうだったんです。付属高校から大学に上がることを考えたときに、福祉系のところなら進学できそうだなと。
福祉にも、障がい者、高齢者、地域福祉などコースがあるなかで、自分は子どもコースを選びました。特に福祉や子どもに興味があったわけじゃないので、決めたのは「なんとなく」ですね。
ただ、児童養護施設の実習に入ったとき、「これならできるかも」と思うことがあって、そこで一気に興味を惹かれたんです。
施設の職員になるには、社会福祉士や保育士、教職などの資格が必要です。自分はどれも持っていなかったので、学校に入りなおして、保育士の資格を取りました。
―――実習では、どこに興味を惹かれたんですか?
実習で入った家に、気性の荒い高校生の女の子がいたんです。ふだんから、ひとりの男性職員と気が合わない様子でした。
その男性職員が担当のある晩、彼女が施設の外に出て行ってしまったんです。実習生の自分も外まで探しに行ったんですが、見つからず。そうこうしていたら、数時間で彼女が戻ってきました。
そしたら、その一部始終を見ていた、同じ棟で生活している小人症の中学生の女の子が自分のところにきて「いつもだったら、戻ってくるまでにもっと時間がかかってる。お姉さんがいたから、早く戻ってきたんだと思うよ」と言ってくれたんです。
私が特別、何かしたわけではないんですけど。
子どもってよく観察してるな、感受性が豊かだな、ということを感じました。
学校でも、子どもや障がい者のことは学んでいましたが、よく理解していませんでした。でもその一件があって、子どもでもちゃんと考えていて、障がいのある子も私たちと変わらないなって。
何もできないと思っていたけど、自分がいるだけで、できることがあるのかもしれないと思いました。
―――素敵なお話ですね…!
その高校生の女の子が、30代くらいの女性職員さんと一緒にキッチンに並んでいたときに、職員さんのことを「私のお母さんなんだ~」って話してくれたんです。そんなに長時間一緒に過ごしているわけではないはずですが、そんな風に思わせる職員さんってすごいなと思って。
さっきの男性職員さんも、頼りない人だったんですけど、4歳の男の子が青い鼻水を垂らしていたら温かいタオルを長時間あてて、固くなった鼻水を溶かしてあげたり、綿棒で取ってあげたりして。そういう、人のよさ、温かさを見ていいなと思って。
2週間の実習は、施設の中ではなんでもない日常だったんですけど、自分にとっては新鮮な体験で。そんなことがあって、児童養護施設の職員になりたいなと思いました。
―――施設で、自分にもできることがあるかもしれないって思われたんですね。
いろんな子がいて、いろんな職員がいて、相性はあるから、自分みたいな職員がいてもいいんじゃないかなって思っています。
親の虐待をスタンダードだと思ってしまわないように
―――職員さんたちの年齢層は?
20~30代が中心ですが、特に20代前半くらいの若い職員が多いと思います。結婚や、ほかにやりたいことがあったり、メンタル不調などが理由で辞めていく人も多くて。いつも人手不足です。
実習生が毎年3人くらい来るので、児童養護施設のいいところや楽しさを知ってもらえたらと思って接しています。偏見もあるかもしれないけど、生活しているのはいい子たちだから。
―――お子さんたちは、事情があって親御さんと暮らせない子たち。
そうですね、7割が虐待で。暴力、支配、ネグレクト、少ないですが性的虐待など。あとは親御さんが精神疾患などで養育が難しい子。
―――ご両親が他界されている子が多いのかと思っていました。
児童養護施設の始まりは、そうだと思います。第二次世界大戦が終わって、戦災孤児を救う取り組みとして始まったので。いまはご両親が亡くなっているケースは少ないですね。
―――お子さんたちは、自分の親御さんに対してどんな思いを抱いているんでしょう?
いやぁ、複雑でしょうがないんじゃないかな、と。虐待されても親は親なので、過去は美化されるところがあって。嫌なことがあっても「~~してくれた」「~~買ってくれた」っていう気持ちがあるので。こちらもなかなか踏み込めない部分ではあります。
―――お子さんたちは、親御さんの話題は出さないものですか?
積極的に言う子は少ないですね。親の名前もうろ覚えだったり、誕生日を知らない子もいます。
よく実習生からは、「自分の親のことを言ってもいいですか?」と聞かれます。全職員が同じように考えているかはわかりませんが、私は自分の親のことを話すタイプです。子どもたちが経験したものはスタンダードではないから、それを知っておかないと、自分が親になったときに同じことを繰り返してしまうかもしれないですし。「穏やかな両親がいるおうちもあるよ」ということを伝えておかないといけないなと、私は思っています。
自分の親についてはプライベートなことだから言わない職員さんもいますし、それぞれの考え方がありますね。
毎日鳴る入所依頼の電話。受け入れられない葛藤
―――現状の制度では、高校を卒業すると、施設も卒業ですか?
※施設で支援を受けられる年齢を22歳まで引き上げる方針が厚生労働省から発表されている
そうですね、高校卒業と同時に自立を目指して、子どもたちにも意識させるようにしています。事情があれば引き続き預かれるんですけど、子どもも甘えたくなってしまうので。
一時保護所で待機している子や、入所ができずにずっと待っている子もいるし。一時保護所もパンパンです。目の前の子も大事にしたいけど、まだ見えない子たちのことも考えないといけません。
―――入れなくて待っている子たちもいるんですね。
毎日のように、一時保護所から入所依頼の電話がきます。結構な数。
多くの場合、いまは定員がいっぱいだから難しいです、とお断りします。
―――虐待で亡くなってしまうお子さんがニュースになると、児童相談所がたたかれがちですが、保護しきれないような事情もあるんですね。
場合によっては。一時保護所も、枠に限りがあるので。最大2か月で出ることになっているんですが、預け先がなければ延長になります。一時保護所はつねに120%くらいの入所率で、窮屈な状態ですね。
児童相談所の方が家庭訪問して、緊急で「一時保護所に入れなきゃ」と判断しても定員オーバーで入れない場合は、一時保護委託というものがあります。登録されている地域の一般のご家庭が、一時保護の役割で預かるシ
ステムで、そちらに預けることもあります。
―――一時保護委託。存じ上げませんでした。どのようなご家庭が多いのでしょうか?
ご夫婦だけだったり、お子さんがいらっしゃったり、さまざまです。
※一時保護委託先として民間が運営する施設もある
―――一時保護の子と、施設に入る子との線引きはどこにあるのでしょう?
一時保護した後、ご家庭でも大丈夫そうだから戻る場合もありますが、入所できる枠がないので入れないというのが実情です。
男の子の枠しか空いていないのに「女の子を入れられますか」と聞かれても入れられないですし。施設内での性のトラブルも皆無ではなく、いま生活している子たちの安定も図らないといけないので。
―――じゃあ、施設に入れる子たちは幸運な子たちなんですね。
そうなんですよ。本人たちにその自覚はないんですけど(笑)
実家みたいに、ごはんを食べに帰れる場所に
―――卒業したお子さんたちとは、どんな関係ですか?
卒業してからも数年間は、担当者がアフターケアといってこまめに連絡をして様子を把握するようにしています。それがなくなっても、卒業した子がたまにお土産を持って帰ってきてくれたりします。
―――大人になってる(笑)
そう、敬語なんて使っちゃって~と思ったり(笑)。このあいだもエクレアを持ってきてくれました。
「だれだれ職員いる?」といわれたときに、たまたまいなかったり、あるいは辞めちゃったりしていることもあります。卒園後も帰ったら職員がいるのが大事だと思うから、私は残っている、という部分もあります。会いに来たのに、いなかったら寂しいと思うから。
私の理想としては、実家のような感覚で「ごはん食べていきなよ」って言えたらいいなって。コロナだからそれもいまは難しいんですが、世間話でちょこちょこと報告しにきてくれたら嬉しいなって思っています。
―――卒業したら、金銭的には完全に自活していかなきゃいけないんでしょうか?
福祉サービスはいろいろあります。
大学に通う子には、児童養護施設対象の奨学金も活用できます。課題作文が大変ですし、生活費は自分で稼ぐことになります。
また、施設にいる間の児童手当を貯金していて、通帳は施設が預かっています。子どもに持たせると使ってしまうので、紙にサインしてもらって、「施設で預かってるね。何かあったら、言ってくれれば渡すから」と伝えてあります。
―――大学へ進学されるお子さんも多いですか?
進学する子は、多くはないです。進学しても断念してしまうケースも多いかな。よほど芯が強くないと、卒園してアルバイトしながら勉強のモチベーションを保つのは難しいですね。芯が弱いと、必要なことを後回しにして、単位が足りなかった、ということも多いです。
―――生活費を稼ぎながら学業と両立することは難しいんですね。
難しいですし、入所している子は不登校の傾向が強いんです。
自分に合う投稿日数を考えて通信制を選んだものの、それも通えなかったり。単位が足りないときに、職員が学校にかけあうことで、なんとか進級できたという経験が、自分はこれからも大丈夫だろうって思ってしまう。職員がやってくれているありがたみがわかっていないから、その感覚で大学に進学してしまうと、進級できなくなってしまうみたいです。
―――難しいですね。職員さんも子どものためにやってあげたはずが。でも、それはどんな子にでも当てはまることかもしれないですね。
「やればできるんだ」と過信していたのが「そうじゃなかった」と、自立してから気づく子も多いですね。
学校に居場所があれば、毎日の登校につながる
―――不登校が多いとおっしゃっていましたが、中学校で増える印象ですか?
そうですね、中学校からが多いですね。
思春期でいろんなことが気になって、勝手に人と比較してダメだと思ったり、なんか合わないなと思いやすかったり。頑張ろうと思っても、自分が思ってるような評価をもらえないと「意味ないじゃん」と思って行きたくなくなってしまったり。
―――人間関係を原因にすることも多いんでしょうか?
自分の居場所があれば通えるけど、居場所がない子はいづらくなっちゃうかな。
部活で認められているとか、学力がなくてもクラスの中でキャラクターが立ってみんなを笑わせて「すごいね」と言われていたりしたら、ちゃんと通える子が多いですね。
―――不登校のお子さんには、どんな働きかけをされていますか?
自己肯定感が低い子が多く、勝手な思い込みで学校に行きたくない理由を作っているように感じているので、生活の中でさりげなく言うようにしています。学校を休んでも、おうちで勉強はしなきゃいけないので。めずらしく勉強をしていたら「ここ3年生になったらやるからね」と言ってみたり。
―――勉強も見るんですか(驚)
見ます。ひとりでは勉強できないので。
仕事の内容は、男女問わず「お母さん」みたいな感じなんです。ごはんを準備して朝「おはよう」、掃除しながら「いってらっしゃい」。夕飯作って、宿直の人が来たら子どもをお風呂に入れたりして。
不登校の子も勉強しないわけにはいかないから、ワークをして。
―――そのワークは、どこから入手するんですか?
市販の本を「これなら取り組みやすいかな」と選びます。子どもと一緒に買いに行くこともあります。
そんななかで、「中学校ってこんな感じだよなー」と独り言のように言ってみたり。興味を持って聞いてはくれます。「はい、勉強しましょう」という感じにしてしまうと、「お? 学校に行かせる気か?」と思われちゃうので、あくまで自分の体験談として伝えています。
―――高校よりも、中学のほうが、ギャップによる不登校は多いですか?
そうですね。中学は義務教育ですが、高校は通うか通わないかを自分で選択できるので。
なかには、高校生になるタイミングで自宅に帰る子もいます。中3のときに親御さんと施設で話し合いをして、親が迎えたい、子どもも帰りたいという話になれば、帰る方向で、高校もおうちに近い学校を選びます。
―――事情があって離れた家に、帰る……。お子さんの年齢が上がれば、親御さんとの関係性は変わるものですか?
変わりますけど、親も勘違いしちゃうんですよね。自分で育ててないから、変に期待をしてしまって、すごくいい子だって。帰ってきたらおうちのこと手伝ってもらおうとか。
子どもも親を理想化して、「こういうことしてくれるはず」と思ったらそうでもなくて、すれちゃったり。
お互いに理想化しちゃって、同居も難しい面はあります。でも帰れるんだったらそのほうがいいですよね。1人枠も空くので、新たな子を迎えられます。
「いろんなことが無駄じゃなかった」とわかるのは数年後
―――やりがいを感じるのはどんな瞬間ですか?
やりがいかぁ。あるけど実感する瞬間って難しいですね。
幼児さんのときに担当してた子が、再度自分の担当になったときに、母の日にプレゼントをくれたんです。100均で買ってきたツムツムのミッキーマウスのキーホルダーを「あげる」って、お手紙をつけてくれて。
値段もわかってるし、ほかの職員にお金出してもらって買いに行ったことも知ってるんですけどね(笑)。
実習のときに、高校生の子が職員を「お母さん」と言っていた話をしましたが、それを自分も体感できて嬉しかったです。
―――母の日っていうのが、嬉しいですね。

使い込んで色も変わってしまったけれど、お守りのように大切にしている。
あとは、卒園した子が「いまこういうことやっているよ」「就職したよ」って報告に来てくれるのが嬉しいですね。
いまやっていることの成果はすぐ出ないんですよね。いい結果になるかが見えるのは数年後で。いい報告がもらえると、いろんなことがあったけどそれが無駄じゃなかったなって。
みんな結構、失敗を繰り返しながら曲がり曲がった人生を送っているので、明るい報告は本当に嬉しいです。
―――こういうとき大変だな、って思われるのはどんなときですか?
子ども同士のトラブルです。
見えるもの見えないもの、トラブルは結構あります。
特に思春期は大人に反抗する特性がある時期なので、年齢が近い子が集まると、気持ちが大きくなるというか、やっかいなことにはなりやすいですね。
―――そう考えると、子ども同士の組み合わせは難しいですね。
かといって年が離れていると、小さい子は職員に甘えやすいけど、大きい子は職員に甘えにくくなっちゃって。大きい子が小さい子に嫉妬してしまうこともあります。大きい子は「甘えたい」と言えないので。
―――今回の本で先生がおっしゃってて印象的だったのが、中学生って女子も男子も、べたべた抱き合っているんですよね、と。もう親には抱き着いたりできないけど、まだ人と触れ合っていたい年齢だから、友だちと抱き合っているんだと思います、とおっしゃっていました。
中学生はじつはまだ甘えたいという気持ちを持っているんですよね。
ひとりになるのが怖いから、私この子の友だちよ、という感じで守られている気持ちになるかもしれません。
自分が親にしてもらったことを、子どもたちに
―――私自身、この本を作っていて、当時の自分を改めて客観視することが多々ありました。お子さんと接していると、自分の昔のことも合わせ鏡になって見えてくるものがありそうですね。
つねにあります。もうひとつ、施設職員になった理由としては、親から自分がやってもらったことを子どもにやってあげたいなっていう気持ちがあるんです。親への恩返し、親孝行じゃないけど、子どもに還元していけるかなって。
―――素敵! 親御さんにお話しされたことはあるんですか?
「あのとき、ごめんね」とか「ありがとう」とか話しますね。
施設で子どもにお弁当を作っているときに、卵焼きの味つけについて自分の親と大げんかしたことを思い出して、あとで「あのときごめんね」と謝ったり。
―――お弁当も作るんですか?
作ります。子どもがつまみ食いしに来て「今日のごはん何?」というような一般家庭のかたちがいいいよねという施設の方針で、各家で食事の準備をしています。
用意されたメニューに沿って作りますが、子どもが嫌いなものだったら作り変えます。唐揚げ、これまでに何キロ揚げたかな? っていう感じです(笑)
高校生は、お弁当か給食かを学校で選べるので、お弁当だったら作ります。子どもたちが寝ているころに作り、朝に温めなおします。
―――すごい、やらなきゃいけない分野が多岐にわたっていますね。
そうですね、おもしろいですけどね。
―――どういう部分がおもしろいですか?
いろんな子どもを見られるのはおもしろいですね。パターンがあるように見えて、それぞれ違うので。「このパターンはダメか」と思ったり。相性もありますし。
―――いくつかの接し方のパターンがあるんですね。
あるけど「合うかな? どうかな?」と、毎回チャレンジする感じです。ツンデレの子が多いですね。素直じゃないねぇ、っていう子が。みんな気づいてほしいタイプ。
―――それは、気づいているよサインを出すんですか?
出すとき、出さないときがあります。
親身な「どうしたの?」がマイナスになる場合も
たとえば、子どもが自傷、リストカットしたときに、「血出た」って腕を見せられて、ふつうだったら「どうしたの、なんかあったの?」って言っちゃうと思うんです。
でもそれをすると「自傷をすれば話を聞いてくれるんだ」って覚えちゃう。個別の時間を持てるっていう学びになっちゃうので。
手当はしてあげるけど、その場では何も聞かない。
後日、何かのときに「どうしたの?」とほかの人が聞くようにしています。
―――成功体験になっちゃうんですね。
そうですね、試してるんでしょうね。「この人は自分のこと心配してくれるのかな」って。
子どもはいろんな大人を見ています。親も、職員も、いろんな人がいるので。自分のこと大事にしてほしいし、心配してほしい、本当は自分の話を聞いてほしいって気持ちもあるから。
―――それは職員1年目に「気を付けてね」って先輩職員から言われるんですか?
1年目のときに、普段からやっている子がいたので、言われました。
傷つけたところは普通の考えだと「見せないほうがいいよ」と言いますけど。その子にとっては、見てもらいたいんですよね、隠したくない。
―――普段かわいがっている子が、そんな様子を見せたらつらいですね。
つらいですね。自分の宿直のときだけ、自傷が多いですっていうのを気にしてメンタル不調になる職員もいますね。自分の対応が悪いのかなって。
子どもは自分の感情ぜんぶに寄り添ってくれる人が欲しいので。
―――やっぱり、大変なご職業ですね。
そうですね、でも若いから治りが早いな~とか、自分だったらこの傷もう治んないよ、って思ったりもします(笑)
子どもと一緒にSWITCHのゲームをやって遊んだり、おもしろいことも多いですよ。
―――Kさんはお子さんに楽しんで接してらっしゃるから、お子さんたちもきっと楽しいですよね。長く仕事を続けられる秘訣かもしれないですね。
変に目標を高く持っているほうが、つぶれやすいかもしれません。うまくいかなかったときに崩れてしまうというか。
―――施設の子どもたちだけじゃなくて、後輩の育成もしなきゃいけないんですね。
そうですね、人が少ないから長くいてもらいたいし。
―――両方に気を配りながら。
そうですね。でも、おもしろいですよ。
子どものなかには大人の感覚でモノを言ってくる子もいるんですけど、大人が楽しくにぎやかにしているほうが、子どもらしくいられるのかなって思います。
なかには、子どもに理不尽な仕打ちをされても、飲み込んであげて、仕事だって割り切ろうとする人もいます。でも、のちのちメンタル不調になりやすいですね。
だから理不尽だなって思ったら、「違うだろ」ってちゃんと突っ込んだほうがいい。子どもが大人になって社会に出るときに、身につけておいてほしいことを見据えて、大人がダメなものはダメって教えてあげないと、勘違いしていくだけになっちゃう。
言葉のチョイス、伝え方は大事ですね。
日ごろから「気にかけているよ」のサインを
―――それは長年、お子さんたちと接していく中で見つけていったものですか?
経験ですね。受け止めていくだけだとダメだなって。いろんな人のパターンを見て。
ダメなものを直接「ダメでしょ」って言っちゃうと反発しちゃうので、私は冗談で返す感じにしています。笑いながら「こんなんじゃ全然違うよ~笑」って言うと「そうだよね」って。
―――高等テクニック! 難しいですね。
子どもたちは否定されたっていう感覚になると、聞いてくれなくなっちゃう。笑ってくれたら、伝えたいことは子どもの耳に入っているから、ひとまずOKというか。
―――それは親御さんたちも参考になりますね。
言える関係性というのもありますね。その子のキャラクターもあるし。
さっきの話のように、まだ中学生は甘えたい年代なので。冷たくされても「気にかけているよ」のサインは出して、いざというときに話せる関係をつくっておくことが大切かなと思います。
*
施設内での大変なお話のなかでも、Kさんが何度も「楽しいですよ」とおっしゃっていたのが、とても印象的でした。
子育ての渦中にいると、大変に感じることも多いですが、Kさんのように客観的に楽しむ視点を持てれば、数年後に「いろんなことが無駄じゃなかった」と思える未来がくるのかもしれない、と感じました。
子どものわかりやすい変化・成長がすぐに見えなくても、焦らず、毎日を楽しめたらいいですよね。
『中学校ってどんなとこ?』は、お子さんだけでなく親御さん、学校の先生からも「参考になった」という声を多くいただいています。こちらも、みなさんのお役に立てば幸いです。
全3回の連載は今回で終了です。ありがとうございました!
第2回「中学入学準備の本が欲しい」というKさんのお話はこちら。
◆総監修
升野伸子(ますの のぶこ)
筑波大学附属中学校 副校長
公民科教育・ジェンダー論 東京大学経済学部卒業。お茶の水女子大学修了。大妻中学高等学校教諭を経て、現職。共著とし『女性の視点でつくる社会科授業』(学文社))『入門 社会・地歴・公民科教育―確かな実践力を身に付ける』(梓出版社)『中学歴史 生徒が夢中になる!アクティブ・ラーニング&導入ネタ80』(明治図書出版)など多数。
◆第 4 章監修
多田義男(ただ よしお)
筑波大学附属中学校 教諭
教科:技術・家庭科(技術分野)
東京都公立学校主幹教諭などを経て現職。情報学に関する研究、道徳教育に関する研究、授業実践多数。東京都を中心に研修会の講師を務める。
◆第 5 章監修
道幸玲奈(どうこう れいな)
筑波大学附属中学校 養護教諭
東京都公立中学校での勤務を経て現職。自分も相手も大切にできるいのちの教育に取り組んでいる。
