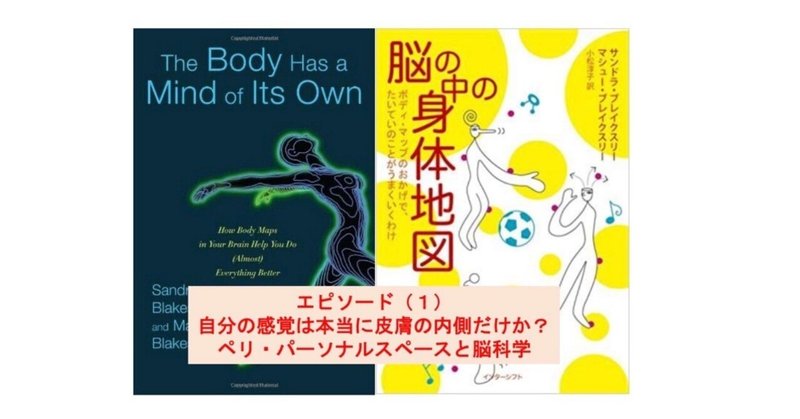
エピソード(1):自分感覚は本当に皮膚の内側だけなのか?ペリ・パーソナルスペースと脳科学
自分の意識や認識は、生後の自分の生い立ちやその周囲との関連を背景としていて、我々自身は確たるものとして疑わない。
しかし、最近の脳科学では、意識や認識は必ずしも現実ではなく、自分の脳のなかの神経の演算結果を、自分の論理で合理的に提示したものだ(つまり辻褄合わせをした)と考えられている。
自分とはイリュージョンの積み重ねかもしれない。
こうした意味で、座って行う西野流呼吸法のimaging法「身体の中心」、あるいは「皮膚を超えて周囲に溶け込む」というイメージトレーニングは面白い。
西野流呼吸法での周囲イメージは、自分自身が周囲に溶け込んでいくイメージである。
しかし、自分の溶け込んでいく空間(ペリ・パーソナル)は、道具の使用による脳内の自己拡張という新たな研究展開を含め、脳科学として非常にエキサイティングな課題でもある。
脳科学で身体論の何が明らかになりつつあるのか?
最近のSandra & Matthew Blakeslee母子による「The body has a mind of its own」(Random House、 2007)(日本語訳:「脳のなかの身体地図」、小松淳子訳、2009、インターシフト)が参考になる。
日本語訳のタイトルの意訳が示すとおり、この本は身体論の本である。
Bodyとmindは別物ではない。心は身体に繋がっている。
あるいは身体そのものに心がある。こうした意味で「身体知」という言葉を西野先生は全く独自に使っている。
しかし、筆者らの謝辞にもある通り、この本にはあまりにも多くの情報が盛り込まれている。通読するだけでは新規事実群の中で迷子になってしまう。
また膨大な情報の元の文献がまとめられていないので、興味を持ったら自分でPubMed(米国の医学関連文献データベース)を検索して見つける必要がある。
この中には、文化的背景、民族的背景などがペリ・パーソナルスペースや、その色、臭いなどにも深く関与すると述べられている。
自分と言うものが作り物であるから、当然文化的背景で相違していいのだろう。
例えば、アフリカ西海岸の砂漠に住む「Himba族」は油脂と香料と赤土を体表に塗り、赤い皮膚の女性として観光でも有名である(Wiki、英語版、リンク、https://en.wikipedia.org/wiki/Himba_people)。彼等は自分の身体の周りにシャボン玉のようなペリ・パーソナルスペースを使いこなして、接触したり、融合して生活していると述べている。
あるいは、日本の理科学研究所の入来篤史氏の熊手を使うマカク猿の関連脳領域の変化も取り上げである(理研、リンク、https://www.bdr.riken.jp/ja/research/labs/iriki-a/index.html)。
我々の皮膚の内側の身体感覚を、道具使用によってより空間的に広い脳領域にまで取り込むことが可能である事実の、脳科学的な証明である。
実際、毎日運転する自動車が、道の角の障害物に当たるかどうか?自分の皮膚感覚には及ばないが、習熟によりかなり判断が向上するのは事実である。
すなわち自分の身体感覚が自分の車の外側まで広がっている。
実は、本noteが取り上げる「不思議」な呼吸法の基礎、「足芯呼吸」による身体イメージは、こうした脳科学による説明が将来的に必要となる。現段階ではそこまでいかない。
そこでBlakesleeらは彼らの著書の中で
”When you work with instructors of
dance,
yoga,
tai chi,
Pilates,
Alexander Technique,
Feldenkrais,
or dozens of other kind of movement training,
you are basically working on body schema awareness. These methods teach you to purposefully attend to the many core elements of your schema as a means of self-exploration”(同書、p37)と記している。
次に述べるように、「足芯呼吸」において、身体各所をイメージし、意図的に注意を払うことは、脳科学的にも意味のあることである。
ここにいうように自分の身体の中を探索することである。多くの身体操法がかかるイメージを使っている。
(追記:先に記したようにこのnote原文より後に、「呼吸臨床」に連載した中では、第8回にbody awarenessに関して、interoceptionやその中枢としてinsula(島皮質)に関して述べた。参考まで。リンク、https://kokyurinsho.com/focus/e00077-2/)
将来的な脳科学の研究展開はどうあろうと、実践せねば始まらない。
結局は自分が実際に自分の身体、あるいは相対する人間の身体を感知して、自分の身体がそのsensingに反応するようになる。この過程として、この足芯呼吸によるself-explorationを実行する以外には、決して身につくことは無い。
30分に渡って繰り返す身体imagingを、「不思議」な呼吸法稽古として面白いと感じて続けるか、あるいは証明がないから胡散臭いと避けるかは、個々人の主体的な問題である。
しかし知的訓練ではなく身体訓練であるので、稽古しなければ、あなたの身体の中にある未知のプログラムが目覚める事は、決して起こらない。
Subcorical(皮質下=旧脳)に働きかける手段は古来の伝承にしか、現時点ではない。
これが伝承の意味であるが、同時に新規な方法論も待たれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
