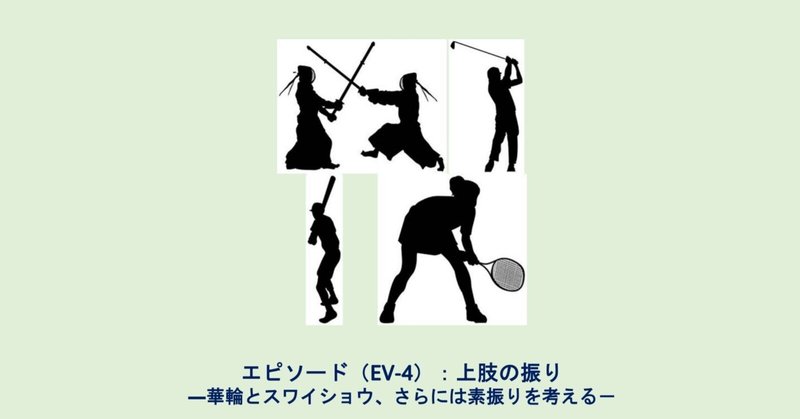
エピソード(EV-4):上肢の振り ―華輪とスワイショウ、さらには素振りを考える-
華輪に似て上腕を振るスワイショウは、古くから太極拳や中国拳法の訓練に取り込まれている(日本では漢字がないのでスワイショウとカタカナ表記される)。その訓練手法はかなり歴史が古いと考えられる。
具体的には両腕を揃えて前後方向に振ったり、あるいは交互に振ったり、西野流呼吸法で行う軸を中心とした回旋運動とはまた異なる脱力への方法である。
ものを放るようなイメージで行うという。
実際の動きはYouTubeなどで多数の例を見ることができる。
同じような回旋運動はラジオ体操にも一部取り入れられている。
しかし西野流呼吸法では同じ動作を数百回も行う点が異なる。
両手の脱力感などの感覚は、長時間(約5分間)回旋運動を繰り返す動作で生じるのでないかと考えられる。
先の上段の華輪で詳しく述べたが、脊椎動物進化史上、下肢、上肢は魚類の腹鰭、胸鰭が、さらに陸上進出で四肢に進化したものである。
脊椎動物の祖型としてのヤツメウナギの体軸クネクネ運動に、進化上新たに加わった構造と機能である点は、Grillnerの総説の図で解説した。
(MMC(内側細胞柱)、LMC(外側細胞柱)の項を参照:西野流呼吸法総本部YouTube、Powerpoint録音第1回YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=DE4uY-1dZ9E&t=748s)
これらの脊髄神経内の神経細胞群は21世紀になる頃、分子生物学的手技で同定された、非常に新しい理解である。
東洋系Bodyworkの華輪やスワイショウという「不思議」な稽古は、こうした脊椎動物の上肢から体幹筋群構造に連携させる働きかけではないか、と私は予想している。
日本人として思い出すことはありませんか?
そう剣道の素振り伝承です。
これは何を訓練しているのか?
しかし今後この伝承は、世界的に注目される可能性があるのではないか?
すなわち先ほどのMMC(体幹筋群運動神経)、LMC(四肢筋群運動神経)を考えると、両腕の動きを体幹筋群の筋力へ連携させる訓練と考えられる。
以前記載した文献中に、現時点で考えるとこの連携現象だと理解されるものがあります。
(呼吸臨床連載第5回:西欧のBodywork探究が切り開いたFascia医学とAnatomy Train、図5(通読するにはID/PW登録が必要)、URL:https://kokyurinsho.com/focus/e00066/)
他にも素振りの伝承は現代スポーツの多様な部分に広がっていますね。
テニス、ゴルフ(NHKの筋肉体操(谷本氏)でも最近取り上げていたURLhttps://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pwrdojn7MR/bp/pd0a4XDvAj/)
最も大きな成果は、実は米国大リーグ大谷翔平氏ではないか?
賛否の多い、中学・高校時代からのバット素振りには、運動学的根拠があるのでないか?
世界的に注目されるとすれば、日本の伝承「素振り」のメカニズムでしょう。
なぜ素振りの動きが、体幹筋群構造を連携できるのか?
あるいは体幹筋群を覚醒できるのか?
このnote記事でどこかで議論したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
