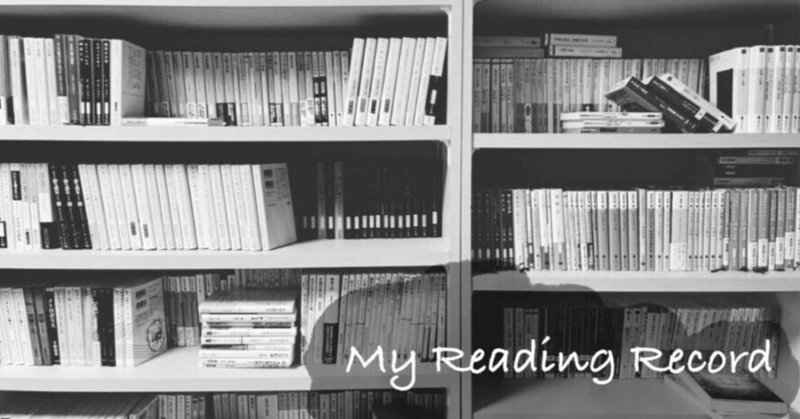
デレラの読書録:金原ひとみ『アンソーシャル ディスタンス』

金原ひとみ,2024年(単行本2021年),新潮文庫
アルコール、美容整形、化粧、不倫、SNS、コロナ禍、自殺、セックス、激辛料理。
多彩なテーマが取っ替え引っ替えに繰り出され、描かれる五つの短編。
現代日本を生きる登場人物たち。
各作品は独立しているが、彼らは「ある感覚」を共有している。
登場人物たちが共有する「ある感覚」とは何か。
それは「不能感」である。
つまり、コントロールの不能感だ。
人間は多かれ少なかれ不能感を抱える。
管理可能/不可能の境界は人によって違うし、時代によっても違う。
わたしはコンビニでおにぎりの具を選べるが、おにぎりの値段は変えられない。
日の出を見に行くかどうかは決められるが、日が昇ってくること自体は選択できない、日は勝手に昇る。
自己決定できる範囲は大して広くない、むしろ自己決定できない範囲の方が圧倒的に広いだろう。
近年の流行病は自己決定の範囲をさらに狭くさせるように働きかけた。
神経質的な視野狭窄である。
それは流行病に限らない。
恋愛のような、ある種の思い込みを作動させる精神活動もまた視野狭窄へ向かう。
自己決定、自己管理の不能感に苛まれたとき、人はどうするのか。
この問いに対して、金原ひとみは「身体へ介入することでそれに抗おうとする」と回答するのではないか。
本作に限らずそういう表現が目立つように思う。
身体への介入。
つまり、スプリットタン(デビュー作『蛇にピアス』)に始まる身体改造である。
本作の身体の介入は、アルコールによる酩酊、美容整形による顔貌の改造、化粧、手指消毒やマスク、自殺、ハメ撮りなどの身体撮影、激辛料理による口唇・発汗・肛門の痛み、位置情報を共有するSNSなど、多岐にわたる。
人は自己を見失うとき、その存在論的不安が身体改造への欲望に転化する。
当然、金原ひとみは、その身体改造への欲望が「悪いこと、良くないこと」だと短絡的に表現しているのではない。
むしろ、身体改造が、人にとっての最後の砦である、と表現しているのではないか。
視野狭窄に陥っていることに気がつかせること、あるいは、視野狭窄の中でなんとか生き延びる術として。
コントロールの不能感に陥った絶望の中での、最後の希望。
その一筋の光としての身体への介入。
不能の絶望感の中で、神経質的に陥る視野狭窄と、身体介入がもたらす一瞬のコントロール感に救われることのリアリティによって、わたしは身体改造する登場人物たちに共感してしまうのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
