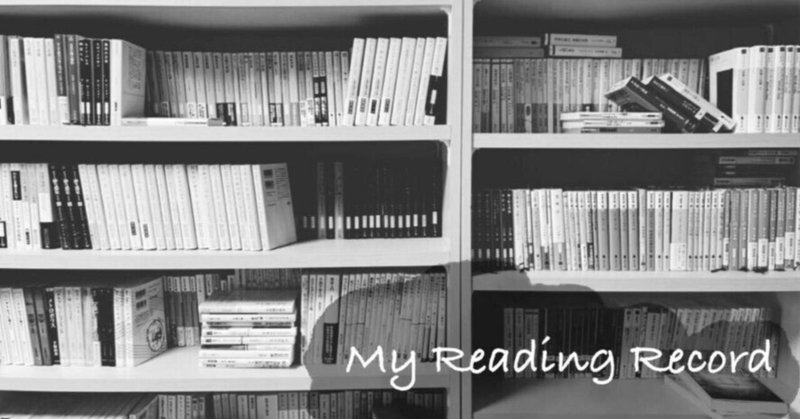
デレラの読書録:宮内悠介『スペース金融道』

宮内悠介,2024年文庫化(2016年単行本),河出文庫
人類最初の植民惑星・通称「二番街」で繰り広げられるSF×闇金取立屋のエンタメ作品。
アンドロイドに高金利で金を貸し出す「新星金融」。
そこで働く取立屋コンビのユーセフとぼくが奇想天外なSF設定を駆け巡る。
面白いのはアンドロイドの設定の塩梅だ。
どういうことか。
「アンドロイド」はSFでは古くから使われているモチーフだ。
広義のSFは、科学的な設定や思弁的な設定を持ち出して、「人間とは何か」とか「社会とは何か」を逆照射するようなところがある。
ようは「アンドロイド」は、SFでは「人間や社会とは何か」を問うためのモチーフでもあるのだ。
というのも、まさにアンドロイドは「人間のような形をした人間でないもの」であるからだ。
従って、アンドロイドのSF設定上の役割は、人間がやりそうなこと、できないこと、見た目の違う人間、つまり、人間の境界性を際立たせることにある。
では、『スペース金融道』ではどのように描かれているのか。
『スペース金融道』の世界では、アンドロイドは人間に差別されていて、危険で不安定な職に就いている。
そのため大手金融機関では金が借りれず、闇金である(主人公たちが働く)新星金融で金を借りることになる。
取立先ではアンドロイドの事情や思惑、屈折があり、物語をドラマティックに仕立てている。
さて、特に面白いのがアンドロイドに刷り込まれている「新三原則」だろう。
一つは、スタンドアロンであること、二つは、経験主義を重視すること、三つは外部のグローバルネットワークに接続できないことだ。
特にいい味を出しているのが第二条の経験主義の重視である。
どういうことか。
本書の説明はザックリしている。
あまりに合理的だと人間っぽくないから、経験を重視しましょうね、というものだ。
経験した因果律を重視する、つまり、成功と失敗を重視する。
ようは、アンドロイドは過去の体験に密着しているということ。
当然これは、人間はそういう生き物だ、ということを示している。
SFにおいて、アンドロイドは、人間のメタファーなのであった。
機械知性なのだから人間より賢いだろうと連想するのが普通だが、本書では、アンドロイドは、自分の考えに固執し、騙され、利用され、傷つき、極端な思考に振れさえする。
あまりに人間的なので、アンドロイドであることを忘れてしまう。
展開のテンポの良さ、賭博やミステリなどの多様なモチーフとエンタメ性の裏には、ウィットに富んだ人間社会への批評性が本書にはある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
