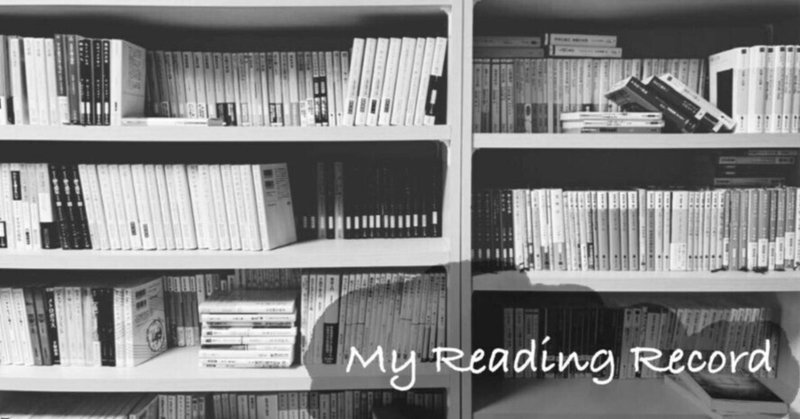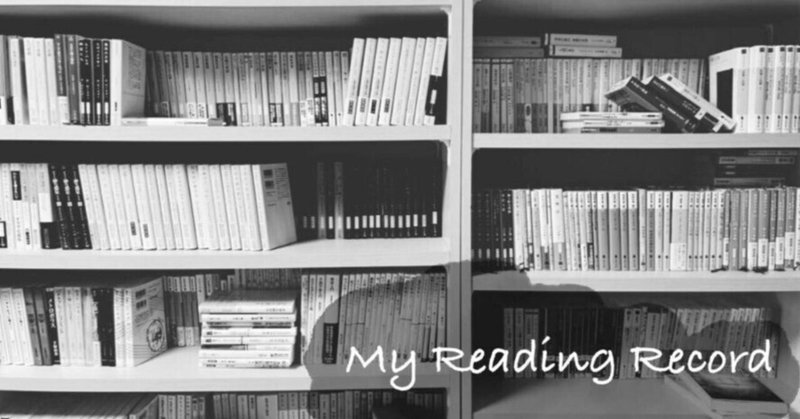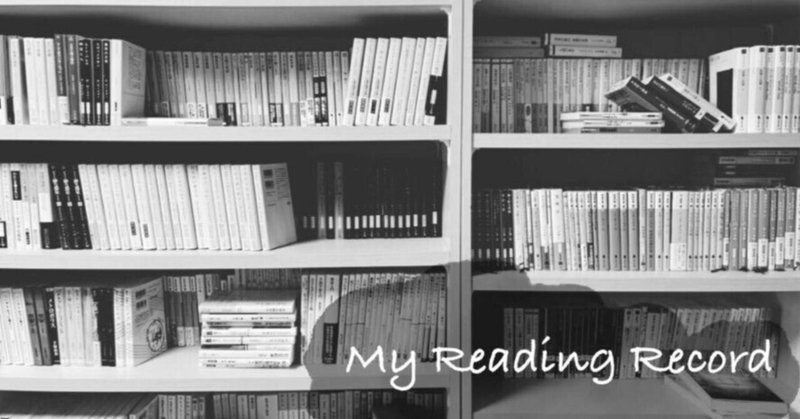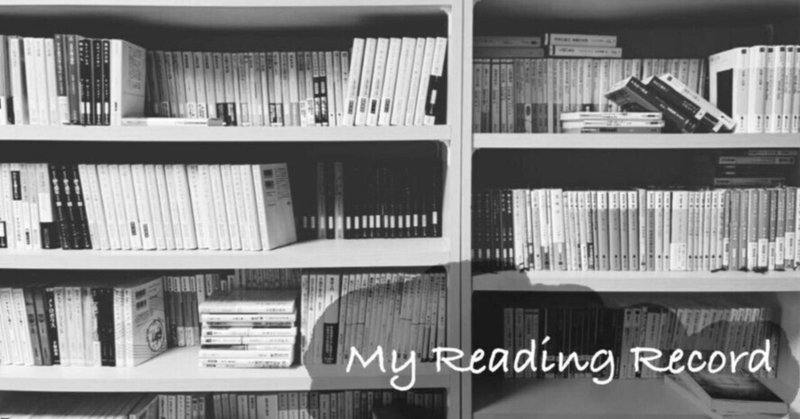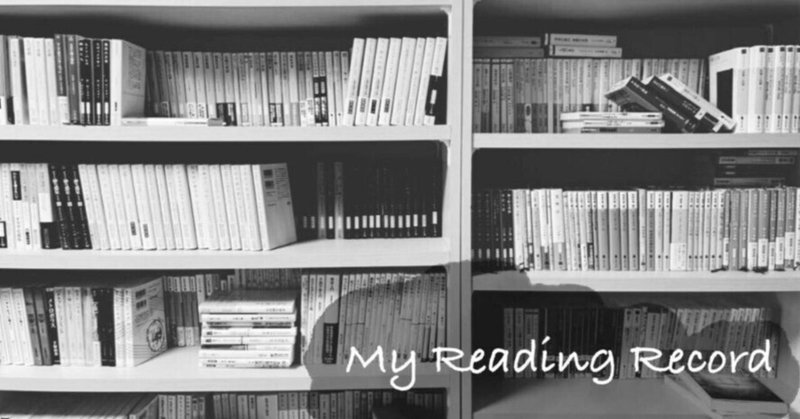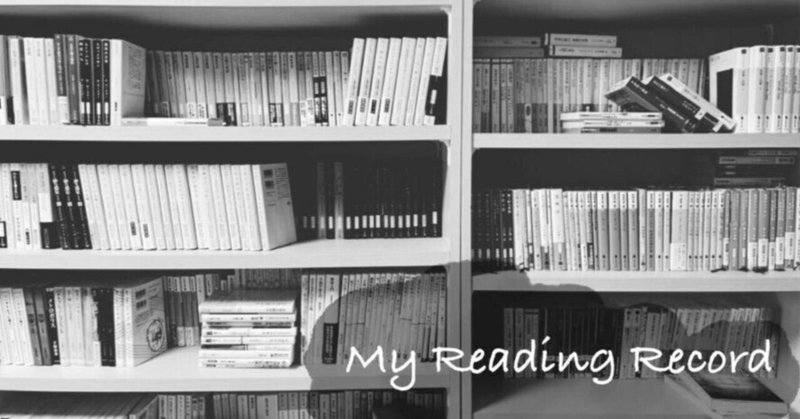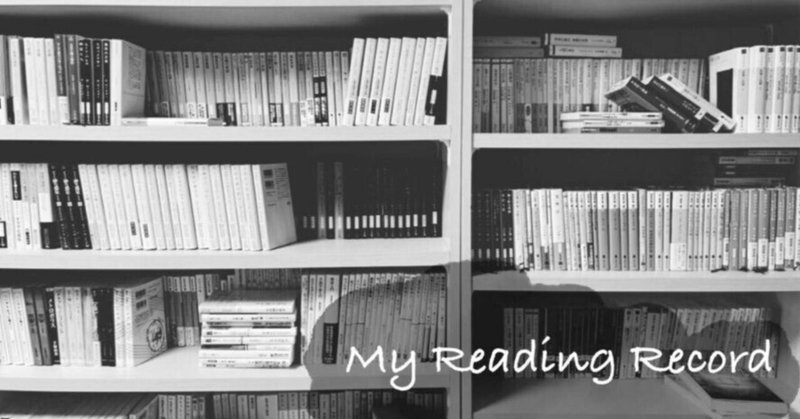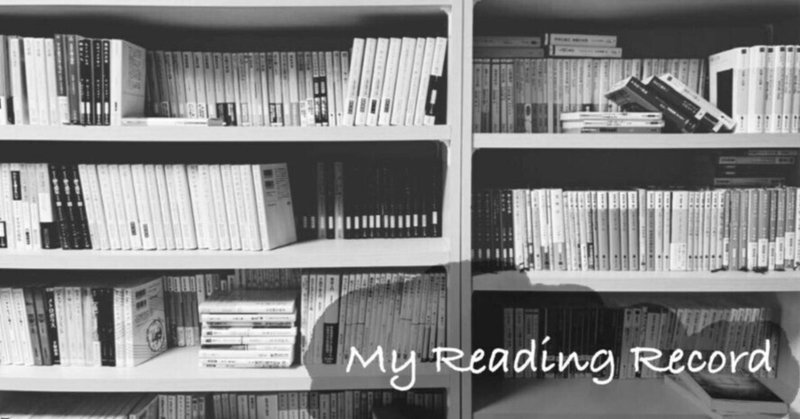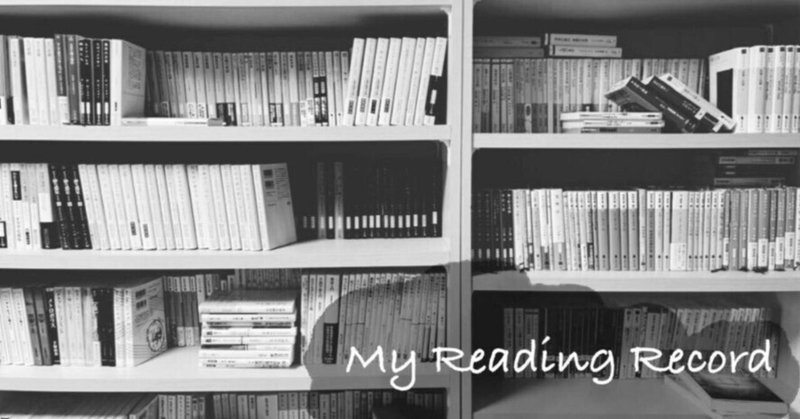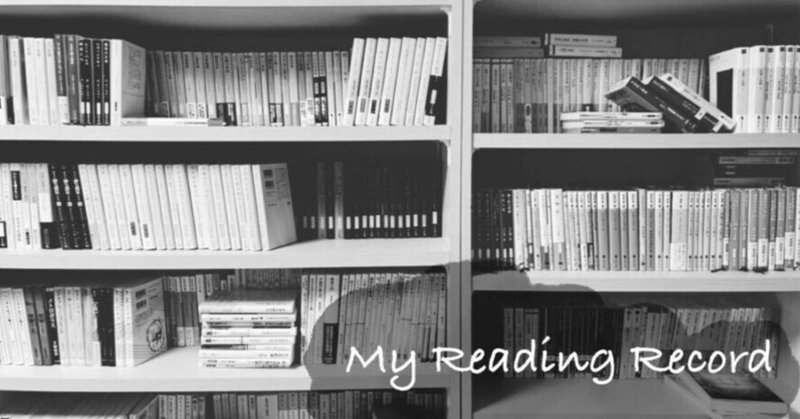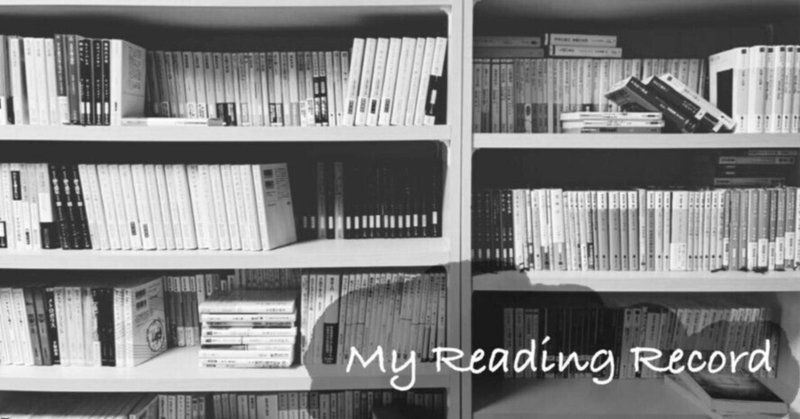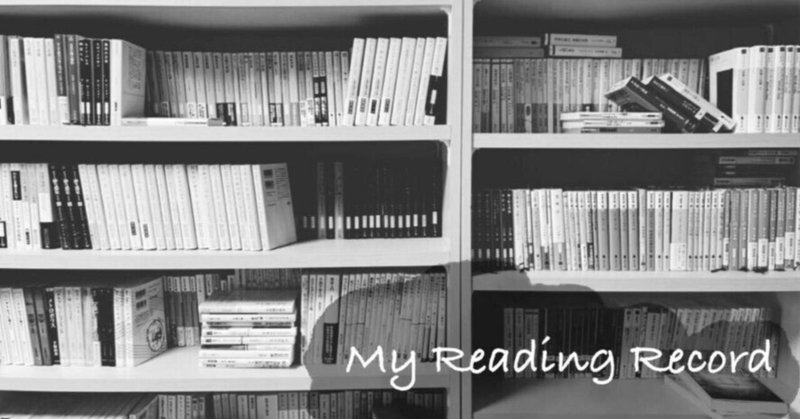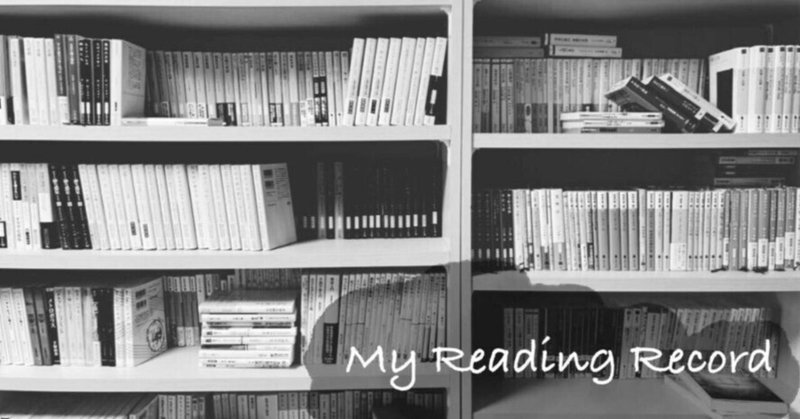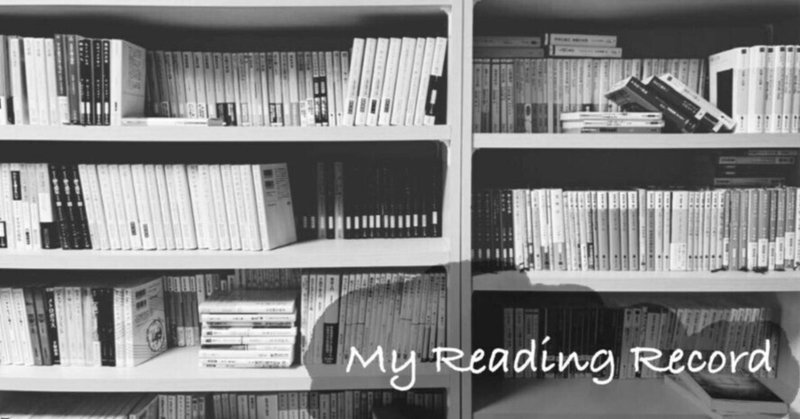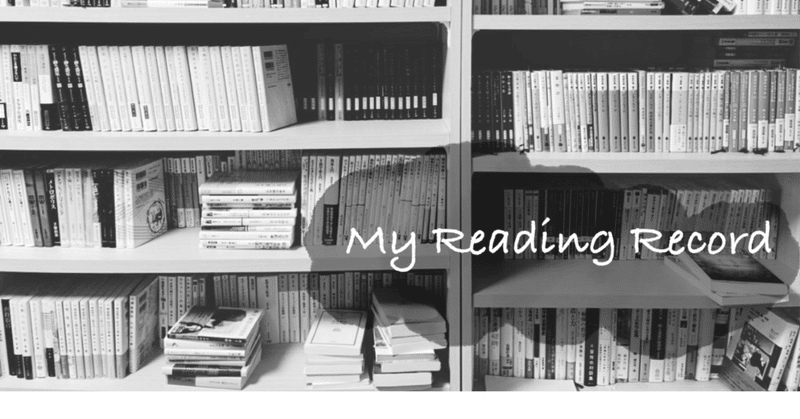
- 運営しているクリエイター
記事一覧
デレラの読書録:フランク・ハーバート『デューン砂漠の救世主』
砂の惑星アラキスを中心に描かれるSF大河小説デューンの第二巻。
第一巻で、ハルコンネン家の陰謀に打ち勝ち、帝座に着いた主人公ポール・アトレイデス皇帝の統治から12年。
帝王となったポールの運命の物語である。
ポールが帝座についたのは、もとは砂の惑星アラキスをめぐる覇権争いのなかで、一度は全てを失ったポールが、原住民族であるフレメンと共闘してハルコンネンおよび皇帝を打倒することの延長線上にあっ
デレラの読書録:フランク・ハーバート『デューン砂の惑星 下巻』
ついにポールがハルコンネン家に復讐を果たす時が来た。
ポールは産砂の命の水を飲み、クウィサッツ・ハデラックとして覚醒した。
クウィサッツ・ハデラックとはベネ・ゲセリットの信じる、いわば救世主だ。
ポールは救世主となった。
クウィサッツ・ハデラックは時空を渡って遥か遠い過去を振り返ったり、現在から先、枝分かれした未来の世界線をはっきりと見ることができる。
砂の惑星アラキスで産出される香料メ
デレラの読書録:フランク・ハーバート『デューン砂の惑星 中巻』
砂漠に逃げ延びたジェシカとポールはハルコンネン家に憎悪を抱くフレメンと共闘しようと近づく。
必然的にポールたちとフレメンは出会う。
かつてベネ・ゲセリットが残した予言の通りに、二人がフレメンに受け入れられるまでの物語。
生き延びるためにはフレメンと共に生活しなければならない。
しかし、その道は悲惨で陰鬱な聖戦へと繋がっている。
民族が戦争で勝利を手に入れるために自らの身体を賭す。
大量
デレラの読書録:フランク・ハーバート『デューン砂の惑星 上巻』
SF小説の金字塔、壮大な大河作品。
香料の産地「砂の惑星アラキス」で宇宙を統治する大貴族であるアトレイデス家とハルコンネン家が衝突した。
両家の衝突は宇宙に何をもたらすのか。
鍵となるのは原住民族のフレメンである。
宇宙を統べる帝国の帝王皇帝、救世主を信仰する女子修道会ベネ・ゲセリット、覇権を狙うハルコンネン家、善政を目指すアトレイデス家、利権に群がる領主議会と大公家連合、宇宙ギルド、砂の