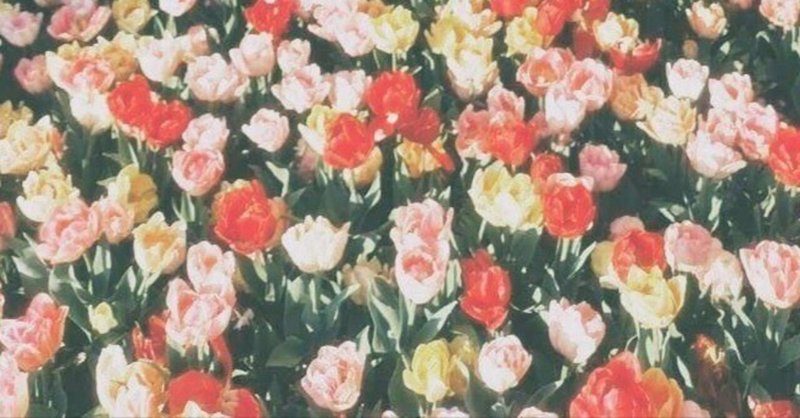
彼の語る「本の思い出」は、とても尊い
彼の語る本の思い出は、とても尊い。
江藤淳氏の『なつかしい本の話』を読みながら溢れでるそんな気持ちが、しぜんと私の口角をあげ、私にこの本を抱きしめさせるのです。
読んだことはないけれど、江藤氏の書く文芸批評は、きっと私の貧弱な読解力と知識量では太刀打ちできないものだろうと思います。
読書量でさえ、彼の足元にも到底及びません。
でも、少なくとも、この『なつかしい本の話』の江藤氏の文章には、私は親しみの微笑を向けることができる。
なぜならば、江藤氏は、本を愛しているひとだから。
私よりも、もっとずっと、本を愛しているひとだから。
それがひしひしと伝わってくる本だったから。
私が『なつかしい本の話』のことをすきになったのは、紹介される本たちがすべて、当時の江藤氏の生活や思い出と密接に繋がりあっているからです。
自己の内面や水面下での葛藤に溺れそうになったとき。
若い自意識の真っ只中にいた彼の身体に纏わりついていた、戦後日本の空気と、そこに名状しがたい感情を抱いたとき。
病床にあってせつなかったとき。
そんなときに出会った本と、出会ったひとたちのこと。
江藤氏が本の記憶を紐解くとき、そこで語られるのは、その本に書かれている物語についての感想ではありません。
彼が本の話をするということは、それはつまり、その本とともに息づいている、彼自身の個人的な諸々の記憶について語る、ということでもあるのです。
一冊一冊の本が、江藤氏の精神と記憶に深く結びついていて、だからこそ本は、ただの本ではなくて、唯一の、かけがえのない一冊となってゆく。
まさに、人生とともに本がある、そんな関係性。
そこにあるのは、どこまでも純粋な本への愛と、渇望と、知的好奇心だけなのです。
私も、めぐりあえた本と、すてきな関係を築いてゆけたらいいなあと、そんなふうに思いました。
