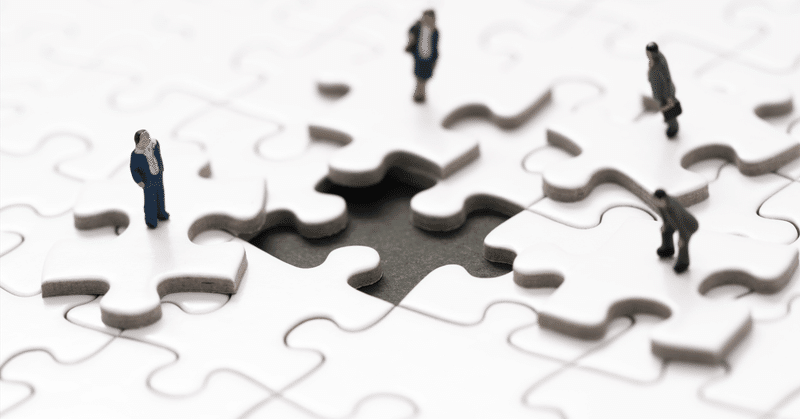
あるデータマネージャーのキャリア
はじめに
近年DXやAI活用が推進される中で、データマネジメントをミッションとした部門の設立が増えてきた。
自分もデータマネジメントをミッションとする部門に属しており、いったいどんなキャリアの人が所属しているのかというのが事例としてあまり公開されていないため、本記事では自分のキャリアを記載します。
データマネジメントの進め方
今すぐわかるデータマネジメントの進め方
著者のDMBOKを用いてCDO室を立ち上げデータマネジメントを推進した経験を基にデータマネジメントの進め方をまとめたkindle本を執筆しました。
データ組織立ち上げ編 AI事務員宮西さん
著者のデータ組織の立ち上げ経験をマンガ+コメントでまとめてみました。
無料公開のため0円となります。こちらもkindle本になります。
職務経歴
大学時代から現在までの職務経歴をずらずらと記載。
どんなチームで、どんなことをやって、どんなスキルを身に着けたのかを書いていく。
大学・大学院時代
情報系の学科を卒業してそのまま大学院へ進学。
大学院に進学したがもっと学問をやりたいというモチベーションではなくもうちょっとロハスな生活したいという不純な動機のほうが強かった。
研究テーマはレコメンドをやっていたが、今記憶にあるのは協調フィルタリングとTF-IDFという単語くらい。
その後、データサイエンスが流行り機械学習の仕事をやることになったので分野としての筋は悪くなかった。
卒業は無事にできてIT企業へ
メッセージングアプリのバックエンド開発
配属されたのはLINEのようなメッセージングアプリのバックエンド開発。
開発と言ってもローカライズだったため、あまりコードは書かず今で言うインフラエンジニアに近い業務だった。
FreeBSDだったのでUNIXサーバーのコマンドやパッケージ管理、クライアントサーバーシステムの考え方とかを覚えた。
この時は学生気分が抜けず、できの悪い社会人だったと思う。
タスクフォースのため広告チームに異動に。
検索連動広告、ディスプレイ広告の業務システムの開発
異動先はアドプラットフォームの部署。
この時代は純広告と呼ばれる特定の枠を買う広告から、運用型広告と呼ばれる配信枠があり何かしらのロジックで決まった広告が出る広告へと変わる境目の時期であり、運用型広告を作るために各所からの大量の人数が集められた。
最初の状況はまさに烏合の衆であり、もともと30人位のチームに100人位寄せ集めたので相当統率が取れてなかったことを覚えている。
最初はCSさんが使う業務系システム開発だったので酷いコードを書きつつ、コードの書き方の基本を教えてもらった。
PHP+OracleでフレームワークはSymphonyを使っていて、フロントエンド開発の進め方とかを覚えた。
烏合の衆だったため、タスクのアサインがうまくできておらず1年位はずっと暇だった。
ここまではまだ学生気分だった。
暇してた中、お金が好きだった自分は課金処理の調査を任されてそのまま課金処理のチームへ行くことに。
検索連動広告、ディスプレイ広告の課金処理のバックエンド開発
隣りにあった配信システムと管理システムの予算管理を繋ぎこむシステムの部署に引っ越しした。
この時期は、会社の大きな転換期の一つでありビジネス判断により検索連動広告システムを切り替えることになった。
烏合の衆は変わらない状況だったが、ビジネス要件として期日だけは決まっており取り組まざるを得ない環境により烏合の衆から洗練された組織へと変わっていった。
この時はメインはPHP+Oracleは変わらなかったけど、PLSQL、ストアドプロシージャー、シェルスクリプト、Perlとかを使ってデータベースの操作を中心にやっていた。
洗練された組織になった状況で、データベース設計やクラス設計を、つよつよエンジニアにレビューされたのはかなりためになって、この時エンジニアとしての思想が身についたと思う。
この時エンジニアとしては一番成長して、やっと学生気分が抜けて仕事ができるようになった気がする。
一方で、つよつよエンジニアの強さと、ビジネス側とシステム側が完全に分けられており下請け企業さながらの関係だったため、エンジニアはつまらないなと企画職へと社内異動の公募に申し込んだ。
金融Webメディアのディレクション
異動先は金融Webメディアのチームで企画、エンジニア、デザイナーが計15人くらいのチームで一つのサービスを運営しており、打って変わってベンチャーのような感じだった。
職種の変更のため、半年くらいは何でもやっていてサービスのことを学ぶ時間に当てられた。
この時は金融Webメディアとのシナジーが生めそうだということでFX事業が買収された。
最初にディレクションをしたのはそのための為替ページのリニューアルで、この当時FXが流行り始めた時でシナジー効果を期待して、投資メディアの2本目の柱としてリニューアルを行った。
ユーザーの閲覧ログから出すレートを決めたり、ニュースを掲載するためにニュース配信企業に交渉しにいったりと今で言うプロダクトマネージャーのような仕事をしていた。
エンジニアリングがわかるディレクターとしての立ち位置を築けた。
仕事の仕方はエンジニア時代に鍛えられていたため、すんなりと戦力になれた気がする。
このままFX連携の担当者に。
FX事業買収によるシナジー効果創出担当
為替ページを為替・FXへのリニューアルが終わり本腰入れてシナジーを生むことを期待された。
為替ページの担当だったこともありそのままシナジー効果創出担当にアサインされた。
具体的にWebメディアとのシナジーとは何かというと、わかりやすいのは口座の開設件数があげられるだろう。
この時はただバナーを置くことから始まって、バナーを置いただけでは見向きもされず間に挟むコンテンツの作成も行った。
毎日数字見て対応するという今で言うデータマーケティングとコンテンツのプロデューサーをやっておりWebマーケティングを身に着けたのはこの時。
最終的にはメインの獲得チャネルになるまでは成長させた。無意味な広告貼っつけても意味がないということを学んだのと予実を見てギャップを追うのは楽しかった。
新規事業立ち上げの担当者が不在だったため、お鉢が回ってくることに。
金融Webメディア新規事業、アメリカ株立ち上げ
矢継ぎ早に3本目の柱を作るべくアメリカ株の掲載企画が進んでいた。
構想はあるもののWebメディアに載せるために具現化する人がいないかということで主担当になることに。
構想は決まっていたけど、契約からスタートだったのでほぼ立ち上げから運用まで一通り主担当として実行できた。
この企画は社外にもステークホルダーが多く、制約も多かったため、社外とのコミュニケーションを学べた。
ステークホルダーが多かったため外部との約束事も増えてしまって、まさに炎上案件にしてしまいエンジニアの皆様には非常に迷惑をかけた案件だった。
この件では心身共に死にかけたのでサイヤ人のように鍛えられた。が、もうやりたくはない。
お金が好きだったので金融Webメディアのビジネス責任者へ
金融webメディアのビジネス責任者
この時は主要KPIごとに責任者を置くという組織設計になっており、サイトとアプリのUUとお金の2つに責任者が設置された。
自分はお金が好きだったのでビジネス責任者にアサインされた。
Webメディアの収益は主に広告売上とアライアンス売上と個人売上になっている。おそらくどのサイトもそう。
しかしどの売上も、稼ぐためにはユーザーへの負担を強いることになりそのバランスが非常に難しい。
チームの人もユーザーのためを思ってWebメディアを運営してるので、ビジネス施策をやると内部の意見とも相反することが多いので大変だった。
お金を稼ぐということは?ということを身に着けたのはこの時で、アライアンス案件などで契約にも多く関わったためビジネスの進め方のイロハを学んだ。
後は経営企画と予実管理をやっていて年度のPLとしての利益目標を意識した取り組みなども行えた。
いろいろ経験したが、ライン組織のリーダーは未経験だったため、企画チームのチームリーダーへ
金融Webメディアの企画チームリーダー
前述の通りプロダクトマネージャーやプロジェクトマネージャーはやっていたが組織マネージャーは初めての経験だった。
その時の出来事の中で特に印象に残っているのはは、チームに30歳中途で金融のスペシャリストだが、Web業界未経験の人が入り、その人のリーダーをするのは大変だった。
おそらくその人なりにはWeb業界のことを学ぼうとしていたのだけど、html,xmlって何?という状況だったので、かなりコミニュケーションに苦戦をした。
その人は金融のスペシャリストなのだから、未経験のWebに期待するよりも金融の知識を活かした案件に注力させたほうがよかった。
この時の教訓は勝手な期待値を設定して勝手に失望するのは止めるということ。
金融の胴元企業のビジネスを学びたかったため、カード会社へ
カード事業の与信スコアリング
全社的にデータ活用が熱くなってきた時代でカード事業にも機械学習を取り入れて与信精度を上げる取り組みを行った。
予測がビジネスモデルの根幹にあるような、機械学習が効くプロダクトは予測が0.1%向上することがビジネス的な価値を生むものに相性が良くて、ジャンル的には広告と金融は取り組みやすい。
機械学習は学生時代に嗜んでいたけど全て忘れていたため、思い出しながら取り組んだ。
政治的な事情でプロジェクトはペンディングになったけど、プロダクトに機械学習を適応してビジネス成果を出すための進め方を学んだ。
データ活用の波が本格的に進み、CDO室が作られることになり、CDOから立ち上げ担当として呼ばれたのでCDO室へ
カード事業のCDO室の立ち上げと全社へのデータ利活用推進
CDO室を立ち上げるにあたって何故か『CDO』がDMBOK2を買ってきて、「これを読んでデータマネジメントをする組織をビジョンとした組織を作ってくれ」とお題をもらった。
エンジニアとPdMの知識でDMBOKを読んで、完全に理解したと思い、CDO室のMVVを作って組織の立ち上げを測った。
CDO室の立ち位置として全社のデータ利活用を促進する部署としたので、横断組織の立ち上げや業務コンサルなども行った。
データ利活用のみならず全社のDXを掲げていたため、BPR、RPA、ノーコード、ローコードもとりくんだ。
なお、この後何回かDMBOKを読んで完全に理解したのは間違いと気が付き、それがDMBOK要約記事の執筆につながる。
データ基盤の課題を解決するためにデータエンジニアチームの立ち上げへ
カード事業のデータエンジニアチームリーダー
データ基盤のインターフェースがcsv出力しかなくて何するにもcsv出力してexcelで加工するという業務になっていたので、そこを改善すべくBigQueryを使ったデータ基盤に作り変えることにした。
親会社のほうでデータエンジニアをやっていた人に来てもらいデータ基盤を開発していった。ここでETL,ELTとかDWHとかデータレイクとかデータパイプラインについて一通り学んだ。
自分は似非スクラムマスターをやり、データ基盤のスクラム開発を行った。
エンタメ企業からデータマネージャー募集のお声がかかり、エンタメ企業でデータマネジメントをやることに。
エンタメ企業のグループ横断データマネジメント、データガバナンス
データ分析を進める中でデータマネジメントの必要性に気づきデータマネジメントに取り組んでいた人を探していたらしい。
入ってみるとジェネラリストのデータエンジニアが奮闘していたので、自分もジェネラリストっぷりを発揮してデータ基盤の整備を進めていった。
異動や出向は経験していたものの、初の転職で自分のスキルが通用するか不安だったが、意外と通用してなんなく馴染むことができた。
組織を拡大していくために、組織のビジョンを描いたりして、実現のためにチームリーダーへ
エンタメ企業のデータインフラチームリーダー
データインフラといいつつ、データエンジニアリングとデータマネジメントを行う部署を立ち上げてチームリーダーへ。
組織マネジメントとCDO室立ち上げの経験が生きた形で、組織も安定稼働している。今はまだ個人のスキルで組織運営している形なので採用含めて組織を安定化させるために奮闘している。
エンタメのドメイン知識を学びつつ、採用を中心とした組織の運営を学ぶことができている。
次のチャレンジはなんだろうか。
その他活動
主務とは関係なく取り組んできた活動を記載。
スマホアプリ開発
2011年ごろiPhoneの個人開発が注目されていた時でひねくれものの自分はAndroidアプリ開発をやってみたくてIS05を買い、Eclipseで開発した。
その頃はアイドルマスターにはまっていたので、「アイマスあんてな」というアプリを作ってアイマス声優さんのブログをRSS経由で更新チェックをしてアプリで閲覧できるもの。
デイリー100人くらい使ってくれていたが、サーバーの維持とアプリのバージョンアップ対応がめんどくさくなって5年くらい運営してクローズした。
ライフイズテック(Life is tech)の先生
1社目の会社がライフイズテック(Life is tech)という学生向けプログラミングスクールと組んで短期的なスクールをやるので、先生を募集していたので応募した。
学生時代に塾の先生とかやっていたくらい先生は好きなので、小学生、中学生にゲーム作りを教えて、楽しかった。
バックデイ
ハックデイという開発イベントに3回出た。
開発というよりアプリの企画に力を発揮した記憶がある。
半リアル恋愛シミュレーションゲーム
女性バージョンと男性バージョンのアプリがあり、某ときめきメモリアルのような恋愛シミュレーションを行う。
相手はアニメ絵とやり取りするのだけど、実は後側で人が操っていてゲームをクリアすると人通しがやりとりする2ndラウンドが始まるというものを作った。
ワンタイム電話番号アプリ
Twillioというサービスが開発イベントのために無料開放するという会だったのでTwillioを使ったサービスを考案。
ワンタイム電話番号というものはどうだろうという事で、1回電話がつながったらかけた人はもう発信できなくなるというものを作った。
浅草観光アプリ
この頃はオキュラスが発売されたため、オキュラス+360度カメラ+リープモーションを使って何かしようという事になった。
特にひねりはなく、浅草の仮想観光アプリを作った。例えば店に入るときにマークが出て触ると店に入れる。店に入ったら店モードに切り替わって店の買い物体験ができるような感じのものを作った。
ハックU
ハックUという大学向けの開発イベントの企画を8年くらいやっていた。
母校でHackUの中で最多開催くらいやったので、母校にもある程度貢献できたと思われる。
1回だけは司会もやったものがありyoutubeにもアーカイブされている。
競馬予測
仕事で機械学習をしていたので、競馬の予測ができるんじゃないかと思ってデータを集めて機械学習の環境を作った。
競馬で勝ち馬を当てるだけならば、オッズを見れば大体あたるのだけど、競馬はあたってもあまり意味なくて、配当が高いかつ勝率は高いものを予測しないと意味がない。
そこがなかなか難しくて、期待値100%を超えるようなモデルは作れずあまりいじらずに終わってしまった。
環境はまだあるので、また取り組みたい。
資格
仕事と関係しそうな資格をちょくちょく取るようにしている。
なぜかもろ業務に係る資格は取ってない。
・簿記3級
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・ITパスポート
・情報セキュリティマネジメント
・ビジネス実務法務3級
おわりに
自分の知識をまとめるためと今後誰かがデータマネジメントをやってみたいと思った時のきっかけとなるためにnoteを書くことにしました。
モチベーションのために役にたったという人はぜひ、フォロー&スキをお願いします。
ツイッター(@yoshimura_datam)でもデータマネジメントに係る情報をつぶやいてますので、よろしくお願いします。
データマネジメントを学ぶ人が抑えておきたい本
今すぐわかるデータマネジメントの進め方
著者のDMBOKを用いてCDO室を立ち上げデータマネジメントを推進した経験を基にデータマネジメントの進め方をまとめたkindle本を執筆しました。
データ組織立ち上げ編 AI事務員宮西さん
著者のデータ組織の立ち上げ経験をマンガ+コメントでまとめてみました。立ち上げ編は組織を立ち上げてやることが決まるまでのストーリーです。
無料公開のため0円となります。
データ組織の立ち上げに関係する方は是非読んでみてください。
DXを成功に導くデータマネジメント
DXを成し遂げるために必要なデータをどうマネジメントしていけばよいかが書かれている。
データ環境より、セキュリティの観点であったり、プライバシーの観点であったりといった非技術者向けの内容が多く書かれている。
データマネージメントに興味を持った人はまずは読んでみるとデータマネジメントでなすべき概要が理解できる。
実践的データ基盤への処方箋
データ利活用を行うために必要なデータ基盤の考え方と、利活用するためにはデータをどのようにマネジメントしていけば良いかを具体的な例を用いて説明されている。
技術が中心になるので現在データ技術に係る人がデータマネージメントに興味を持った時には、まず手に取ることをおすすめする。
個人データ戦略活用 ステップでわかる改正個人情報保護法実務ガイドブック
個人情報保護法を順守するための基本的な考え方が実務ベースで書かれている。2022年4月に施工される改正個人情報保護法で新たに追加される概念も同様に記載されている。
政府の出しているガイドラインよりも俯瞰的に読めるためデータプライバシーにかかわる人、データを使ったビジネスを推進する人は読んでおくとスムーズに業務が進められる。
データマネジメント知識体系ガイド(DMBOK)
自分も要約・解説記事を書いているDMBOK。データマネジメントに興味を持った人がまず手に取ると挫折することは間違いないほどのボリュームがある。
読めば読むほど味が出てくるので、データマネジメントを進めようとしている人は各家庭に1冊は是非買っておきたい。
データマネジメントが30分でわかる本
著者もDMBOKを読むためには非常にボリュームが多く読み解くには苦労するので、かみ砕いた解説書をまとめたと書いてある通り、DMBOKを独自解釈してわかりやすく書かれている。
DMBOKを技術者目線で読み解いた内容になっているので、実践的データ基盤への処方箋と同様データ技術に係る人におすすめする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
