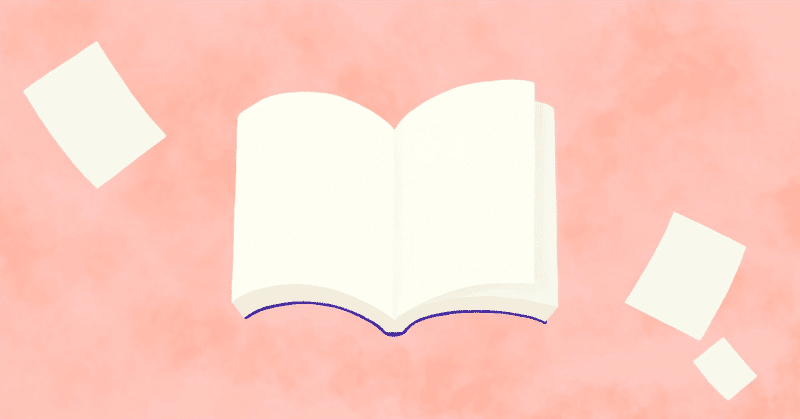
小説感想「山月記」│この気持ちは誰にも分からない…
はじめに
はじめまして!寿司田 四と申します。今回は初めてのnoteということで、練習がてら「山月記」の感想を書いていこうと思います。
実は今学校で「山月記」をやっていて、感想を書く課題があるんです。ついでに課題ができておトクなので「山月記」をテーマにしました。
誰もが知る名作ですが、できるだけ自分らしいユニークなnoteをかけるよう頑張ります!
(「山月記」を読んだことがない人は先に読むことをおススメします。中島敦 山月記 (aozora.gr.jp))
「山月記」とは
「山月記」は1942年に文學界という雑誌で発表された中島敦のデビュー作だそう。文學界なんだ。
短篇だけど難しい語彙がふんだんに使われていて少し読みづらい。たとえば叢とか。そもそも登場人物に袁傪っているし……。読めるかってんだ。
まあ中国が舞台みたいだからね。しょうがないか。
高校生の現代文でとりあげられるため知名度はとても高い。「その声は、我が友、李徴子ではないか?」という文はインターネットでもネタとして使われることがあります。
作者について
作者は中島敦。20世紀前半に活躍した小説家です。硬派な文体ながらも叙情的で、芸術性の高さが評価されているそうです。最近だと「文豪ストレイドッグス」の主人公としても有名なのかな。ある友達が文ストで知ったと言ってた。
「山月記」の感想
「山月記」はとても芸術性の高い作品で、難しいけれどとても満足できる作品でした。
特に好きだったシーンを紹介します。
名シーン①再会
残月の光をたよりに林中の草地を通って行った時、果して一匹の猛虎が叢の中から躍り出た。虎は、あわや袁傪に躍りかかるかと見えたが、忽ち身を飜して、元の叢に隠れた。叢の中から人間の声で「あぶないところだった」と繰返し呟くのが聞えた。その声に袁傪は聞き憶えがあった。驚懼の中にも、彼は咄嗟に思いあたって、叫んだ。「その声は、我が友、李徴子ではないか?」
(中略)
叢の中からは、暫く返辞が無かった。しのび泣きかと思われる微かすかな声が時々洩もれるばかりである。ややあって、低い声が答えた。「如何にも自分は隴西の李徴である」と。
李徴の最も親しい友人である袁傪が、虎になった李徴に気づく有名なシーンです。
李徴は自分が見下していた役人の下につくことになって自尊心を大きく傷つけ、狂気のあまり失踪していました。その知らせを聞いた袁傪はどう思ったのだろうか……。再開した時の感動は……。心が動かされてしまいます。
名シーン②李徴の長い独白
己の中の人間の心がすっかり消えて了えば、恐らく、その方が、己はしあわせになれるだろう。だのに、己の中の人間は、その事を、この上なく恐しく感じているのだ。ああ、全く、どんなに、恐しく、哀しく、切なく思っているだろう! 己が人間だった記憶のなくなることを。この気持は誰にも分らない。誰にも分らない。己と同じ身の上に成った者でなければ。
人間(虎?)には、苦しみを分かって欲しいという気持ちと、簡単に分かられてたまるかという気持ちが矛盾してあります。李徴は誰も自分の気持ちはわからない突き放すけれど、心のどこかで自分と共感し合える者がいないかと思っているようにも見えました。
名シーン③別れ
又、今別れてから、前方百歩の所にある、あの丘に上ったら、此方を振りかえって見て貰いたい。自分は今の姿をもう一度お目に掛けよう。勇に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、以て、再び此処を過ぎて自分に会おうとの気持を君に起させない為であると。
(中略)
一行が丘の上についた時、彼等は、言われた通りに振返って、先程の林間の草地を眺めた。忽ち、一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを彼等は見た。虎は、既に白く光を失った月を仰いで、二声三声咆哮したかと思うと、又、元の叢に躍り入って、再びその姿を見なかった。
月に照らされて天を衝くように咆哮する虎を想像すると、恐ろしいと思う。しかしその虎が1人で苦しみを抱える元人間・李徴であると考えると、とても残酷で可哀想に感じる……。
おわりに
拙い文章ですが、精一杯頑張りました!
お読みいただきありがとうございます。
良ければなんかコメント?とか?いいねとか?
そういう類のものをしていただけるとうれしいです。
追記:次回は
・東京都同情塔(九段理江)
・デミアン(ヘルマン・ヘッセ)
・劇場(又吉直樹)
あたりの感想を書きます。
これ「下書きに戻す」で良かったのかな……?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
