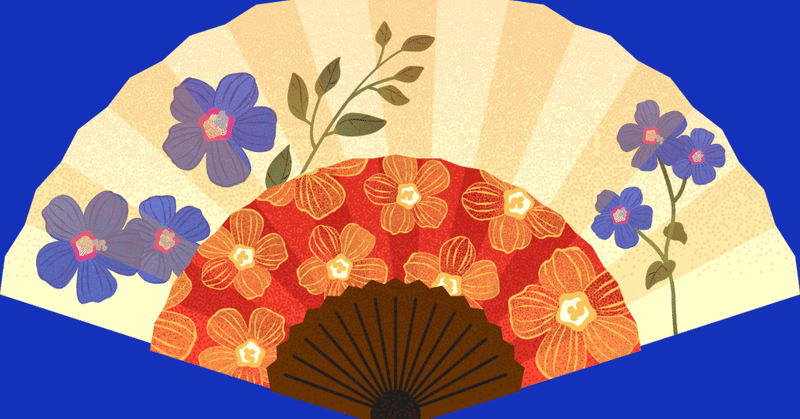
古典を勉強しておけば、私の夢研究も捗ったのかも
現実世界で夢の話ばかりしていると、「ちょっとおかしい人」とか「ヤバい人」のレッテルが貼られてしまう。
夢の意味を考えたり、面白がったりする行為は、あまりメジャーではないというか、大っぴらにするものではない、という空気を感じる。
私自身は、夢の世界に興味があって、夢の書き起こしや、SNSで他の人の夢日記を読むなど、一日何時間かを夢関係に費やしている。
そういう者からすると、夢が軽視されている現状を、憂うとまでは行かないが、「もうちょっと現実世界で夢の話が出来たらいいのにな」と思ったりする。
そんな折、国立公文書館で「夢みる光源氏―公文書館で平安文学ナナメ読み!―」という展覧会があるのを知った。
平安時代の和歌や文学と「夢」についての特別展で、当時の人々にとって夢がどのような存在であったかに迫る内容だったらしく、敬宮愛子内親王殿下が展示をご覧になったと報道されていた。
残念ながら、私がそのニュースを見た時点で、展示期間は終わっていた。行きたかった~・・・・。
うらめしくネット記事を漁るしかなかったが、その中に愛子さまが「夢を通して平安貴族の心のあり方に触れることができました」と感想をおっしゃっていた、という一文があった。
不敬ながら「そう!正にそれ!」と思った。
私が夢の世界に興味を抱いているのは、夢が心の在り方を映し出すからだ。
夢について書いたり話したりすることで、他者の心を覗き見たり、他者が自分の心に触れたりという、面白いことが出来るからだ。
また、その時代の人たちが夢について書き残しているからこそ、約1000年前の平安貴族の心情を現代の私たちが推し量るなんていう、ちょっとスペクタクルなことが可能になっているわけで、やっぱり夢に興味を持ったり、執筆に労力を割いたりすることは、決して無駄ではないと感じた。
まあ私は平安貴族じゃなくて令和の一般庶民であるから、そんな者が夢について書き残したところで・・・・という気もするが、それでも自分が自分を知る手助けにはなるから、やっぱり夢には興味を持ち続けるべきだろうと思う。
更に、この展覧会についての関連記事には、こんなことが書かれていた。
平安時代、夢は日々の吉兆を占うメッセージと捉えられており、病気快癒の処方から田畑の作付けの時期まで、何らかの判断を夢で見た内容によって選択していたという。
当時は今よりもずっと夢が身近なものであり、「こんな夢を見たので、きっといいことがある」「怖い夢だったけれど、人に相談したら逆夢だといわれホッとした」など常に人々の間で話され、関心事であった。
夢の世界が身近だった様子が窺える。
現代なら「夢の話ばかりする酔狂なヤツ」と見なされかねない私も、平安時代なら馴染めてたのか?
なお私は、中学時代は不登校で、高校以降も全然勉強してこなかったので、恥ずかしながら古典・古文が全く分からない。
本当に、すゑひろがりずのネタとか、小学生の頃に読んだ『源氏物語』の学習マンガの知識しかない。「あり・をり・はべり・・・」というのも最近知ったくらいだ。
今更ながら、『源氏物語』で描かれる夢の描写について知りたい。『枕草子』にも夢への言及があるというから、当該部分を読んでみたい。
せめて『万葉集』とか『古今和歌集』をちゃんと知っていれば、と悔しく思う。百人一首もうっすらとしか知らない。
私は夢に興味を持っていると言うくせに、夢を題材とすることが多い和歌を知らないというのは、なんていうか、本当に情けない。
だけど、私が抱いている「夢についてもっと語りたい」という欲求は、もしかすると、古典文学にぶつけるべきなのかも?という発見が今回あったから、まずは中学校で習うようなことから調べてみようか、なんて思ったりしている。
遅きに失した感はあるが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
