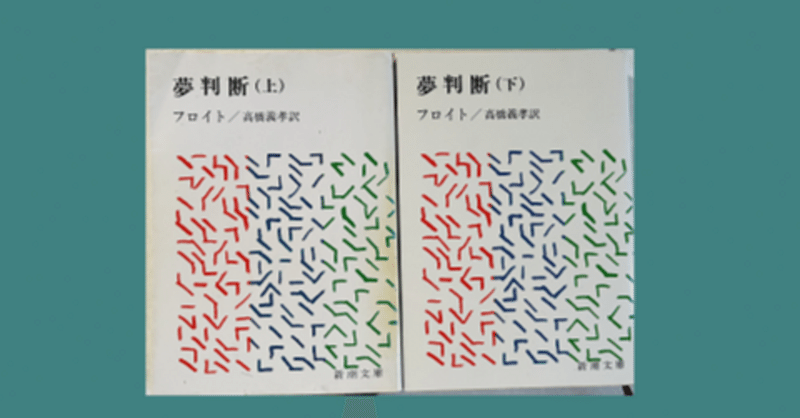
【全9冊】幾多の断捨離と引越しをかいくぐってきた本を紹介する
これまで引越しの度に、「服・雑貨・本」の多さに泣かされてきた。
その反省から、自分の持ち物は極力、身軽にするよう心がけている。
たとえば、
服→(夏物、冬物それぞれ)小さい3段ケース+ハンガー10本に収まる量
雑貨→大きめの四角いクッキー缶ひとつに収まる量
本→バスケット(30cm×25cm、高さ15cm)に入るだけ
と、なんとなく決めている。
特に、私は書店やブックオフに行くことが半ば趣味になっているから、本を増やさないようにするのは結構大変だ。
極力図書館で借りる、買ったら売る、寄付するなどして、所持する冊数を減らすようにしている。
家族共用の辞書や地図帳、便覧系を除くと、私個人の所有している本は現在9冊である。
それぞれの本を、幾多の断捨離を掻い潜ってきた理由とともに紹介してみる。
1.『1週間で8割捨てる技術』筆子(KADOKAWA)
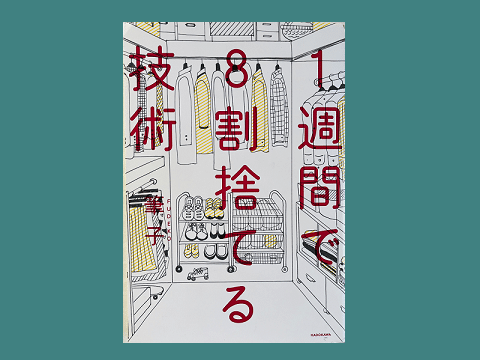
以前の記事でも紹介した筆子さんの本。
家にモノが増えてきたなと思ったら読み返して、手順通りに断捨離している。
年に何度も活用するため、手元に置いておきたいと思い、購入。
2.『フランス人は10着しか服を持たない~パリで学んだ“暮らしの質"を高める秘訣~』ジェニファー・L・スコット(大和書房)

こちらも「モノを減らす系」の本ではあるが、実用的なテクニックというよりは、心豊かに生きるためのヒントをもらうために読む。
これを読むと、ジャンクなお菓子をバリボリ食べたり、生地ペラペラ縫製ガタガタのプチプラ服を買ったりする気が失せる。
もっと、心から気に入ったものと楽しく暮らそうという気持ちになれるし、流行に左右されないおしゃれの心構えもたくさん載っているので、これからも何度も開くことになるであろう一冊。
3.『思考の整理学』外山滋比古(ちくま文庫)
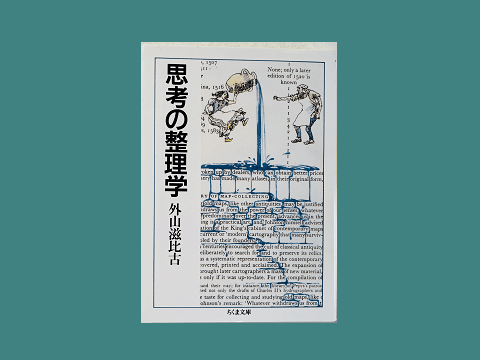
「東大・京大で1番読まれた本」のキャッチフレーズに惹かれて購入。
ブログやnoteを始めて、日常的に文章を書くことが増えてからは、この本に書かれていたことがよく思い出された。
「アイディアを寝かせる」ことや、時に「切り捨てる」ことが、思考を深める上で思いがけない効果を発揮する。
たまにパラパラと読んで、「気楽に、流れに任せて書こう」というマインドを呼び起こしている。
4.『夢判断(上)』
5.『夢判断(下)』 フロイト(新潮文庫)

これははっきり言って、挫折した本。
「夢の研究を趣味としている」と標榜している以上、フロイトとユングくらいは読んでおかねばなるまいと、古本屋で張り切って購入したものの、めんどくさい言い回しにうんざりして、上巻を読んだところでやめてしまった。
気が向いたら再チャレンジしようと思い、手元に置いてある。
6.フロイト『夢判断』 2024年4月 (NHKテキスト)
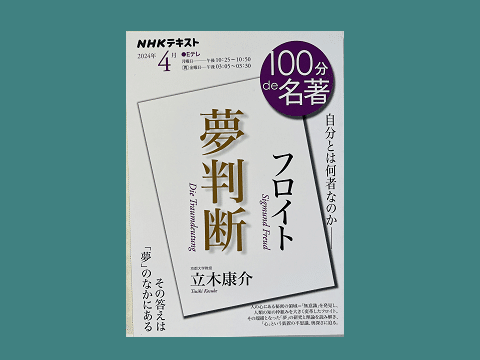
↑の流れで。NHK『100分de名著』の解説テキスト。
録画した番組と合わせて読むつもり。
7.『新版 貧困旅行記』つげ義春(新潮文庫)
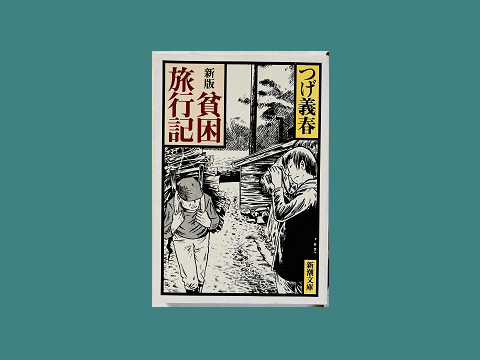
『つげ義春とぼく』と一緒に所持していたが、そちらには「家族に見られたら困るシーン」がちらほらあったので、ギリ見られてもOKなこの本だけが残った。
8.『パプリカ』筒井康隆(新潮文庫)
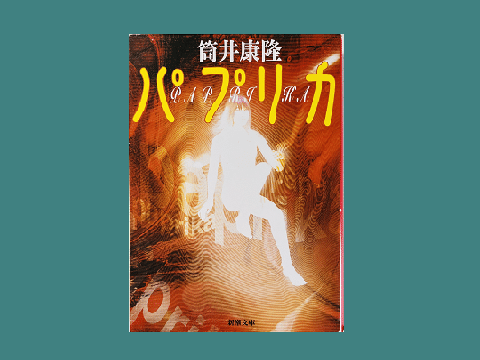
唯一の小説。持っている理由はもちろん、「夢がテーマになっているから」だ。
少し「失敗したな」と思うのが、映画版を先に観てしまったこと。イメージが鮮烈過ぎた。
まず文字だけで味わうべきだったな。でも、本も映画も大好き。
9.『ゼロ年代お笑いクロニクル おもしろさの価値、その後。』手条萌
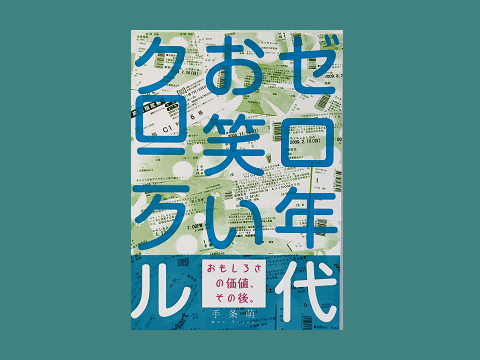
これはイベントで購入した同人誌。
まさにこの時代にお笑いに夢中になっていたので、「そうそう!」と膝を打ちながら読んだ評論本。
お笑い史年表がよくまとまっていて便利なので、ちょくちょく参照している。
以上が私の手持ち本である。
これ以外に、小説版『ムーミン』、さくらももこや水木しげるのエッセイ、歴史や神話の本などもあるが、それらは子と共有しているため、子ども部屋の本棚に置かせてもらっている。(これちょっとズルいかもしれないな。)
今後もおそらく、引越しの機会は何度もあると思う。
それでも、少なくとも自分の趣味で手元に置いている本に関しては、バスケットをはみ出す量は持たないつもりだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
