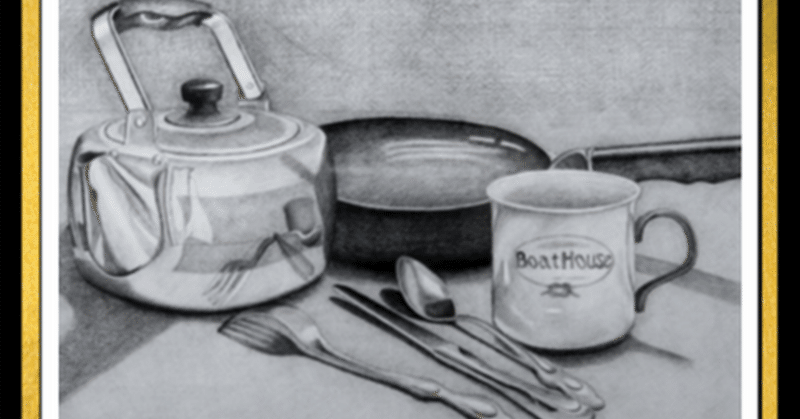
デッサン・鉛筆画入門者から上級者まで必見!選び方で変わるスケッチブックと紙の世界
どうも。鉛筆画家の中山眞治です。毎年のことですが、桜に雨や風はつきものですね。一気に花びらが散り始めてさびしい想いもしますが、元気でお過ごしですか?^^
さて、デッサンや鉛筆画の魅力を引き出す上で、スケッチブックや紙の選び方は欠かせません。
この記事では、質感から耐久性、さらにはサイズ選びまで、鉛筆によるデッサンや鉛筆画作品の表現力と寿命を最大限に伸ばす秘訣を紹介します。
プロが推奨するスケッチブックのブランドから、コストパフォーマンスに優れた選択肢まで、あなたのアートを次のレベルへと導く情報が満載です。
それでは、早速見ていきましょう!
1 鉛筆デッサン・鉛筆画入門者必見!なぜ紙とスケッチブック選びがアートの質を左右するのか?

鉛筆デッサンや鉛筆画は、単に技法や技術だけでなく、使う画材の選択によってもその質が大きく左右されます。特にスケッチブックや紙の選び方は、描き手の意図を正確に描写するための基盤となる要素です。
それでは、スケッチブックや紙の選び方が鉛筆デッサンや鉛筆画において、どれほど重要なのか、その理由と共に詳しく探っていきましょう。
(1) アート作品を格上げ!紙の質感が生み出す表現力の秘密
スケッチブックや紙の表面の質感は、鉛筆の筆圧や種類によって異なる描写を生み出します。
例えば、滑らかなスケッチブックや紙は、モチーフの細密な部分を描きやすい一方で、ざらざらとしたスケッチブックや紙は、筆圧による濃淡の描写が魅力的です。
そして、適切なスケッチブックや紙の質感を選ぶことで、意図した表現を効果的に伝えることが可能になります。
(2) 耐久性と厚みで変わる!スケッチブックが作品寿命を伸ばす理由
スケッチブックや紙の厚みは、作品の寿命や保存性に直結します。薄いスケッチブックや紙は破れやすく、強い筆圧での描写には向きません。
一方、厚めのスケッチブックや紙は頑丈で、何度も修整を加えたりトーンを乗せる際にも適しています。また、長期間の保存を考えた場合、耐久性の高いスケッチブックや紙の選択は必要不可欠です。
(3) 創作の自由度を広げる!スケッチブックのサイズと形状の選び方
スケッチブックや紙のサイズや型は、作品の大きさや構図の選択に影響を与えます。そして、小さなスケッチブックは持ち運びに便利で、外でのスケッチに適しています。
また、大きなスケッチブックや紙は、細部まで丁寧に描写するのに適している一方で、展示や表現を強調する際にも迫力が加わり有利です。
総じて、スケッチブックや紙の選び方は、作品の完成度やその後の発表時などでの展開を大きく左右します。
鉛筆デッサンや鉛筆画を追求する上で、適切なスケッチブックや紙の選択は欠かせないステップと言えるでしょう。
2 スケッチブック完全ガイド:選び方から特徴まで徹底解説

アーティストやデザイナー、趣味のスケッチ愛好者にとって、スケッチブックはアイデアや感じたことを瞬時に捉えるための重要なツールです。
しかし、多種多様なスケッチブックが市場には出回っているため、適切なものを選ぶことは簡単ではありません。ここでは、主要なスケッチブックの種類とそれぞれの特徴について解説します。
(1) ハードカバー型スケッチブック
堅固な表紙を持つハードカバー型は、持ち運ぶ際のページの保護や、長期間の保存に向いています。しっかりとした表紙は、外部のダメージから中身の画面を守り、スケッチの品質を長く維持できます。
(2) リングバインダー型スケッチブック
ページを自由に追加・取り外し可能なリングバインダー型は、カスタマイズの自由度が高いのが特徴です。アイデアの整理や、特定のテーマごとに分ける際に、このタイプは非常に便利に使えます。
(3) アコーディオン型スケッチブック
連続した景色やストーリーを描く際に便利なのはアコーディオン型です。ページを広げることで、一連のイラストやスケッチを一つの流れとして表示することができます。
(4) 水彩用スケッチブック
水彩画などの、液体の素材を使用する場合に最適なのが、水彩用スケッチブックです。厚くて吸水性の高い紙質は、色のにじみやページの歪みを防ぎます。
(5) ポケットサイズスケッチブック
持ち運びやすさを重視する人には、ポケットサイズがおすすめです。手軽にどこでもスケッチが楽しめるので、旅行や日常の中での瞬間描写に最適です。
スケッチブックの選び方は、使用する場面や目的に応じて変わります。それぞれの特徴を理解し、自身のニーズに合わせた最適なものを選ぶことで、スケッチの楽しさや効果をさらに向上させることができます。
3 デッサン紙の選び方:質感と厚さがもたらす描き心地の差

鉛筆画やデッサンにおいて、筆圧や技法だけでなく、用紙の質感や厚さが描き心地や作品の出来映えに大きく影響します。
用紙の選択はアーティストにとって重要な決断の一つです。ここでは、デッサン用紙の質感と厚さの違い、そして、それがどのように描き心地に影響するのかを詳しく探っていきます。
(1) デッサン紙の質感を理解する:アートに深みを加える選択
a 滑らかな質感 (Smooth)
モチーフの細密描写を重視する、繊細な作品や細かい陰影技法に適しています。細やかな表現が可能で、鉛筆やチャコール(木炭)で細部までをしっかりと捉えられます。
b 中程度の質感 (Medium)
多くのアーティストに好まれるこの質感は、多様な技法や材料に対応可能です。バランスの良い描き心地が特徴です。
c ざらざらした質感 (Rough)
筆圧の変化や、立体的な陰影画法を楽しむのに最適。特にチャコール(木炭)やソフト鉛筆(B系の濃い鉛筆)と相性が良く、深みのある表現が可能です。
(2) 紙の厚さが作品に及ぼす影響:知っておきたいポイント
a 薄い用紙 (Lightweight)
軽くて扱いやすいですが、繰り返しの修整や強い筆圧には向きません。速写(クロッキー)や一時的なスケッチに適しています。
b 中程度の厚さ (Medium weight)
最も一般的で、多目的に使用可能で、破れにくく、多少の修整も容易です。
c 厚い用紙 (Heavyweight)
強い筆圧や、水彩、混合の液体画材(メディア)にも対応できます。破れにくく、長期保存にも向いています。
d 最適なデッサン用紙の選び方
用紙の質感や厚さは、描くテーマや使用する道具、さらにはアーティストの好みによって選び分ける必要があります。
適切な用紙を選ぶことで、作品の質を向上させ、描く過程そのものをより楽しむことができるのです。自身のスタイルやニーズに合わせて、最適なデッサン用紙を見つけ出しましょう。
参考:世界堂オンラインショップ
画材・額縁・文房具通販の世界堂オンラインショップ (sekaido.co.jp)
4 プロ推奨!高品質なスケッチブックブランド6選

アーティストの間で評価されているスケッチブックや紙のブランドは数多く存在しますが、その中でも特に評価が高い、プロからのおすすめブランドをピックアップしました。
以下、その特徴とともに6つのブランドをご紹介します。
(1) モレスキン (Moleskine)
イタリア発のこのブランドは、優雅なデザインと耐久性で知られています。ポケットサイズから大きめのサイズまで幅広く展開しており、旅行先でのスケッチや日常のメモ取りにも最適。
(2) ストラスモア (Strathmore)
アメリカの老舗ブランドで、質の高いデッサン用紙や水彩紙で知られています。多様な技法に適応した紙のラインナップが魅力で、特に中級者からプロのアーティストに支持されています。
(3) クレッシー (Canson)
フランスの歴史あるブランドで、上質な水彩紙やスケッチペーパーが人気です。特に色の乗りや筆の滑りが良く、鉛筆画や水彩画に使用するアーティストからの評価が高いです。
(4) ファーバーカステル (Faber-Castell)
主に、鉛筆などの筆記具で知られるドイツのブランドですが、スケッチブックも展開しています。耐久性と描き心地の良さを兼ね備えており、デザイナーやアーティストにおすすめです。
(5) レムタ (Rhodia)
フランス生まれのこのブランドは、滑らかな紙の質感とシンプルなデザインで知られています。インクや鉛筆との相性が良く、きれいなラインが引けるのが特徴です。
(6) 大雑把な価格比較

プロがおすすめする、スケッチブックのブランドに関する価格比較一覧表は大雑把に上記の通りです。価格は平均的なものを示し、実際の店舗やサイトにより多少の変動が生じる可能性があります。
※ 各メーカー商品をネットで探す場合には、上記一覧表のブランド名の( )の中の名称で探してください。例えば、クレッシーのスケッチブックを探す場合には、Cansonで探すということです。
(7) ホワイトワトソン (メーカー名:ミューズ 東京都所在)
スケッチブック選びはアーティストにとっての重要な一歩です。
歴史を振り返れば、1960年のデビューから多くのアーティストに愛されてきた「ワトソン」。その信頼性を受け継ぐ形で誕生したのが「ホワイトワトソン」です。
その美しい白色は、夏から冬にかけてのシーズン毎の明度差を活かした奥深い表現が可能です。
特に白色度添加剤を使用せず、自然水のみでの製法は、純粋な白色を追求するアーティストには特におすすめです。
さらに、このスケッチブックの真骨頂は紙の質感にあり、ほどよくザラついた中目の紙肌は、鉛筆及びチャコール(木炭)やパステルの乗りと相性が抜群です。
因みに価格は、大雑把に上記の価格一覧表の中の$一つ表示と同程度で、低価格帯です。筆者も最近は、このスケッチブックを使用しています。
尚、紙が白いことは、画面上のハイライトを利かせる部分に、そっくりその際立つ白さを輝く部位に充てることができるという利点もあります。

5 コストパフォーマンス抜群!プロが選ぶスケッチブックブランド5選

安価なスケッチブックも、多くのアーティストや学生にとって大変重要です。以下は、コスパが良く、初心者から上級者まで幅広く活用されているスケッチブックを5点紹介します。
(1) ストラスモア スケッチブック
特徴
ストラスモアは、100年以上の歴史を持つ信頼されているブランドです。
スケッチブックは、酸性フリーで中程度の紙の厚さを持ち、鉛筆、チャコール(木炭)、スケッチ用インクなど、さまざまな画材に対応しています。
価格
中価格帯ながら高品質。
(2) Canson XL シリーズ
特徴
CansonのXLシリーズは、価格が手頃で大量のページであることが特徴です。
特に学生や初心者におすすめです。酸性フリーで、複数の異なる表面(サーフェス…スムース、ミディアム、ルーフ)が選べるのも魅力となっています。
価格
低価格帯。
(3) Pentalic スケッチブック
特徴
ポケットサイズのバリエーションが多く、外出時のスケッチに便利。酸性フリーの紙を使用しており、ページ数も多いので長期間の使用に適しています。
価格
低〜中価格帯。
(4) Moleskine クラシックスケッチブック
特徴
Moleskineは世界的に知られたブランドで、そのクラシックなデザインと堅牢性で人気です。
190g/m²の紙は、鉛筆やペンだけでなく、水彩にも対応しています。バンドで締められるデザインが、紙をきれいに保持してくれます。
価格
低〜中価格帯。
(5) Art Alternatives スケッチブック
特徴
高品質ながら、手頃な価格帯のスケッチブック。ブライトホワイトの酸性フリーの紙が、鉛筆、チャコール(木炭)、インクに適しています。
また、多様なサイズの選択肢があるので、携帯に便利なサイズから大型のサイズまで選択可能です。
価格
低価格帯。

6 スケッチブックの大きさで変わる!あなたのアートスタイルに合った選び方
上記のスケッチブックは、コストパフォーマンスが良く、初心者から上級者までのアーティストにおすすめできる品質を持っています。
特定の予算や使用目的に応じて、最適なものを選んでください。おすすめは、Canson XL シリーズです。
お求めの際には、F4~F10のサイズで探してください。Fサイズとは正方形に近い長方形のことで、筆者もこのFサイズのスケッチブックを使っています。あなたが最初に取り組む場合には、F6程度がおすすめです。
しかし、あなたの進む方向性が、各種展覧会や公募展などへの展開を考えるのであれば、やがてF30~F130くらいまで大きな画面にする必要もあります。
そこで、徐々に大きくすることに慣れるためにも、F10くらいから始めてみるのも良いでしょう。また、それ以外の形や大きさについては、次の一覧表を参照してください。
現在の全国公募展を見た場合に、一番大きい部類に入るのはF130号であり、小さいものではF30号及びそれ以下のサイズでも出品できる公募展もあります。
最初は、あなたのお住いの都道府県・市区町などで行われている展覧会への入選を目指されてはいかがでしょうか。具体的には、市の展覧会⇒県の展覧会⇒全国公募展⇒個展の開催で展開といった具合です。

7 疲れ知らずで描き続ける!デッサンの正しい姿勢とツールの活用法

鉛筆デッサンや鉛筆画は、繊細な技法と持続力が求められるアートの一つです。長時間にわたる作業での疲れを最小限にするためには、正しい姿勢及びツールの使い方や保管方法が不可欠です。
以下では、プロのアーティストも実践する制作時の姿勢や、効果的なツールの取り扱い方法と、それらを長持ちさせるための保管のポイントを解説します。
(1) 描画の角度
スケッチブックや画板は、デスクやテーブルの上に水平に置くのではなくて、手前に少し傾けることで目と紙の距離が近くなり、疲れにくい姿勢を保てます。
尚、取り組みの最初は絵画教室へ行きましょう。そこには、イーゼルや各種モチーフがあるので、取り組みの最初にはちょうど良いのです。
自宅で最初に取り組む際では、机の上に「手ごろな段ボール箱」を置いて、立てかけて制作するのでも良いです。
(2) 制作時の姿勢と鉛筆の持ち方
制作時の姿勢は、足を組まずにイスに深く腰掛けましょう。この姿勢が、長時間描いてもあまり疲れないための大きな秘訣です。
そして、鉛筆の持ち方は、描き心地や筆圧に大きく影響します。描画に取りかかる最初の持ち方は、全体を大きく捉えて、モチーフ全体の輪郭を描き込んでいきます。
その際には、親指・人差し指・中指で優しくつまむように持ち、腕と肩を使って、大きな動作で描き込んでいきましょう。その中に、「これだ」と思える輪郭線が見つかるはずです。
次の段階では、全体の輪郭線の中で、あなたが確信を持てた線以外は、「練り消しゴム」で整理しましょう。
そして、徐々に細部へ描き進める段階での鉛筆の持ち方は、文字を書くときのような持ち方にすることで、均等な筆圧を保ちやすくなります。
また、場合によっては、筆圧を高めたり、描線の種類を変えるために、鉛筆の先端近くをもって、鉛筆を寝かせて線を引くこともあります。
(3) 鉛筆を削る

鉛筆は定期的に削り、常に適切な太さと鋭さを維持します。
尚、鉛筆が短くなった場合には、鉛筆削りでは削れなくなりますので、鉛筆ホルダーを使って、ナイフやカッターなどで削れば、2cmくらいの長さまで使えます。 詳しくは、次の関連記事も参照してください。
関連記事:初心者必見!鉛筆画・デッサンで最適な鉛筆の選び方とその特性ガイド
https://pencil-drawing.com/3327.html
(4) 消しゴムと画面上の掃除
練り消しゴムを使う場合には、消しゴムの「消しカス」は出ません。
しかし、プラスチック消しゴムなどを使う際には、「消しカス」は画面に残ったままにせず、「羽根ぼうき」や「ティッシュ」を使用して、そっと表面を撫でて定期的に払い落とします。
適切なツールの使い方と保管方法を実践することで、ツールの持ち味を最大限に活かすことができます。これにより、より高品質な作品を生み出すことができるでしょう。
尚、練り消しゴムの知っておくべき重要な使用方法については、次の記事を参照してください。
関連記事:鉛筆画・デッサンにおける「練り消しゴムの秘密」:プロが教える光の描き方とは?
(5) 休憩の取り方
1時間に一度、5分間程度の休憩を取り入れることで、手や目の疲れを解消できます。尚、自宅での制作では、制作につかれるたびに、家事をこなせば一石二鳥です。
尚、鉛筆画の場合には、作業全体が細かいので、肩や首と目が疲れますが、回転させるなどの軽いストレッチが効果的です。
筆者の場合には、取り組みを始めた当初には肩も首もこりましたが、慣れてしまいました。目が疲れた場合には、やはり「目薬」が効きます。
(6) スケッチブックの保管
湿度や直射日光は紙の劣化を招きます。スケッチブックは乾燥した場所に、平らに保管することで紙の品質を維持できます。
尚、あなたが愛煙家の場合には、作品の表面が直接空気に触れるような状態にしておくと、気づかぬうちに「ヤニ」が付着してしまうので、注意が必要です。
この件では、やがてあなたが展覧会などを意識して、大きな作品を製作するようになった場合には、「パネルに水張り」して出品するようになるはずです。
しかし、展覧会から作品が戻ってきたとして、ガラスやアクリルのカバーがかかっていたとしても、タバコの煙はカバーの隙間から入り込んでいきます。
タバコを吸わない部屋で保管していたとしても、やがては必ず影響を受けてしまいます。
そのような場合には、タバコの煙が絶対に入って来ない別の場所で保管するか、作品を額ごと「ラップ」をかけるなどの工夫も必要です。
これは、他の技法の制作でも全く同じことが言えます。尚、ホームセンターでは、幅広の梱包用ラップを販売していますので、包装も検討しておきましょう。
8 プロへの第一歩!デッサンと鉛筆画の基礎から学ぶ道筋

あなたが、鉛筆画・デッサンに取り組む最初は「絵画教室」で学ぶことが、一番取り組みやすいと思われますが、その知識の吸収には、半年もあれば充分です。それ以上は教室に通うべきではありません。
それは、絵画教室の講師が、実績のあるすばらしい作品を描いていることをあなたが知っているのであればともかく、「大した実績もなく、素晴らしい絵を描く人でもない」場合には、習うことも少ないはずです。
まして、鉛筆デッサンや鉛筆画による、全国公募展での複数の入賞や入選などの、大きな実績を持っている人は、そう多くはないからです。
しかし、あなたが絵画制作の初期の頃であれば、描き始めの鉛筆デッサン程度は教えてもらえるでしょう。
尚、絵画教室へ通って、講師をあまり頼り過ぎて、常に「手を加えてもらう」ことが多くなってしまうと、モチーフを変えるたびに講師を頼ってしまい、あなたは独立して自由な制作ができなくなってしまいます。
それが、絵画教室をやめられない主な要因です。基礎さえ教えてもらえれば、あとはあなた自身が「構図の本」を1冊購入して独学で学習して、市や県及び公募展や個展を目指して展開していきましょう。
関連記事:初心者からプロへ!鉛筆画・デッサンで画家になるステップバイステップガイド
https://pencil-drawing.com/1.html
9 まとめ

鉛筆デッサンと鉛筆画の世界では、スケッチブックや紙はただの制作画面ではありません。それはアーティストの意図と感情を伝え、作品に命を吹き込む重要な役割を果たします。
質感から耐久性、サイズまで細部にわたる選択が、最終的な制作活動の質と持続性に大きな影響を与えるのです。この理由から、適切なスケッチブックと紙の選択は、アーティストにとって基本中の基本と言えます。
アート作品の寿命を延ばし、表現の自由度を広げるためには、用紙の厚みや質感がどのように作品に影響を及ぼすかを理解することが不可欠です。
例えば、厚手の紙はより多くの修正を許容し、深みのある質感は表現の幅を広げます。
また、スケッチブックのサイズや型は、アーティストが場面に応じて最適な選択をすることを可能にし、描く喜びをさらに向上させてくれます。
プロのアーティストが推奨するスケッチブックブランドを選ぶことも、質の高い作品作りには欠かせません。彼らの経験に基づく選択は、初心者や上級者を問わず、すべてのアーティストにとって価値ある指針となります。
さらに、コストパフォーマンスの良いブランドを知ることは、経済的な制約の中でも質を犠牲にせずに済むことに役立ちます。
正しい姿勢とツールの使い方は、長時間のデッサン作業でも疲れにくくするために重要です。また、適切な保管方法は、作品を長持ちさせるための鍵です。
これらすべての要素を総合することで、アーティストは自身の技術を磨き、プロへの道を歩み始めることができます。
鉛筆デッサンや鉛筆画におけるこれらの要素の重要性を理解し、適切な材料選びから姿勢、保管方法までをマスターすることは、アーティストとしての成長に不可欠です。
ではまた!あなたの未来を応援しています。
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!^^
