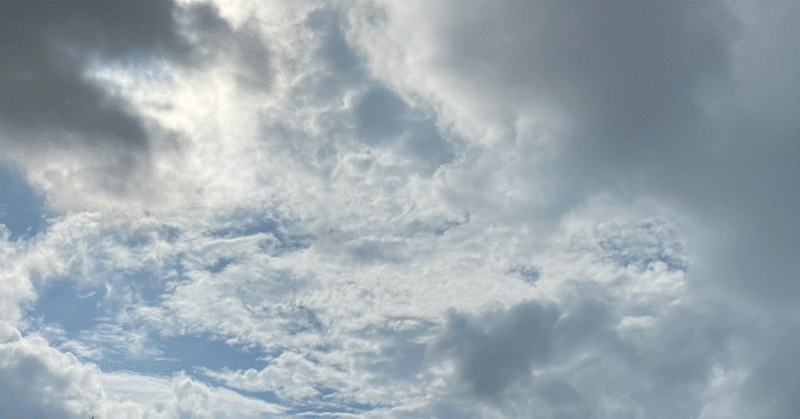
「栗の樹」はどこにある 今村樹二亜 ~小林秀雄『栗の樹』を読んで~
こんにちは! 広報の二ツ池七葉です。今回は我々が出版している雑誌『ダフネ』の執筆者を知ってもらう取り組みの一環として、小林秀雄の『栗の樹』というエッセイを読んで考えたことを各々に自由記述してもらうことにしました。
『栗の樹』は、数にして言えば2ページ程度の短いエッセイです。小林は文学を仕事にすることの大変さを軽く嘆いた後で、妻の話を本作の中で一つ紹介しています。簡単に要約すると、島崎藤村の『家』を読んで生誕の地を懐かしく思った妻が、故郷の信州まで馴染みの『栗の樹』を見に行くという、ホッコリエピソードです。小林はエッセイの最後を、このように締めくくっています。
「さて、私の栗の樹は何処にあるのか。」
以下、各々による本文になります。今回は、今村樹二亜が記述します。是非、一読ください。
「栗の樹ネ、そんなものどこにあるのか、僕も知りたいね」
そう言いながら読者に向かってサインをする小林秀雄は、なかなか憎いところがある。実際、「栗の樹」は存在しなかったという担当編集者の証言がある。(『小林秀雄の思ひ出』郡司勝義)大学の図書館でその記述を読み、僕は今呆然としている。図書館に人は少なく、窓の外の入道雲が夏の日差しを反射して眩しい。真っ白な光が、静寂な図書館にキンと広がっている。
僕たちは、彼の言葉のひとつひとつを信じて疑わなかった。最初は疑ってかかった彼の言葉に、気づいたら飲み込まれていた。いや、疑ってかかったのかは怪しい。ただ、彼の言葉がわからなかったから、理解しようと努めただけだ。どうにかして彼の見ている世界を同じように見たいと必死に読んでいっただけかもしれないが、そんな過程の中で気づいたら僕は、彼の言葉に、ある深淵なる真理を見出していた。その真理を説明してくれ、と問われれば僕は何も答えられないことに、今更ながら気づく。結局、真理を勝手に見出していたのは僕の目であった。小林秀雄を知らない者の目には、栗の樹は見えない。小林秀雄の目にも、栗の樹は無かった。
「ある」のか、「ない」のか。そんな問題は、どうだっていいことだ。僕は「ある」と信じていた。それが「なかった」だけの話だ。不動の存在は、とどのつまり、自分の信仰によって形づけられる。現世は確かに諸行無常である。その中で不確かなものを見つけるとしたら、抽象的な形而上学の世界にしかないのだろうか。形而上学を確かなものにする信仰の力を、僕は今失ったのだ。不動の存在が存在しなかったとわかり、その信仰が崩れただけだ。あとはどうなるか。何も残らない。ただそれだけのことである。かっこつけているわけではなく、厭世的な気分に浸っているわけではなく、ただそれだけのことだったのだと、今はゆっくりと思う。
ぼーっとしながら考える。
文学は虚構か?——大いなる嘘つきかもしれない。
言葉の魔術ではないか?——虚構の狭間に、真実があるんだろう。
なぜ文学を愛しているのか?——嘘を愛すのも、人間じゃないか。
情熱と孤独が、人間が作り出した文化の本質的土壌であるならば、僕たちはまさに、この存在するかどうかわからない栗の樹の根によって、自らの精神的土壌を耕していたのかもしれない。さて、この土壌から何か育つだろうか。芽を出し、花を咲かせ、いつか実を落とすだろうか?
夢とは雲のようなものだ。言葉によって作られた抽象の階段を登りきって、きっと雲に触れることはできるだろう。だが、雲を掴んだ人間は、かつて1人だって存在しなかったのだ。
なるほど、雲を掴むような話か。眺めているだけで美しいのか。僕たちは、その雲を作りだそうと思ったのではないのか。
時々、氏は強い言葉を用いる。それを聞いたある者は、強い言葉に揺るがされないように固く身構える。
またある者は、感化される。自らの両肩に乗っていた重い鎧を、吹き飛ばしてくれるからである。文学がたとえ虚構であったとしても、非常に無機質でモノクロな現実に、活力と彩りを与えてくれた経験があるわけだから、僕は文学を信用していた。「批評家は冷静さを必要とする。しかし感動しまいと努める必要はどこにある」とは、氏の文である。
夏の空は変化に激しく、入道雲はどこかに消えていった。灰色の怪しげな雲がちらほら見えてきて、どうやら雨が近い。僕たちは、夢や希望や絶対といった強い言葉を使う者を訝っている。ある程度の、知識や世間体といった冷静さと理性をもってして、強い言葉からの襲撃を守っている。しかし、誰も自分自身で作りだした強い言葉を、自分で防ぐ術を知っている者はいない。さて、小林秀雄は自分の創り出した強い言葉に騙されていたのではないだろうか。
ベルクソンの言葉を思い出す。「哲学者は真理が目の前にあるのに、真理に靄をかけて見えない見えないと騒ぎ出す。」まさにうってつけの表現だが、小林秀雄もこの言葉に感心しただろうか。それとも読み流しただろうか。僕には想像がつかない。氏はモーツァルトの音楽から、疾走する悲しみを聴き取った。その時にははっきりと、モーツァルトの悲哀の影がうっすらと見える表情を見切っていただろう。今の僕には、小林秀雄がどんな顔をしているのか、ちょっと見えないのである。それが腹立たしくもある。それでいながら、見えないのが当たり前だろうと割り切っている思いもある。堂々巡りにはなるが、小林秀雄がモーツァルトの音楽の一小節に悲しみを勝手に見出していた可能性もあるのだから。
だから、素直にこう思うのである。文学と信仰の関係は深く複雑だが、小林秀雄に傾倒することもあるかもしれないが、まず自分が自分自身を信じるべきである。議論をおこなうには、まずこの前提が大切なのだと思う。ナポレオンであれ、家康であれ、世界のどんな偉人であれ、あなたの見ている世界を見ることは出来ない。あなたの見ている世界を表現するのは、あなたにしか出来ないことである。
今回は今村樹二亜が記述しました。今後も執筆者の紹介が続きます!乞う、ご期待!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
