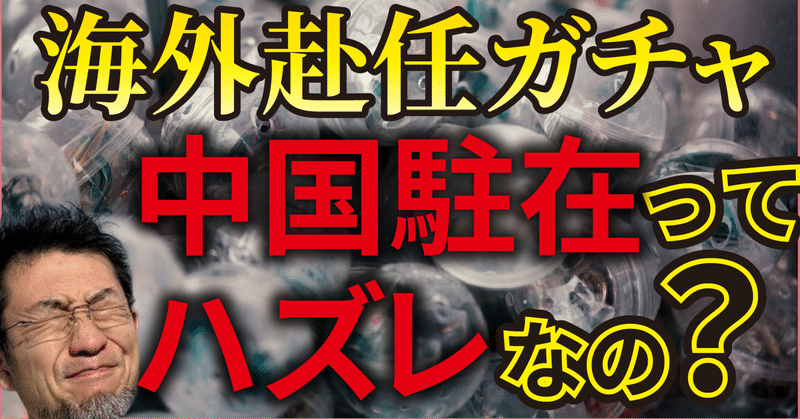
海外赴任ガチャ…中国駐在ってハズレなの?
日本の会社で中国赴任を命じられると、「ハズレを引いた」と嘆く人や泣き出す人もいると聞きます。複数の海外拠点を持つ会社では、駐在員から「アメリカがよかった」「希望はイギリスだったんだけどな」と、残念がる声を聞くことも。会社員にとって中国駐在はやっぱりハズレなんでしょうか。
このnoteは、毎週水曜に配信するYouTube動画のテキストバージョンです。
記事の末尾に動画リンクがあります。
中国駐在はある意味ハズレ
今回は「中国駐在ってハズレなの?」というタイトルをつけました。身も蓋もないことを言えば、やっぱりある意味ハズレかなと思います。今から行く人や着いたばかりの人には申し訳ないですが。
どんなところがハズレか、挙げてみます。
中国語
まずは言語面でハズレです。中国では英語がなかなか通用しません。上海あたりなら場面によっては通じるかも。ほとんどの社員が日本語をしゃべれるというごく一部の会社を除き、基本的にはすべて中国語です。
中国語の素養がある方はいいですが、日本で小さい頃から中国語に触れてきたという人はあまりいないと思います。言語コミュニケーションのハードルが高く、がんばって学んでも他ではあまり使えません。
日中関係と政治体制
国と国の関係も厄介です。比較的おだやかな時期と、ビジネスに大逆風の時期があり、コントロールはおろか予測も難しい。中国という国は、政治面で他の海外よりも気を使う点が多くあります。国内政治にも気をつけていなければなりません。
酒席・乾杯文化
他国にも酒飲みはいますが、ぜんぶ飲み干すまで帰さないとか、手から杯を下ろしていけないといったハードな乾杯文化はなかなかないと思います。下戸にとっては苦痛以外の何物でもないです。飲める人でも肝臓などをやられて体調を崩してしまうことがあります。
社内管理と不正
社内管理はどこの国もそれぞれに難しさがあるのですが、複数の国の駐在経験者から「中国はまだマシ」と言われたことはないです(基本的に、中国に比べればまだマシだった…ばかり)。やっぱりいろいろな意味で難しいんでしょうね。
また、中国の不正は一旦発覚すると規模がデカいです。私が案件として手がけただけでも10億円以上のケースがありました。フィリピンやインドネシアで、100ドル、1,000ドルの使い込みで従業員を解雇したという話を聞くと、遠い世界を見ているような気分になります。
取引のトラブルと役所対応
取引のトラブルも厄介です。代金を支払わない、供給が滞る、勝手に他社を優先してしまう、いろんなことが起こります。契約の通りにならないとか、裁判で決着したのに解決しないとか、一筋縄ではいかないことが多いです。
取引先以外にも、中国は役所が強いお国柄です。環境、安全、消防あたりの当局から「ライン停止か、この設備を導入するか、どっちか選べ」みたいな態度で迫られたりします。
簡単に設備と言っても億単位です。嫌なら月末で稼働停止。どっちも選べない…と言っていると他国では三択目が隠れていることもありますが、現在の中国では二択と言われたらたぶん二択です。2000年代前半ぐらいまではナアナアで何とかなることもなきにしもあらずだったものの、いまは基本的に厳しいです。
行く街によってもだいぶ違う
これは中国に限ったことではないですね。赴任地が都会ならいいけれど、周辺に日系企業はウチだけ、日本料理店はゼロ、日本語を聞く機会さえないという地域もあります。本当の田舎だと、上下水道が未整備だったり。そういうところでは生活が大変です。
「対日本」で考えたハズレポイント
中国に駐在した後に日本での立ち位置がどう変わるかを考えても、確かにハズレと認めざるを得ないです。
欧米中心主義で異端児扱い
特に大規模な会社で多いケース。同じ駐在員でもアメリカやヨーロッパの人たちが幅を利かせていて、グローバル=欧米という図式が出来上がっている。こういう会社では「北米閥」なんて言葉も存在します。
欧米帰りの声が大きく、なかなかアジアの話は聞いてもらえない。欧米中心主義の会社では、中国はかなり端っこに位置します。肩身が狭いだけでなく、異端扱いされることもあります。
中華圏から出られない
いくら欧米中心主義でも、会社にとって中華圏は大事な市場や事業基盤だったりするので、誰かが行ってマネジメントしなければいけません。しかし、中国には先ほどから言っているさまざまなハードルがあります。それらをうっかりクリアしてしまったのが中国駐在員の皆さんです。
となると、いちど中国に赴任したら最後、延々と中華圏をスライドして歴任するというパターンにはまりがちです。結果的に何十年も中華圏から出られなくなる方もいます。
これは本人のキャリアのためというより、「代わりが見つからない→誰かに行ってもらわないと困る→誰が行けるんだ→彼しかいない」。で、図らずも中国専門になってしまいます。
経験が活きない
中国で経験したことを他国ですぐに使えるかというと、これもまた難しいです。欧米にはまったく違う世界が広がっています。日本でもマネジメントの方法やリーダーシップを発揮する力点が違っている。いちど中国に行くと潰しがきかないと感じる方はいるかもしれません。
本当にハズレガチャでしかないのか
身も蓋もない話を連発したのですが、では中国駐在=ハズレガチャで確定かというと、私は考え方によると思います。
私は大当たりを引いたと後から思ったタイプです。行った当初は本当に苦しくて、体重も10キロぐらい減り、過度のプレッシャーとストレスから甲状腺機能障害に苦しみました。七転八倒ではあったけど、振り返ってみると「いやぁ、大当たりだったな」という気がします。
中国駐在は、人によっては大当たり。見方によって当たりになるポイントを挙げてみます。
中国語を母語とする人は10億人
中国語を母語とする人の数は、実は世界最多です。英語より多いんですね。中国語の標準語(北京語)の母語話者は8億~10億ぐらい。英語を母語とする人が3.5億人~4億人、それにスペイン語が続きます。
母語に限らない話者のトップは英語で、13〜14億人ぐらいだそうです。これもその次が中国語なので、英語ができて中国語も話せるとなると20億人以上と話ができることになります。これは結構すごいことです。
日経新聞の全紙面に登場するぐらい一衣帯水
日経新聞に取り上げられるニュースのうち、欧米発のものと中国発のものがどれぐらいあるか、私は普段から気にしています。ちゃんとした統計は取ってないですが、私の体感では圧倒的に中国のニュースが多いです。毎日一面から最終面まで、ほぼ全ての面に何かしらの中国ネタが出ています。文化面にまで出てきますから、中国は本当にさまざまなニュースを日本に提供しています。
その理由の一つは、地政学的に近いからだと思います。中国と日本は良くも悪くも関係が深く、お互いの影響力を考えざるを得ない。日本人も関心を持っています。欧州あたりの国よりも圧倒的に日本との関係が深い地域を押さえられるのは、中国駐在の利点です。
自動車・AI・DXの最先端実験場
自動車産業は100年に一度の大変革時代と言われています。内燃機関を使わないEV車の存在が世界で急速に大きくなりました。先鞭をつけたのはテスラだったのに、中国・中国勢が早々と主役の座を奪ってしまいました。もうEVは中国抜きに語れません。
さらに、中国の変化は極端に早い。半年単位で市場の状況がどんどん変わっていきます。他国の5倍、10倍のスピードで、ものすごくいろいろなことが起こる。ライバルがしのぎを削り合って潰れたり、新しいプレイヤーが出てきたり、バチバチやり合っています。
EVだってBEV全盛時代がしばらく続くかと思いきや、すでに淘汰が始まり、PHEVにシフトしつつある。この先もユニークなアイデアや技術が続々と出てきて、ほとんどは潰れ、有望なものはすぐ猛烈な模倣と競争が始まります。淘汰が進み、勝者も変化し続けないとすぐ落伍する環境で、どんどん変化が生まれるでしょう。
産業の中でも最も裾野が広いと言われる自動車業界。その最先端の実験場を生で見ることができるのは、関係者ならずとも非常に大きいと思います。中国の状況イコール世界の未来とは限りませんが、一つの可能性ではあります。
中国と同じようになっていく国もあるのではないか、中国の5分の1の速度で変化が進んでいくとしたらどうなるか。中国で変化が起きた時間の5倍の猶予があるわけですから、何をしていけばいいのか考える機会が作れます。
また、AIやDXなど、これから社会に大きな影響を及ぼす、最も先端的な新しい変化の実験場でもあります。
中国には、ラボの中にとどまらず、新しい技術はすぐに商売に変えて試してみる人たちが無数にいます。99.99%がアイデア倒れで潰れていっても、ものすごい勢いで、ものすごい数の人たちがトライしていますから、その中から浮き上がってくる事業、アイデアは必ずあります。
この分野では日本はかなり後方のランナーなので、中国の変化がすぐ日本に波及することはないかもしれません。でも、TikTokやSHEINがアメリカやヨーロッパに与えた影響をみると、これから日本発の新しいことが欧米に広がる可能性より、中国発のベンチャーが日本の外の世界に大きなインパクトを与えていく可能性の方が高いと感じます。
中国駐在では、その最先端はどうなっているのか、生で見ることができます。
アジア時代の黒船を知る
10年前、ここまでのスピードで中国が日本を抜いて自動車輸出ナンバーワンになるという予測は、どこの調査機関もしていなかったと思います。2023年、中国の自動車輸出台数は世界のトップに立ちました。
自動車産業に限らず、ヨーロッパにしても、アメリカにしても、アジアの他のエリアにしても、アフリカにしても、中東にしても、日本がこれまで進出して勝負してきて、ある程度のポジションを占めていたところに、アジア勢がどんどん殴り込みをかけてくる時代になりました。
彼らのたくましさ、戦い方、強みと弱みを知るには、中国が最も適した材料です。中国勢よりも脅威になるプレーヤーは少ないと思います。
異文化組織の虎の穴
先ほど中国の組織マネジメントは潰しがきかないと言いましたが、応用の仕方次第です。
現地に行けばすぐわかるように、中国人と一言でいってもカラーは一つではありません。上下も横も振れ幅が本当に大きい。優秀な人はとてつもなく優秀だし、どうしようもない人は本当にどうしようもない。赴任先にも、少なくともウチの会社には不適合でしょというような人が混じっています。
いろいろな人が混じった組織をどうやってマネジメントしていくかが中国駐在の鍵だとすれば、実はこれ、他国でも一緒です。日本だって単一文化かと言われたら、60代と30代は違うし、40代と20代の新入社員だって違う。関心を持っていることもコミュニケーションの仕方もぜんぜん違います。
そう思えば、世界のどこに行っても「異文化」の混成組織であることは間違いありません。バラバラな人たちをまとめるという異文化混成組織の核心部分は、どこでも応用できると私は思っています。
「虎の穴」と表現したのは、中国で学んだ人が他に行って手こずることはそんなにないと思うからです。言語や宗教の違いなど、中国流がそのまま通用するわけではありませんが、中国で異文化混成組織のマネジメントを鍛えられた人なら、たぶんどこに行っても「これならいけるな」と感じるはずです。
また、特にアジア圏では多くの国で華僑の存在感が非常に強いです。私もシンガポールやタイに行って痛感しました。フィリピンもインドネシアも、ベトナムもそうでしょう。中国語もけっこう通じます。なので、アジア圏では中国流の方が日本流よりもうまくいく局面がある。日本に近い国だったら、日本人としての日本的なやり方と、シビアな状況に対応できる中国的なやり方の両刀使いであればなお良しということになります。
生の情報が取れる
中国は生の情報が取りにくい国です。さっき日経新聞に毎日載っていると話しましたが、メディアの情報を追っていれば中国のことはだいたい把握できるかというと、全然そんなことはありません。
特に直近で起きている大きな変化は、現地に行っていないとわからない。あるベテランの駐在員さんが「帰国して3か月も経つと、もう中国の今を把握できてない気がして不安だ」と言ってましたけど、まさにその感覚です。
駐在員も帰任してしまえば新しい生の情報は取りにくくなるかもしれません。が、だいたいこれぐらいのスピードで変化するなという体感はあるので、日本で得た情報を頭の中で補正できるようになります。ここは現地に行った方と行っていない方では大違いだと思います。
現地の風圧を体感できる
変化のスピード、中国のプレーヤーのレベルアップの仕方など、さまざまな風圧はやっぱり行かないとわからないです。
現地で中国勢の風圧を感じると、自分たちの戦い方を考えるきっかけになります。外から見ているだけでは「中国勢は勢いがあっていろいろチャレンジはするけど、クオリティとかアラも多いから、他の国に進出して浸透する力はないでしょ」みたいな感覚になってズレていきます。
他の商売をするにしても、中国を離れた後にしても、中国勢の存在感・成長レベルは知っておいた方がいい。これからの日本のライバル、潜在力の大きなプレーヤーとしての中国を、日本の仕事人は理解しておくべきです。
「和魂洋才亜力」への道
世界の巨大圏はアメリカと中国であり、英語と中国語です。先日シンガポールに行きましたが、私が接した限り、タクシーの運転手は10人中9人が中国語を話しました。みんながペラペラということはなく、英語とチャンポンになっている人もいたので、中国語がベースだとは言いません。でも人口の7割ぐらいが中華系だそうです。やっぱりすごい存在感です。
この傾向はヨーロッパでもあると聞きます。アフリカも、いまの経済支援などを含めた展開のスピードから考えれば、中国勢が力を強めていると思います。
二大圏を比較すると、英語圏はアクセス手段が豊富にあります。ビザなしで行ける国も多いし、現地の情報もフィルターを介さず得られ、すぐにやり取りできます。
一方、中国語圏はなかなか住まないと見えないところがある。言葉の問題で、翻訳されない情報が入ってこないこともありますが、経由する人/メディアによってフィルターがかかります。
私はずっとYouTube動画(水曜便)で、これからは和魂洋才に亜力(アジアのパワー)を加えていかないと勝負できないという話をしてきました。仕事人が和魂と洋才と亜力を備えた人材になるためには、中国に住んでビジネスをしてみることがいちばんです。
アジアのたくましさを学ぶなら中国ではなくてインドだ、と30年後には言われるかもしれませんが、まだしばらくの間は、影響力が大きいのは中国だと思います。
今日のひと言
意欲的仕事人なら大当たり
「中国駐在はハズレか」ときかれたら、「普通の人ならハズレかもしれませんね」と答えます。
でも、もしそこで終わる仕事人ではないなら、これから外の世界で、あるいは日本で、新しい時代の日本の経営にチャレンジしていきたい、リーダーとしてチームをまとめていきたいという意欲のある人であれば、中国赴任は大当たりです。これ以上に鍛えられる機会はないと私は捉えています。
YouTubeで毎週、新作動画を配信しています。
【中国編|変化への適応さもなくば健全な撤退】シリーズは、中国/海外事業で経営を担う・組織を率いる皆さま向けに「現地組織を鍛え、事業の持続的発展を図る」をテーマとしてお送りしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
