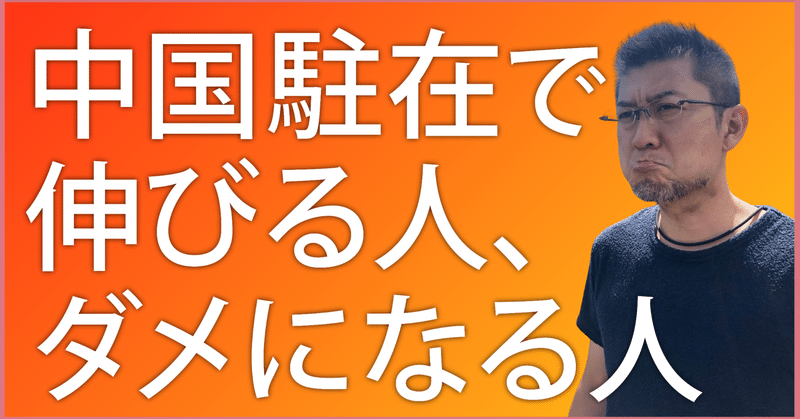
中国駐在で伸びる人、ダメになる人
このnoteは、毎週水曜に配信しているYouTube動画のテキストバージョンです。
記事の末尾に動画リンクがあります。
最近、議論していて「中国駐在員の中には、帰任してから仕事ができなくなってしまう人が一定数いる」という話になりました。そこで、これまで20年くらい駐在員を見てきた印象から、中国駐在で成長する人とダメになってしまう人の特徴をまとめてみます。「小島の偏見」ではないと思いますよ。
中国駐在でダメになる人
どんな人が「ダメになる」かを挙げます。あくまで私の体験と伝聞ベースですけれど。
遊びにはまる人
これは中国だけじゃないですよね。特に多いのは東南アジアだと思いますが、プライベートの息抜きを通り越して、遊びにハマってしまう駐在員がいます。
典型的なのは夜遊び。修羅場になって強制帰任させられた人もいますし、美人局の後始末は私も両手の指では足りないぐらい手がけました。
それからゴルフ。仕事上の付き合いのつもりがハマってしまい、毎週のように出かけて費用は会社持ち。現地社員からは白い目で見られます。
遊びの範疇を超えて悪事に手を染めてしまう人もいます。リベート要求や、不正取引に手を染めてしまう。社員や業者に巻き込まれる(もちろん弱みを握られる)人もいれば、自分が主導して親玉になっている悪質なケースもある。これらは帰任後の懸念どころか、仕事人生を棒に振るような問題です。
こうして、自分では「駐在中だけのちょっとしたお遊び」と思っていても、ハマってしまうと、帰任後は日本の仕事のペースに全然ついていけず、ドロップアウトすることになります。
異文化に適合できない人
異文化に適合できず、職場で浮いてしまう人も要注意です。
現地の社員から総スカンを食らったり、逆に存在感ゼロで飲み会やイベントにも決して誘われない。いずれにせよ現地にいる意味がありません。
適合できないストレスから暴飲暴食に走る人もいます。夜中まで飲み歩き、アルコール依存症に限りなく近づいてしまう。仕事に支障をきたすようになれば強制帰任です。
なかなか現地に適応できず本社が見かねて帰任させた、あるいは本人の要望で途中リタイヤしたとなると、帰任後にはチャレンジングな仕事を任せてもらいにくくなります。
さらに深刻だと心身の健康を損なうケースもあります。現地で倒れて要療養になった人、仕事がつらくて退職してしまった人、亡くなってしまった人も見てきました。
木を見て森を見ない人
視野を広く持てずにマイクロマネジメントに走ってしまったり、駐在員としての中核業務を無視して、慣れている仕事にばかり専念してしまったりする人もいます。
特に総経理や工場長のような立場では、日本で経験がなくても、現地に行ったら自分で決めなきゃいけないことがいっぱいあります。
例えば…
・役所から巨額の罰金を納めるか生産停止か選べと言われた。
・社員がストライキを起こして不当な要求をしてきた。早く生産再開しないと供給責任問題が起きるが、条件を飲んだら今後の経営が成り立たない。
どっちを選んでも地獄だけど、いま決めるしかないという局面です。
こういうときに視野狭窄に陥って、自分で決められない人がいます。ナンバー2としては非常に有能でも、正解のない状況に追い込まれると弱いタイプです。
遊びにはまる人は経営に向かない
中国駐在で潰れやすいタイプを3つ挙げましたが、いずれも本人が悪い・問題があるというより、適性がないんだと私は思っています。
人はなかなか変われません。適性の問題を解決しろと言うつもりはないです。会社や組織としては、むしろ適性を確認できてよかったと捉えて、あとは全体最適の観点から考えればいいと思います。
トップの座を任せると潰れてしまう人には、ナンバー2やエキスパートとしての仕事を与えればいい。異文化に適合できない人は、馴染みある環境に配属して力を発揮してもらえばいい。
しかし、遊びにハマってしまう人には要注意です。
昔の歴史小説では、閑職に追いやられた有能な人が、風が吹くまで待っている風車のような心境で、特に余計なことをせずに、力を貯めて英気を養い、牙を研ぎながら来たるべきチャンスを待つというシーンが出てきます。
海外駐在だと「駐在中はどうせ評価Bで固定だし」「役員もここの拠点は見てないし」「ちょっとぐらいお手盛りでもいいでしょ」と考えて、遊びにハマったり、手を抜いたりするタイプ。
気持ちは理解できなくもないですが、これからの経営には向きません。
これからの日本は、リーダーがいなくてもマネジメントで利益が上がった時代とは違います。トップはリーダーとして「なぜやるか/やめるか」「何をやるか/やめるか」を決めていく仕事です。
駐在員は現地のトップ・組織のトップ。トップのリーダーシップを求めている現地社員たちがいるのに「評価が変わらないから遊ぶか・手を抜くか」という人は、非常に利己主義か役割理解不足。人を率いる器ではありません。
リーダーとはチームの向かうべき先を示し、そこに向けてチームを動機づけリードしていく仕事。自分がビジョンや挑戦目標に全力を尽くさず手を抜いているトップに、本気で従う人はいません。
いくら有能でも、自分の評価や上司の顔しか見ず、現地の社員や顧客のことを考えられない人は、将来を担う経営幹部・リーダー候補失格だと覚えておきましょう。
中国駐在で伸びる人
こちらも3タイプにまとめてみました。
楽しめる人
駐在を楽しめる人は強いです。食べ物や言葉の違いにストレスを感じたり、腹を立てたりするのではなく、そのこと自体を楽しめるタイプですね。
現地に行くと想定外に遭遇します。日本だったら部下たちのお膳立てがあり、自分の予測可能な範囲でしか仕事が動かなかったかもしれませんが、現地では毎日が想定外です。それを楽しめる人は伸びます。
日本の経営だってグループの経営だって、未来の確かな答えはない世界。未知の未来・巨大な想定外にどう対処するかがトップの仕事ですから、想定外への対応力はリーダー・経営者として重要な資質です。
それから、中国という社会はすべてが駆け引きです。社員とも駆け引き、お客さんとも駆け引き、取引先とも駆け引き、役所とも駆け引き……。それでも消耗したり疲れたりしないタイプは強いです。
好奇心がある人
現地では、自分の知らないタイプの人、枠からはみ出た人がいっぱいいます。自分の常識では測れない流儀や事態にも遭遇します。こういう「自分の知らない世界」に対する好奇心がある人も伸びます。
現地の人たちの行動原理や、レストランや新しい店など街のすべてに好奇心を持って、あちこち見て回って、いろいろ試していける人は現地への適応が早いです。
返報性の法則で、こちらが相手に好奇心を持って入っていくと、相手も関心を持ち、受け入れてくれますから、仕事がしやすくなっていきます。
楽しめる人、好奇心を持っている人は、周りが味方してくれたり、助けてくれたりします。お会いしてきた方々を見ていると、本人の力だけじゃなく、追い風や後押しもあってさらに伸びるのかなと思います。
相手を渦に巻き込める人
自分の渦に相手を巻き込むことができる人も伸びます。
向こうは日本語がしゃべれない、こっちは中国語がわからない、英語も通じない。そんな状況でも、めちゃくちゃな言葉を使って、とにかく直接対話しちゃえる人だと、相手は困惑しながらもだんだん巻き込まれます。そうしているうちに、次第に呼吸が合ってくるようになります。
甘え上手もいいですね。社員たちから「またですか…」と突っ込みを受けつつも、なんだかんだ周りが世話を焼いてくれるようなポジションに乗るのが上手な人です。
それから「独裁者」タイプ。本物の独裁者は困りますが、リーダーとしての迫力を出せる人です。会社のルールには不備もあるし、グレーゾーンもあります。でもいざという時は自分が決めるんだという強さを持ち、時々発動して、相手を自分のペースに巻き込んでおきます。
こういうキャラが確立できていると、例えば、業績の厳しい時に大幅な昇給要求を一蹴したり、規定や制度の厳格化を打ち出したりしても、「あの人ならしょうがない」と周囲も受け入れます。
キャラじゃない? 意識すればできる!
楽しむ、好奇心を持つ、自分の渦に巻き込むように人と接していくというのは、自然にできる人もいますし、意識して努力できる領域でもあります。「私はそういうキャラじゃないから」という人も、海外でしっかり仕事して帰りたいと望むなら、こうしたことを意識してやってみてください。
今日のひと言
会社側は、中国駐在を幹部社員の登竜門にしてください。残念な結果に終わることもあるかもしれませんが、それは人材を潰してしまったのではなく、適性を見極めたということです。
駐在員は、駐在期間を「一回休み」にせず、そこから先によりチャレンジングな仕事をしていくためのチャンスと捉えて取り組んでもらえたらと思います。自分自身や会社にとってだけじゃなく、現地社員、現地でかかわる全ての人にとっても、その方がプラスです。
YouTubeで毎週、新作動画を配信しています。
【中国編|変化への適応さもなくば健全な撤退】シリーズは、中国/海外事業で経営を担う・組織を率いる皆さま向けに「現地組織を鍛え、事業の持続的発展を図る」をテーマとしてお送りしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
