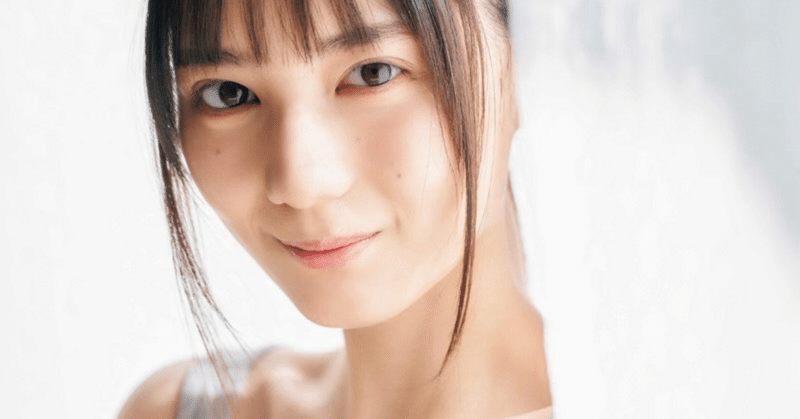
2人のエンリケに導かれたメトロノームが、エンリケを導いた夜
話題を振りまいたのは終始あのマヌケ面だったが、試合の本質はそこにはなかった。あってたまるか
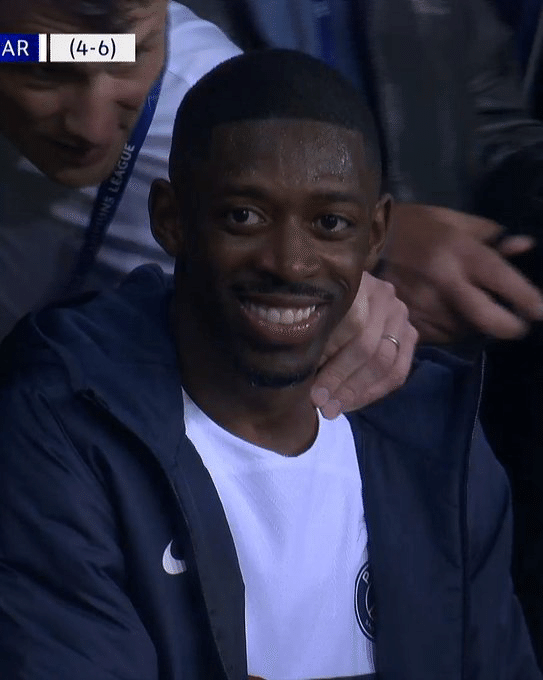
本当にあたまわるそうで草生える
偉大なる𝑷𝑨𝑹𝑰𝑺 𝑺𝑨𝑰𝑵𝑻-𝑮𝑬𝑹𝑴𝑨𝑰𝑵のスタメンは、全て大方の予想を裏切らないものだった。1stレグの後半から変わったのはどう見ても実力不足のルーカス・ベラウドが出場停止明けのアクラフ・ハキミになった点のみ。李康仁がウォーレン・ザイール=エメリになってる?まるで1stレグでWZEじゃなくて李康仁をスタメンで起用してたみたいな言い方だなオイ
故に、このスターティングメンバー相手の対策は、1週間の課題期限内に提出できたはずだった。理論上は。
日本中に跋扈するクソ大学生同様にシャビ監督が課題の回答を出せなかったのは、スカッドのプロメンバーを19人で開幕したバルセロナサイドの編成に理由を求めざるを得ない。層の厚さ・薄さが最も色濃く出るのが、累積警告と疲労が溜まるこのCL準々決勝、2ndレグである。PSGのルイス・エンリケ監督からしても、バルセロナが誰をどこで出してくるかは全部当てられたのではないだろうか。アンドレアス・クリステンセンとセルジ・ロベルトが出場可能だった1stレグ以上に。
予告通りの試験問題へのアンサーを期限通りに提出し、S評価を得たのはエンリケの方だった。ボールの奪い所を露骨にロナルド・アラウホに設定するというレポートは、的を射ていたと言わざるを得ない。誰がどう見てもアラウホにボールを持たせていたPSGは、そのアラウホから出てくるボールを全て中央に集めるように誘導。サイドでは真ん中に、ストレートに通させれば、ダイアゴナルにパスを出させるよりもカウンターに持ち込みやすい。そして、何より今のロベルト・レバンドフスキは肉体的な衰えもあって下がって受けたがるようになっているので、高い位置での奪取も可能だ。だから上背的には不利になるリュカ・エルナンデスとマルキーニョスという機動性能に特化したコンビになっていたし、もっと言えば誰がパスを出そうが結果は変わらなかったはずだ。アラウホを狙ったのは、彼がバルセロナ守備陣のキーマンだったからに他ならない。彼くらいの足元レベルなら、あれだけの自由を与えれば的確に相手の嫌がるところにパスを出せるのは先制点を見ても明らかである。
話をレバンドフスキに戻すと、従来までなら、プレスネル・キンペンベの不在を嘆くところだっただろう―2年連続で対戦した20~21年のCLでレバンドフスキを完封したのが彼だ―。しかし、35歳にもなると欧州の大舞台の最前線で身体を張れるはずはなく、最近はキャリア初期にトップ下をやっていた経験を活かして、下がって受ける術を活用し始めた。1stレグはそれが奏功して、ベラウドの機動性能の限界とPSGサイドの本質的なアンカー不在を突くことができたのだ。しかし、エルナンデスがCBに移ってCBのどちらか一方が前に出られるようになったら話は大きく変わる。
エンリケが見事だったのは、実は長期離脱明け間もないヌーノ・メンデスの使い方だった。WG兼SBのようなWBだった過去の姿は封印し、後方業務に専念。人類が出来る仕事量を超過したせいでふくらはぎを爆発させた教訓を活かした。クルーシャルな仕事がしたいといきり立っていた16歳も、CKで暴れそうになった17歳もいつもの気怠げな雰囲気で相手にせず、隠し持っていたキックのバラエティーを披露してアラウホを退場に追い込んだ。CBのどちらかが高い位置に出れば、きちんと絞り切るなどポジショニングへの気遣いも見事だった。もっとも、バルセロナの先制点はそれが仇となっているが。
アラウホにPSGが感じさせたストレスは、観ている人間には見えにくいが、想像を絶するレベルでもあったのではないかと推察する。ビルドアップではブラッドリー・バルコラが忠実に右足を切り、あまつさえボール奪取すら試みてきていた。ディフェンスシーンで牙を向くのはキリアン・エンバぺと、ジューレス・クンデが手を焼いていたバルコラとファビアン・ルイスのコンビネーションである。おまけに横は17歳と若く、まだプロデビュー間もないパウ・クバルシ。自らが起点となった先制点である程度落ち着けたと思えるだけに、退場を擁護するのは難しいが、メンデスのスライディングフィードもバルコラのランニングも極めて見事だっただけに同情の余地は十分にある。DFのランコースに入れば飛ばなくてもPKになるのだから。ちなみに同情の余地があまりないのはジョアン・カンセロである。なんやねんあのナチュラルにしょうもないファウルアラウホを退場に追い込んだ立役者、と書けば相当悪意はあるが、バルコラの守備貢献は見逃せないファクターだ。敏捷性と長い脚を活かした球際の強さはドリブルだけでなく、守備でも活かされている。高度な間接視野を活かした守備は、前線の選手では歴代でも例を見ないレベル。退場前にも一度危険な位置でカットされていたこともあり、アラウホにとっては相当なストレス要因だったのではないだろうか。
余談だが、審判へのストレスもアラウホ同様に過大になっていたように思う。過去に物議を醸したカードであり、この日の注目度も高いゲームである。前半開始早々にクバルシがエンバペを倒した対応は相当怪しかったが、時間帯を考えればまず流す局面だし、実際にそうだった。しかし、アラウホの決定的なシーンでスイッチが入ってしまった。イエローを乱発していたものの極力準決勝に影響しないようにしていた人選(人選している時点で良くはないのだが)で、下準備も入念にしてきたことは窺えるだけに、非常にもったいなく感じた。一方でレフェリーをうまくコントロールするのもサッカーの一部なのかもしれないとは感じる。大半のレフェリーは試合を荒らすことと公平性を失うことだけは避けたいものなのである。一度バランスを崩されると、審判もバランスを崩してしまうものなのだろう。その意味でアラウホのプレーは流れを読めば失点してでも一番避けたいものであり、擁護するようなことを書きながら擁護しないと書いたのもここに要因がある。逆に言えば、ビハインドでアウェイの地に降り立ったPSGは、審判をいかに崩すかも重要なミッションだったと言えるだろう。エンリケのサッカーは、本人の発言と快活なイメージとは裏腹に割と陰湿である。これを狙っていたとまでは思えないが。
話を戻すと、レフェリーが自己をコントロールできなくなった状態で選手が1人消えれば、試合展開は当然大きく変わる。前半の早い時間に相手が10人になり右CBが世界最高峰の対人CBから17歳になれば、PSGはゆっくり試合を殺せばいいだけ。メンデスが支え、バルコラとファビアン・ルイスが攻め込み、エンバぺも絡んでくるPSG左サイドは次第に相手に多大な負荷を与える。開けた位置でボールを受けたバルコラが、バルセロナDFラインがボールウォッチャーになった瞬間を見逃さずに逆足で丁寧なグラウンダークロスを供給。逆サイドでWG/WBモードに入っていたウスマン・デンベレがボールを蹴り込む余裕を得た。大きかったのは、CFである程度エンバぺがデコイランにも徹してくれたからだろう。エンリケのマネジメントなのか、真に信頼できるチームメイトをついに得られたからなのかはわからないが、少なくともMCN時代―MNMではない―以来の献身ムーブである。
とはいえ、まだ試合を殺すには不十分だった。スコアの差もそうだが、中を固めれば勝てる筋が残っているバルセロナは、それを忠実に実行していたからだ。強調しておきたいのは、アラウホ退場後のバルセロナの対応は常套ながらも忠実だったことだ。元々レンヌでプレーしていてフランスリーグ相手の相性は実証済み―この2試合で再証明する必要はなかったはずだが―且つカウンター局面で強さを発揮するラフィーニャを残して、2試合を通じて本領を発揮できたとは言い難いラミン・ヤマルを下げた采配も、エンバぺ以外は得点力、特にミドルレンジのシュート性能が高くないPSG相手にエリア内を固める戦略もすべて理に適っている。シャビが退場したのはアホだと思う。
しかし、その戦略をヴィティーニャが無駄にした。デンベレからDFの間を通すパス―コース切りを怠ったギュンドアンのエラーだろう―を受け、バイタルエリアで自由を得る。そのバイタルエリアも捨ててエリア内に特化して守っていたバルセロナのゴールに、事前に2タッチもしてから丁寧に蹴られたヴィティーニャの繊細なミドルが刺さる。アタッカー陣の決定力不足も、中盤のエリア管理能力不足も一手に解決するこのポルトガル人MFが、PSGの真のボスであることを示した瞬間だった。てか他ももうちょい頑張ってほしいんやけど
極東は日本でキャンプを張った昨夏から、ヴィティーニャは明らかに中心性を増した。何をしたいのかわからなかったあの3試合で確信できたのは、エンリケのPSGで中心となるのはヴィティーニャだったことだけだろう。長居競技場で叩き込んだミドルがそれを示唆していた。その後、崩しを担っていたネイマールとマルコ・ヴェッラッティが中東へと旅立ったのは偶然ではない。属人的ではなく組織的にボールを前に進めたいエンリケにとって、長く運べる分依存性の強い2人よりもヴィティーニャの方が副作用のない薬に見えたようだ。パスレンジの狭さこそ否めないが、リスクを抑えてパスを刻んでチーム全体を押し上げられ、前線も務まるレベルのスピードとスタミナを利して前方も後方も支援することができる。足りてないと思えば前線へ駆け込んで適性のないミドルレンジのシュートにチャレンジするし、指示されればアンカーポジションに入って相手のアシストコース(特にマイナスクロスのコース)を丁寧に切る。ボールを持てば忠実に左右を見て、相手に恐怖を与える。誰もが気を遣う存在になったエンバぺを平気で無視するのも、表面的な数字ではなく自分に与えられた仕事に忠実だからである。ダニーロ同様のプロフェッショナリズムが彼をメトロノームたらしてめていて、個性になっているのだ。だからこそ、彼が決めると試合が変わるし、試合が変わる瞬間に彼が出てくるのである。PSGファンが中盤に抱えている不満の根源には、彼が守備のタスクから一定程度解放されればという願いがあるのかもしれない。なお来季のスタメン予想には決まって不在の模様。
試合を決めたのは、またもPSGが左サイドから攻め込み、空いた右サイドで待っていたデンベレのルーズタッチに単騎で短気に対応したカンセロが件のPKを与えた61分だった。そのPKが無事に沈められたのと時を同じくして、10人になったことで想像以上に早く消耗してしまったペドリが下がった瞬間、PSGイレブンの方針は無理に攻め込まずにやり過ごすことで一致した。恐らくエンリケとエンバぺの共通認識であったはずだ。かくして、相手とレフェリーにストレスを与えて塩漬けにした試合を殺したPSGが、3年ぶりのベスト4を勝ち取った。まだ始まりですらないのはPSGの全員がわかっているはずだし、フルメンバーを揃えることが叶わなかったバルセロナの全員が思っているだろう。彼らはこんな風に絶頂している暇もなく次に行くし、行かなければならないのである。半年前の日本一でまだ絶頂しているオレとは違って。
著:シェルドン・ノイジー像建立委員会名誉会長
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
