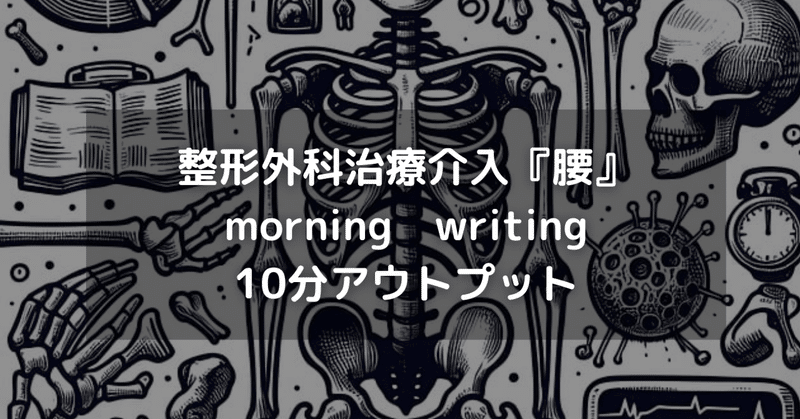
5.支持のための骨『椎骨』の基本構造
椎骨は前部(椎体)と後部(椎弓・上下関節突起など)が結合してなる
前部は支持、後部は機能として働く
前部は支持するため、常に重力による圧がかかっている
胸椎後弯と前屈でストレスが増大する。
椎体は、500~650kg/cm2まで耐えることができる
脊椎は頚椎、胸椎、腰椎と部位によって名前は違えど、椎骨で形成されています。その椎骨には『基本』となる形態があり、それを有している。
椎体と椎弓の構成
椎骨は、椎体と椎弓が結合されてなしているものである。
椎体は、ほぼ円筒状であり、その後方は平坦になっている。
椎弓は、骨性の半環状の形態をしている。
椎弓には、棘突起、横突起、上・下関節突起がある。
連なる上下椎体間をぞれぞれの上・下関節突起が椎間関節となり関節面をなしている。
椎骨の役割
前部脊椎(椎体と椎間板の複合体)
→強い応力を受ける部位であり、脊柱の支持を役割とする。
後部脊椎(椎弓、特に上下関節突起の構成)
→運動の調整機能として役割する。
前部脊椎の支持力
椎体
椎体の前方部分と後方部分との間には、かなり明確な骨量の構築学的差異があることに注意しなければならない。
前方部分の骨梁は、垂直骨梁と輪状骨梁がかなり疎である
後方部分は、特に後壁においては非常に密な組織が良く交差した骨梁で形成されていて、堅固に補強されている。
前方部を押しつぶすには健常で500~650kh/cm2以上の圧力が必要で、後方部ではそれ以上(650kg/cm2)が必要である
脊柱に加わる応力
重心
重心線は、関節構造単位の前方を通るため、この構成単位より上に位置する体の重量は、胸椎を屈曲させる力として作用する。この関節構成単位が水平位での平衡を維持するためには、屈曲力(重力の作用)が、伸展力(後方組織の他動的制動と、伸筋の収縮活動)によって釣り合わなければならない。
→基本は胸椎が屈曲するから背筋を鍛えようね!という話。
また、重心先が脊椎の支点からの距離は、以下2つの条件で変化する。
1.胸椎が異常に後弯している場合
2.体幹を前屈した場合
まとめ
椎骨は前部(椎体)と後部(椎弓・上下関節突起など)が結合してなる
前部は支持、後部は機能として働く
前部は支持するため、常に重力による圧がかかっている
胸椎後弯と前屈でストレスが増大する。
椎体は、500~650kg/cm2まで耐えることができる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
