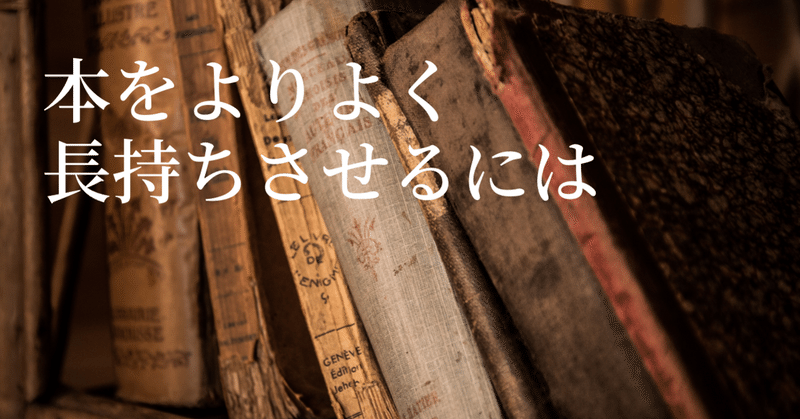
本の寿命
皆さん、こんにちは。紙通販ダイゲンです。
先日、長く持つような本を自作したい!というお問い合わせがありました。
情報を長期間、なおかつ大量に保存しておく際には本にしておくのが未だに多いですね。現在は図書館が様々な本の保存場所としての役割を担っています。
さらに、最近では電子化も進められていて、わざわざ図書館に行かなくても本を閲覧できるようになる動きが高まっています。
そんな中でも実は年々図書館の数も増えていて、紙媒体での蔵書の数は過去10年の間でも5万冊以上増えています。
なぜ、スペースも取らず大量のデータを保存出来るHDDなどではなく、紙媒体が選ばれるのでしょうか?
今回は本の、ひいては印刷物の寿命のついての話をしたいと思います。
皆さんも、お気に入りの本は少なからずあると思います。痛まないように大事にしたり複数買って置いたり・・・・・もしくは好きな画家の方の絵でも構いません。そういうものは丁寧に扱いますよね。
でも中古の本は必ず黄ばんでいたり、表紙の印刷の色が薄くなっていると思います。では、なぜそうなるのでしょうか?
紙自体は短くても100年ほどは持つようになっています。和紙は1000年以上耐えるなんてことも言われています!
ですが、インクの方はそこまでの耐久性はありません・・・・なぜならインクは紫外線に弱いからです。
一番長く保存したいのならば、日の光が届かない湿度と温度が一定の場所に本を手で触らずにずっと置いておくことがベストなのですが、それほどまでして保存しておきたいものならば手元に置いておきたいのが人間の性。また読みたくなったりしますよね。
退色を防ぐためにまずは原因を知っていきましょう。
印刷する際にはCMYKの4色の組み合わせで様々な色を表現しています。これの内黄と紅の2色が紫外線に弱く、長期間の間紫外線に当たってしまうと本来の色が出なくなってしまい本来の色が出なくなってしまいます。
その結果、バランスが崩れて退色してしまう、というのが原理です。
なので、紫外線をできるだけ避けるような保存の仕方をしていきましょう。
紫外線はかなり強力で、一か月間ずっと太陽光の下に置いておくだけでももう退色してしまいます。
それに加えて、製本方法によっても耐久性は変わっていきます。
テープで止めてしまうとすぐに傷んでいきますね。
製本する際にホッチキスで止めてしまうのもやめておいた方がいいでしょう。保存するには向いていません。ホッチキスの部分から錆びてしまい、傷んでいきます。
一番良い方法は和綴じですね。
和綴じは本を止める際に、紐で縛って固定してあるアレですね。
あれならば錆もしないですし、長期的な保存には適しています。
公文書や閣議の資料など・・・・・本当に大事な書類などは今も和綴じで保管されています。和綴じで製本するのはかなりの労力にはなりますが、数十年、何百年と保存される必要がありますからね。
どんなに技術が発展しても最適な方法は昔から変わらないっていうのは面白いですね。先人の知恵を切り捨てるのは簡単ですが、理解して生かしていくこともまた大事だと言える一例です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
