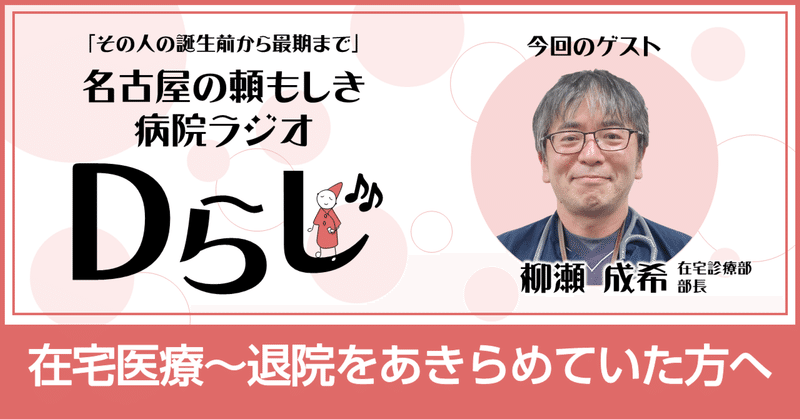
患者さんと医師がじっくり向き合う在宅医療
医師が自宅へ来てくれる「在宅医療」の重要性がますます高まっています。
定期的な訪問で、診察・検査・薬の処方などを行うほか、緊急時には往診もしてくれる。
「自宅では●●ができないから、退院できない」という理由での入院長期化をできるだけ解消し、住み慣れた地域で過ごせるように、今日も医師たちが奔走しています。そんな在宅医療に、急性期の医療機関で関わっている医師がいます。だいどうクリニック在宅診療部の柳瀬成希医師に話を聞きました。(2024年3月6日配信)
病院医療と在宅医療
イズミン 先生は、高度急性期医療を担う大同病院の消化器内科医として勤務されていたところから、在宅医療へシフトしていったわけですが、病院医療と在宅医療はどんな点が違うと思いますか?
ヤナセ 急性期の医療と在宅診療は、水と油みたいなところがあります。在宅でもいろいろなことができるのが、当院の在宅診療部のウリの一つではありますが、それが必ずしも在宅療養の価値観にとっていいかというと、いい場合ももちろんありますが、そぐわないことも多いんです。
シノハラ それは、できるところまで治療をしよう、とか、治療するという選択肢があるならやるべきだ、という考え方があるけれど、在宅療養の場では必ずしもそれが正しいわけではなく、静かに苦痛を緩和するほうがいい場合も多い、という意味ですか?
ヤナセ そうですね、患者さんやご家族は、病院を退院して在宅医療に移行する時点で、ある程度、治療を諦めておられる場合も多い。ところが「在宅でも治療できますよ」と医師のほうから提示してしまうと、そこにすがってこられます。それがうまく行けばいいんですけれども、もちろんうまくいくこともありますが、うまくいかないときにもう一度諦めることにもなってしまいます。そういう選択肢の提示の仕方については、細心の注意を払って、そしてどんな選択をされても一緒に伴走するように心がけています。
在宅医療の風景
イズミン 在宅医療は、どんな方が対象になるんですか。
ヤナセ 基本的には外来に通院できない方が対象です。寝たきりの方や、あとは通院するにはご家族の方の介助・協力が必要だけど、ご家族が高齢だったり、お子さんが遠方にお住まいだったりしてどうしても連れてこられない方のところに伺うことが多いです。
イズミン どんなご病気の方がいらっしゃるんでしょうか?
ヤナセ 病気や病状としてはがん末期の方、病院から退院はしたけれど酸素吸入や点滴などの医療処置が必要な方、褥瘡があって治療が必要な方などがいらっしゃいます。それでも病院ではなく最後まで住み慣れたうちで過ごしたいと思われる方は多いと思うので、それが叶うように支援しています。
イズミン 医療処置も、かなりいろいろなことが在宅でできるんですよね。
ヤナセ はい。例えば、気管カニューレという、呼吸のために気管に直接穴を開けて喉から肺につなげる管を入れている方の管理、「胃ろう」といって、胃に直接栄養を入れている方の管理、腎瘻といって腎臓から直接おしっこを排泄する方の管理、もちろん末梢(手足)に点滴が入っていたり、胸のあたりから大きな静脈に直接、高カロリー輸液を入れている方の管理、在宅酸素療法や人工呼吸器の管理などをしています。そういう医療機器が必要な患者さんが、自宅で安心して過ごすために、在宅医は重要な役割を担っています。
胸水や腹水が溜まった場合にそれを抜く「ドレナージ」という処置なども必要時は在宅で行います。
イズミン 検査はどうなんでしょうか?
ヤナセ はい、血液検査は全然できますし、うちの診療部だと小型の超音波装置(エコー)を持っていて、いろいろな診断に活用しています。携帯用のエコーはスマホよりちょっと大きいくらいで、精度もすごく高いです。
あと、去年の4月から在宅輸血ができるようになりました。うちでやっているのは赤血球の輸血で、なかなか難しい処置ではありますが、安全に行えるように今、スタッフ一同で頑張っています。
高齢の方で、貧血など輸血が必要な方は増えていますが、やはり輸血の必要な方(貧血)というのは、やはり動くとしんどいんですよ。そういう方が、家から病院まで行って輸血して帰るという労力は、できれば他のことに使っていただきたいという思いがあります。
イズミン 普段はどういう形で訪問されるんですか。
ヤナセ 先ほど話した医療機器が必要な場合は、診療補助として看護師を伴って、状態が落ち着いている患者さんのところへは、基本的に医師1人でお邪魔することが多いです。重要な説明などがある場合には、看護師や事務に同行してもらってお話をすることもあります。
イズミン どのくらいの頻度で訪問するんですか。
ヤナセ 基本的には2週間に1回伺います。ただ病状によっては訪問頻度が増えることもありますし、定期訪問日ではない日でも診療が必要な場合は、24時間対応しています。
診察自体は外来での診察と変わらないとは思うんですけども、やっぱり患者さんの話もしっかり聞くし、こちらの話もしっかりするようにしています。
イズミン 病院の外来だと「3分」といわれますが、それに比べるとかなりいろいろなことをお話されるんですよね。
ヤナセ そうですね。やはり医師ですので病勢(病気の具合)のコントロールは大事で、辛い、苦しい思いをせずに安定した状態を続けていけるようにということも大事なのですが、患者さんやご家族がどのように過ごしていきたいのか、病気や今後の生活に関してどのように考えているのかということを常に考えながら、診療に伺っています。
多くの場合、いまの在宅療養生活は初めての経験なので、何かあると患者さんやご家族はすごく動揺されます。そこで僕たちがそれに乗っかっちゃうと、もうハチャメチャになってしまうから、前もって先回りして対応するように常に心がけてます。
イズミン これは宏潤会のバリューの一つ「おもてなしの心」ですね。
ヤナセ ただ、あまり先のことは聞きたくないという方も多いんです。やはり前もって、こういうふうになっていくんだよと、いずれは伝えなきゃいけないのですが、その伝えるタイミングは早すぎても、遅すぎてもダメなんです。
その見極めが難しいので、そのためにもコミュニケーションの時間はある程度必要です。じっくり話し合うとか、顔を見てお話するといったことは大事ですね。
イズミン 診療時間はどれくらいですか?
ヤナセ 診療時間は長い方だと思います。これは他施設の在宅診療医からも羨ましがられます。だいたいお一人に30~40分くらい、本当にしっかり時間をかけなきゃいけない患者さんの場合は、1時間以上になることもあります。
シノハラ 緊急往診はどれぐらいの頻度で行かれるんですか。
ヤナセ 患者さんの病態によっても変わりますが、たぶん皆さんが想像してらっしゃるよりは少ないと思います。もちろん在宅看取りの場合は往診には行きます。在宅の患者さんは、訪問診療と並行して、訪問看護のサービスを利用していることも多いので、主に訪問看護師さんから「往診を希望されています」という連絡が入ります。もちろん患者さんやご家族から、往診希望があった場合にも行きます。
往診希望でなくても「ちょっと心配でどうしたらいいですか」といった電話もあります。その場合は、電話で「この薬を飲んでください」という指示をしたりします。
在宅での看取り
シノハラ 在宅でのお看取りについて少し教えていただいていいですか。
ヤナセ 最期をどこで過ごすかというのは、末期の患者さんやご家族にとってすごく重要な問題ですが、それをしっかり考えてらっしゃる方もいれば、あまりそういうことは考えたくないよっていう方ももちろんいます。考えてないけど自宅で過ごしたいという方はやはりいらっしゃるので、病気の経過に沿って、最終的に自宅で看取れるようにサポートしています。
ただ、そういうところに到達するまでに、患者さん自身もご家族も揺れ動くんですね。状態は悪くなり、昨日までできていたことができなくなる。トイレに歩いて行けなくなったり、寝返りが打てなくなったりする。患者さん本人は次第に意識も落ちてくるんですけども、それを見ているご家族はだんだんできなくなっていく姿を見るのが辛かったり、ビックリされたりするんですよね。だけど、そういうことが亡くなるときの自然な過程なんだよということを知っていただくために、その都度、適切なタイミングで、ご家族やご本人にお話するようにしています。
シノハラ 確かに強い意志を持ってる人ばかりじゃないし、自分が初めて経験されることですから、揺れ動くのは普通のことでありますよね。急に不安になるとか。そういうときに先生が患者さんやご家族と向き合っていろんなお話をされことで、患者さんやご家族が、ある程度覚悟をある程度決めることができれば、自宅でお看取りすることはできるようになりますね。
ヤナセ 実は、こういう話をする役割は医師でなくても別にいいんですね。訪問看護師さんや経験のあるケアマネジャーさんでもいい。誰がやってもいいのですが、やはり(手前みそですが)医師の言葉って重いんです。医師がそういう話をすると、患者さんやご家族に必要以上にショックを与えてしまうことが多い。だから、看護師さんやケアマネジャーさんから、少しずつやんわりと伝えていただいて、最後に医師が話すのが理想的なのかなと個人的には思っています。
ですので、医師だけが頑張ってもダメ。患者さんを支える多職種の方がしっかりとタッグを組んでやっていく必要があります。特に自宅看取り希望だけど、ちょっと難しいんじゃないかなっていう患者さんやご家族の場合は、そういう皆の力が必要になってきます。やっぱりチームの連携がすごく大事なんですね。
だいどうクリニック在宅診療部の特徴
イズミン だいどうクリニック在宅診療部の特徴は、どんなところにありますか。
ヤナセ いろいろな選択肢を提示できるということかと思います。
在宅医療を希望される方は、やはり自宅で「できるだけ」過ごしたいっていう希望をお持ちです。この「できるだけ」というのがなかなか曲者で、患者さん自身の「できる」範囲、介護するご家族が「できる」範囲、訪問看護や僕たち訪問診療が、「できる」範囲というのがあって、それがちゃんと合致していればいいのですが、そうでないことも多い。
僕たち在宅診療部はもちろん自宅看取りにもちろん対応していますが、自宅では無理そうだという場合にも、患者さんやご家族の希望に沿った選択肢をきちんと提示できると思っています。「いやいや、もう病院に行ってる場合じゃないよ」と、無理に自宅に留めておくこともしませんし、その逆もまた然り「もう病院に行っても、あなたの思うような治療はたぶん受けられないと思います」ということをしっかり説明して「おうちで頑張ろう」ということもあります。どちらも正解なんです。
イズミン ところで在宅医療を始めるタイミングはどのあたりなんでしょうか。
ヤナセ 実は「もう少し早く在宅診療部が介入できていたら、より患者さんの利益になるのではないか」と思うことが、最近の僕たちの課題の一つとなっています。
イズミン それはどういう意味ですか。
ヤナセ やはり病院は、病気を治す、治って元気になって帰っていただくところなので、先生方もできるところまで頑張るんです。やがて「やっぱりダメだったね」というときが来るんですけども、それをもうちょっと早く決断していれば、もう少しお家で元気に過ごせる時間ができるんですね。
シノハラ なるほどね。頑張りきって、疲れ果ててから家に帰るのではなく、もう少し自分の体力なりがあるときに、ご自身の快適な自宅生活を過ごし始められたら、ということですね。
ヤナセ わたしたちがサポートすれば、多少点滴やら何やらいろいろ医療機器が必要だったとしても、ご自宅にも戻ることは可能です。「この状態で帰るのは危ないんじゃないか」って心配されて、退院が延び延びになっている場合もあると思うのですが、それをちょっと短くすることはできると思うんです。
入院してやるべき処置は病院でやったほうがいいのですが、これが入院してやることが必要ではない場合でも、「これがあるから家に帰れない」と思われていたとしたら、在宅診療部がご自宅でできることがたくさんあるんです。
イズミン 少しでも早く先生方が介入できるようにするためには、何が変わればいいんでしょうか?
ヤナセ ここ数年間で、大同には在宅診療部があるということは、わりと皆さんに知っていただけたと思うので、「在宅でできないでしょうか」というご相談があれば、いつでも連絡いただければ、随時、僕たちが説明に伺います。
イズミン それは大同病院に入院されている方だけじゃなくて、いろんなケースで対応可能ということですか?
ヤナセ はい、ケアマネジャーさんや訪問看護さんから、他の病院にかかっておられる方のご相談をいただくこともあります。
イズミン わかりました。だいどうクリニック在宅診療部だけでなく、いろいろな地域で、こうした医療処置に対応できる在宅の先生はいらっしゃると思いますので、ぜひお近くでご相談いただければと思います。
ゲスト紹介
柳瀬成希(やなせ・しげき)
だいどうクリニック在宅診療部長。元々は消化器内科の医師として内視鏡などを手掛けていた。大同病院への赴任時には、在宅医療に関わることなど全く予想していなかった。病気の治癒をまず目指す急性期医療とは異なる世界にも次第に慣れ、そこでこそ関われる医療にやりがいを感じている。趣味はマンガを読むこと。好きなマンガはたくさんあるが「オススメは?」と尋ねられて出てきたのは『うしおととら』(藤田和日郎)。昔読んだときには、ボロボロ泣いたという。
関連リンク
https://daidohp.or.jp/homecare/
