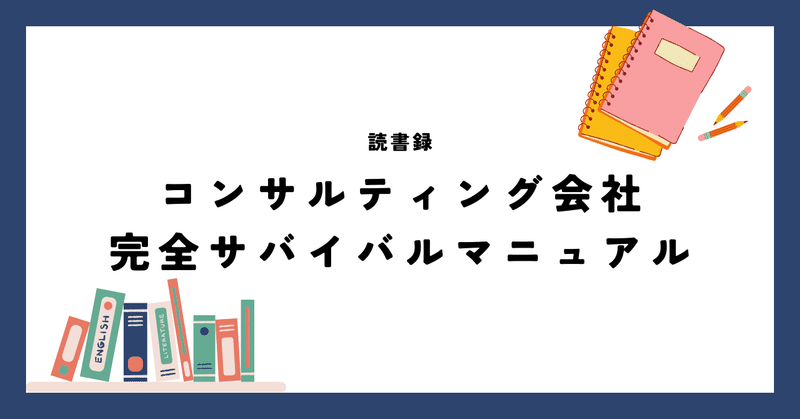
#33 「コンサルティング会社 完全サバイバルマニュアル」
今回の読書録は「コンサルティング会社 完全サバイバルマニュアル」
読んだきっかけはXで紹介されていたことでした(大体いつもそう)。
私はコンサルタントでもコンサルティング会社勤めでもありませんが、コンサルタントの仕事術には興味があります。
常に成果を求め続けられる人たちがどんな思考・行動様式を持ちあわせているのか、それらは自分の仕事にも活用できるところがあるのではないか。
そんなことを考えながら読みました。参考になったところをまとめてみます。
仕事における"速さ"の正体
コンサルタントの仕事に速さが求められるのは何となくイメージできます。
では仕事における"速さ"とはなんでしょうか?
著者は仕事の速さとは次の要素で構成されていると述べていました。
速さ=手順の熟練×最短ルートへの嗅覚×強い期限意識
1. 手順の熟練
まず手順の熟練はツールの操作・作業スピードといった物理的な速さのことです。
例えば
タイピングのスピード
ショートカットの駆使
ツールによる自動化
これらが熟練されていると当たり前ですが仕事は速くなります。Excelの関数やFigmaやXDのプラグインを知っているか知らないかで作業スピードは大幅に変わりますよね。
私の経験上、ツール系の情報やノウハウに興味を持たない人は一定数います。webやマーケティングの知識や経験が豊富でも、Excelの関数は手打ちでなんとかしてますといった方々を見たことがあるのではないでしょうか(それを否定しているわけではありません)。
今後はChatGPTをはじめとした生成AIツールを使っている人/使っていない人では、作業スピードの差がさらに拡大するでしょう。
自分の作業をより効率化できる手段はないかと常にアンテナを張り続けることが重要ですね。
2. 最短ルートへの嗅覚
最短ルートへの嗅覚とは作業前に段取りをクリアにイメージする力です。
作ろうとしているアウトプットに対して、
自分が頭を使うポイントはどこなのか
作業手順のイメージはついているか
自分だけでできない作業なら、誰の助けがどの程度必要か
その助けを得るための依頼は誰から誰に行うのか
提出前に誰の確認が必要なのか
このあたりの解像度が高い人の仕事はきっと速いですよね。
段取りをイメージすることの重要性は、webサイト制作でも全く同じだなと思いました。
例えばディレクターやデザイナー、エンジニアそれぞれがやるべきこと/やるべきではないことを明確にすることで、仕事のスピードは大きく変わります。クライアント側の意思決定者を明確にすることで、プロジェクトの進み方は大きく変わります。
最短ルートへの嗅覚はwebディレクターにとっても必要なスキルでしょう。
3. 強い期限意識
強い期限意識とは自分の作業時間を正確に見積り、生産性をキープすることです。
私の仕事ですと、例えばトップページのワイヤーフレームが完成するまでの時間はどれくらい必要なのかを正しく見積らなければなりません。
そしてこの見積りのズレは後工程に大きく響きます。
ワイヤーフレームは完成後にクライアントからOKをもらい、デザイナーにトスしなければなりません。デザイナーはそれを元にデザインを作り、再度クライアントに確認してもらいます。OKが出ればエンジニアが構築に入ります。
私の作業が3日遅れれば、それだけ各人のチェックや作業も雪だるま式に遅れます。スケジュールの遅れは必ずどこかに歪みを生みます。急いで作る、適当に確認する。その影響で後戻りが発生し、結果的に生産性は落ちます。
お恥ずかしながらこのあたりの見積りは私自身かなり甘いので、もっと鍛えていかなければならないと思いました。
まとめます。仕事を速くするためには作業ツールを極め、段取りをクリアにし、作業時間を正しく見積りましょう。押忍。
本当に解決すべき問題は何か。を考える
すべてのプロジェクトには、そのプロジェクトで本当に解決すべき問題が存在します。著者は論点という言葉を用いて説明していました。
論点を意識せずに仕事を行うと、自分たちのみならず、クライアントも含めて大きな迷路に足を踏み入れることになります。
そして実はクライアント自身も今自分たちが何を解決すべきなのか、どの問題にフォーカスすべきなのかを理解していないケースが少なくありません。
本当に解くべき問題を整理し、間違ったところに労力を割かないようにする。webサイト制作やデジタルマーケティング支援においても重要ですね。
作業が進まないのは考えるに値する材料がない
突然ですが「悩む」と「考える」の違いを抑えておきます。
「悩む」とは必ずしも答えはないモノに頭を使うことで、「考える」とは丁寧に事実を見ていけば解けそうなモノに頭を使うことです。
人の作業が進まない理由の多くは、自分自身は「考えている」時間が実は「悩み」の時間として消化されてしまっているからだと著者は述べています。
これは私自身も思い当たる節があります。
例えばワイヤーフレームの制作に行き詰まることがあります。この時、私自身は情報の構造や優先順位を頭の中であたかも考えているようでいて、実はそもそも構造や優先順位を決め得るだけの情報が不足している状態(ただ悩んでいるだけ)だったりします。
一見すると手が動いているように見えるのですが、どこへ向かっているのか、このまま向かえばゴールへ到達するのかがわからない状態で作業している人がいます。ええ、私のことです。
悩んでいる時間はエネルギーを使うので、仕事をしている気分になれます。悩んでいる自分に酔ってはいけません。
作業が進んでいないのは考えるに値する材料が揃っていないと認識し、もう一度情報収集したり人に話してみたりするといいでしょう。
自分で書いていて目と耳が痛いですが、とても大事なことだと思いました。
プロジェクトは最初の1週間が勝負
新規取引先にようなまだ関係性のできあがっていないクライアントとの仕事がスタートしたときは、まず最初の1週間でクライアントに対して価値貢献をし、信頼を勝ち取ることに集中しようと著者は述べています。
1週間でどんな価値貢献ができるのか…と思うかもしれませんが、小さなことでいいです。
ToDoが明確になった
アバウトなやりとりがドキュメントに落ちて明確になった
関係性のない状態で机上の空論ばかりを説いても相手には届きません。大きな変化を起こすためにこそ、まずは地道な信頼貯金の積み上げが大事。
個人的にはコンサルタントのような"価値貢献"とまでは言わずとも、普段より1.5倍早くレスポンスする程度でもいいのかもしれません。
いずれにせよプロジェクトはスタートダッシュをいかにうまく切れるかが重要であるということはコンサルタントに限らず、どんなお仕事でも通ずると思いました。
以上、コンサルティング会社 完全サバイバルマニュアルの読書録でした。
コンサルタントの思考術系の本は何冊か読みましたが、総じて言えるのは「言われてみれば当たり前のことを、どれだけ正確に早く行えるか」が重要だということです。
あとは仕事の速さのところでも書いたような一つの事象を複数に分解して考えることも大事だと思いました。
ただ単純に"仕事が遅い"と漫然と悩むのではなく、AとBとCのどの要素が原因で遅いのかを捉えることで、より適切な打ち手がうまれます。
そんな話がまだまだ詳細に書かれている1冊です。気になった方はぜひお買い求めください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
