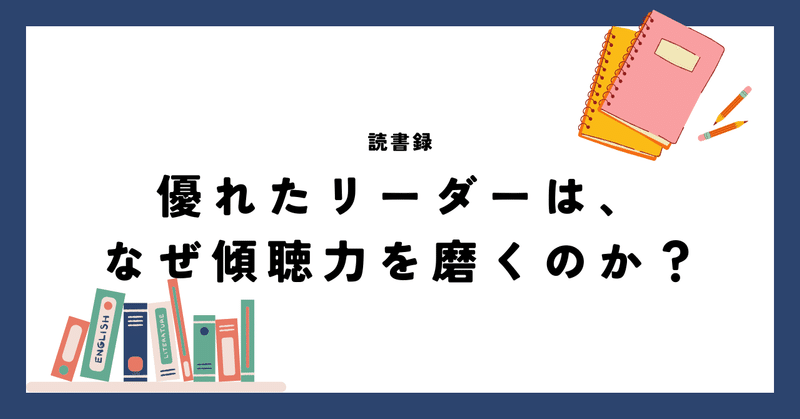
#43 「優れたリーダーは、なぜ傾聴力を磨くのか?」
今回の読書録は「優れたリーダーは、なぜ傾聴力を磨くのか?」

私はリーダー職ではありませんが、傾聴力には興味があります。
webディレクターとして読んだ中で参考になったポイントをまとめてみます。
「聞く(Hear)」ではなく「聴く(Listen)」
早速ですが「聞く」と「聴く」は違います。
聞く(Hear)とは受け身の姿勢で聞いていること、いわば勝手に耳に入っている状態です。一方で聴く(Listen)は聞き漏らしがないように集中し、積極的な姿勢で聞いている状態です。
人間は相手の話を「聴く」つもりでないと、100聞いたうちの75は捨ててしまうそうです。なのでNHKのアナウンサーは視聴者が"聞く"状態であることを想定して、緊急時以外はニュースを若干ゆっくりと読んでいます。逆に緊急ニュースの時は視聴者が集中している="聴く"状態なので、速度を上げて読んでも大丈夫だと言われています。
リーダーは部下の話を聞くときはHearではなくListenで。これはクライアントやプロジェクトメンバーに対するwebディレクターも同じですね。
「短く、頻度を多く」聞く
聴くが大事とはいえ、忙しいリーダーは部下全員の話を長時間聴いていられません。この時の解決策として有効なのは短く、頻度を多く聞くことです。どうやら短い声がけは非常に効果的だそうです。
なぜなら短い声がけをすることで「この人は何かあればいつでも話を聞いてくれるんだ」と思ってもらえるからです。日頃から細かなコミュニケーションを重ねることで、いざ困った時にもすんなり話ができる。確かにそうだなと思いました。
聞く時間は「長く、頻度を少なく」よりも「短く、頻度を多く」した方がよい。これは上司から部下でなくても、プロジェクトメンバー間においても同様かもしれません。
例えば週1回の定例MTGは開催するとして、それ以外の時間で「大丈夫ですか?」や「何か困ってないですか?」とこまめに声をかけてみる。声をかける意識を持つ。もちろん、相手に嫌がられない程度の頻度で。
これによりプロジェクトメンバー間のコミュニケーションがスムーズになったり、プロジェクト内のアラートを早くキャッチできるかもしれません。
webディレクターは特にやってみるが価値ありそうです。
聞くことを1回で諦めない
上司(聞く側)のよくある悩みとして「相手が特に何も答えてくれない」があります。
「困りごとはありませんか?」→「いや、特にありません」
「いま何を感じていますか?」→「何も感じていません」
先ほど「短く、頻度を多く」聞くことが大事だと書きましたが、時間の短いコミュニケーションにおいてもこういったケースは少なくないでしょう。
こうなると聞く側は心が折れます。そして終いには「部下は何も考えていない」や「聞いてもムダ」といった結論に陥ってしまいます。
こういった時はどうしたらよいのでしょうか。
結論は「聞くことを1回で諦めない」です。
いま「困りごとはありませんか?」と聞いて相手に何もなかったとしても、1週間後にはすごく困っているかもしれません。
もしくは本当は困っていることがあったけど、タイミング的に言えなかった…なんてこともあります。「今度聞かれたら答えよう」と思っているかもしれません。
あとは回数を重ねるごとで聞かれる側のマインドも変わってくるかもしれません。「この人は自分のことを気にかけてくれている」と感じ始めて、だんだんと本音を語ってくれるようになることもあります。
聞くことを1回で諦めない。大事な心がけだなと思いました。
傾聴とは「相手に静かな時間を提供すること」
この本のタイトルにある「傾聴」とは相手に静かな時間を提供することであると著者は定義しています。
上司と部下でいうと部下に対する傾聴とは、部下に静かな時間を提供することです。このように伝えると「沈黙なんて耐えられません」とおっしゃる方も多いようです。気持ちはとてもわかります。私も黙れない人です。
ただ著者はとにかく「黙る」ことを推奨しています。「何秒黙っていればいいんですか?」のアンサーは「相手が話し始めるまで何秒でも」です。傾聴とは上司がその権力を使って黙ることだと考えてもよいくらいだと述べています。
沈黙するとはつまり、聴くです。相手の話に集中することです。これができないと相手は話をしてくれませんし、話をしても本音を伝えてくれません。
そしてこの時に大事なのは非言語です。言葉は発さなくても「なんでも言っていいよ」と笑顔や姿勢で示すことが重要です。逆に非言語を活用できないと傾聴できません。ムスッとする、貧乏ゆすりをする、仰け反った姿勢での沈黙では相手も本音を話せません。
ただ実際に沈黙を貫くことはなかなか困難です。言うは易し、行うは難し。
だからこそ傾聴力のある人は優れたリーダーやwebディレクターになるのかもしれません。
私自身も沈黙できない人間なので、少しずつトライしていこうと思いました。
以上、優れたリーダーは、なぜ傾聴力を磨くのか?の読書録でした。
聞く力に関する書籍は数多あります。それだけ多くの人が抱える悩みなのだと思います。
この本を読む限り、傾聴力を磨くためにはちょっとしたテクニックと意識が必要です。逆をいえばこれらを知っていれば身につく力なのかもしれません。
あとは実践あるのみ。webディレクターとして傾聴力を磨いていきたいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
