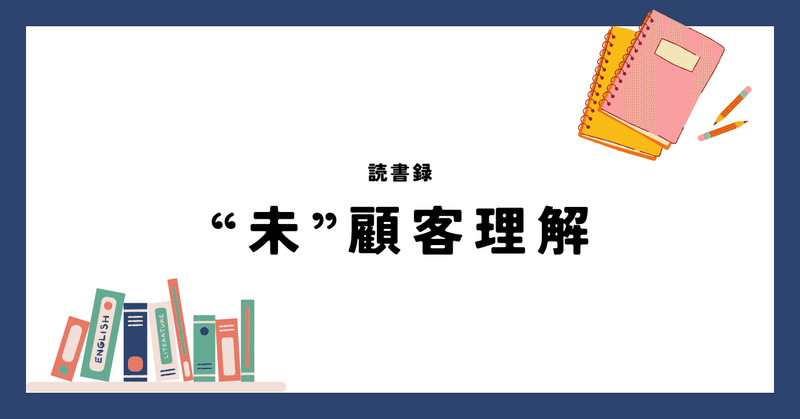
#39 「“未”顧客理解」
今回の読書録は「“未”顧客理解」
サブタイトルの「なぜ、「買ってくれる人=顧客」しか見ないのか?」を見て、そういえばそうだなぁと思いました。
例えばペルソナを考える時は、大体"買ってくれる人"の属性や思考を想像し、整理します。買ってくれない人たち(商品やサービスに興味のない人たち)を念頭に置くことはありませんでした(少なくとも私は)。
そんな私が読んで「なるほど…」と思ったポイントをまとめてみます。
ファンやロイヤル顧客だけを大事にしても事業は成長しない
「ファンベース」「ファンマーケティング」といった自社のファンを大切にし、ファンをベースにして中長期的に売上や価値を上げていく。ファンを大事にしていれば、自然と彼ら彼女らが新しい顧客を連れてきてくれる。そんな考え方を著者は真っ向から否定しています。それは感情的な話ではなく、理論的にもデータでも明らかになっているそうです(少数の例外を除く)。
さまざまな研究により、ブランドの成長に直接影響を及ぼすのは浸透率(顧客数)であることが確認されているようです。ロイヤルティ(ファン化)を高めればシェアが増えるというのも、マーケティングサイエンスの研究者たち曰くそうはならない。
顧客のロイヤルティも大事ですが、それらは浸透率を推進・維持する、つまり補助的な役割なのです。
自社ブランドだけたくさん買って、他のブランドは買わないという夢のような顧客を育てるのは現実的ではありません。その夢を追いかけるよりもブランドにとってウォッチしなければならないのは、時々自社ブランドも買ってくれる競合のヘビーユーザーです。そういったユーザーを増やす、つまりブランド全体の顧客数を増やすことが結果として事業成長につながります。
まとめると多くのブランドの売上の約半分は私たちのブランドに興味のないライトユーザーに支えられていて、事業の成長やシェアを左右するのは、そうした普段意識することのない、顔の見えない未顧客たちです。
真っ向から否定していると書きましたが、ファンを大切にしなくていいという話ではありません。本書のタイトルである"未顧客"にも目を向けましょうという提言です。
結局はいかにヘビーユーザーの離反を防ぐかではなく、離反は起こるものとして、次のヘビーユーザーになってくれる未顧客を獲得し続ける取り組みが求められるのです。
顧客には顧客の合理がある
よく顧客は不合理だと言いますが、そう見えるのはマーケター自身が慣れ親しんだ既知の枠組みの中で顧客の言動を解釈しようとするからであると著者は述べています。
顧客には顧客なりの合理があります。それを理解するためには顧客が置かれた文脈や状況の理解に努め、顧客が見ている世界を見ることが必要です。
顧客理解とは決して客観的な特徴や人となりを整理することではありません。顧客理解とは、特定の状況に置かれた人間がどんな視点で物事を捉えるのか。そこで起こった出来事に対してどんな反応をするか。その文脈に限って合理的な行動とは何か。こうした視座に立ち、顧客を見ることです。
書籍では「チーズケーキを買ってもらうにはどうすればいいか」という事例が取り上げられていました。事例の中でも「どうしたらチーズケーキが売れるか」といきなり答えを出そうとするのではなく、「こうした状況に置かれた人はどういう合理で物事を捉えるだろうか」という視点を持つことが大事と書かれていました。
例えば昼に甘いものを買わない人が、なぜか夜になると甘いものを買う。昼食べるより夜食べる方が太りそう(不合理)ですが、その行動の背景にある「本人にとっての合理性」とは何なのかを考えるわけです。おそらく色々な理由があるはずです。がんばった自分へのご褒美がほしい、大変だった1日に区切りをつけたいなどなど。
あとはその人の合理に沿った形でチーズケーキを訴求する。これが未顧客理解を通じた販促活動です。
マーケターの合理と未顧客の合理は違うものだと認め、どこが違うのかに気づき、言語化、比較し、未顧客にとっての当たり前を学び直す。つまりマーケター自身のアンラーンが必要であると著者は述べています。
私はマーケターではありませんが、このあたりの認識はしておきたいと思いました。
未顧客へのアプローチに必要なこと
ブランドを知らない、興味がない人たちにアプローチするためにはどうすればいいのか。それは未顧客の生活文脈の中にブランドへの入口をできるだけたくさん設けて、ブランドにたどり着く確率を高める必要があります。こうした考え方をCEP(カテゴリーエントリーポイント)というらしいです。
それはただ単に認知を広げればいいという話ではありません。大事なのは生活文脈の中に入り口を設けることです。生活や行動様式とかけ離れたところに入り口を設けても当然自社のブランドにたどり着きません。
いかにCEP(購買のきっかけ)を見つけ出し、ブランドと結びつけるかが本書の大きなテーマです。
なので無関心の人に行動してもらいたいのであれば、「説得して動かす」や「共感で動かす」という姿勢ではなく、既に未顧客の中で確立されている行動や習慣にブランドの方から「寄り添いに行く」という姿勢が必要です。
顧客は変わらないという前提のもと、その変わらない習慣や行動を1つ選んで徹底的にブランドの同質化(顧客の生活に役に立ち、購買を後押しする)を図るわけです。
「顧客を変えよう」とまでは思っていませんが、その前提のもとでどう自分たちを選んでもらうか、行動や習慣に寄り添うかは全然考えられていないなと思いました。自分の購買経験的にも納得感のあるお話でした。
以上、“未”顧客理解の読書録でした。
個人的には目から鱗な1冊でしたね。自分たちが「〇〇である」と思っていることをいい意味で疑うきっかけになりました。
そして読書録を書いていて、これはまとめるのが難しい1冊だなとも思いました。もっともっと読んで内容を咀嚼し、そして実践に移さないといけませんね。
気になった方はぜひ私と一緒に読んで感想を共有しましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
