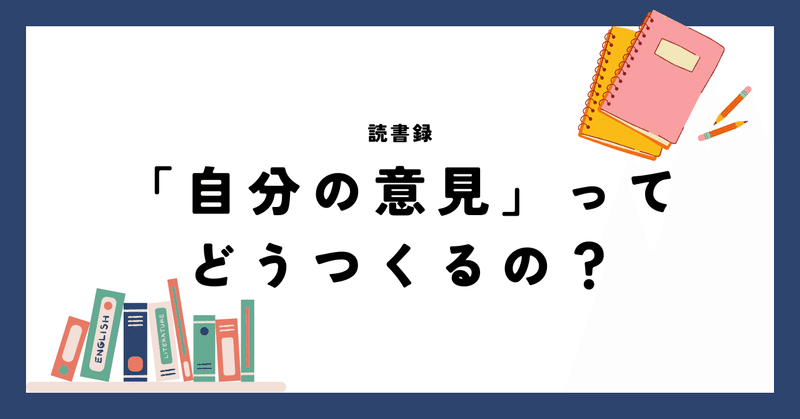
#44 「「自分の意見」ってどうつくるの?」
今回の読書録は「「自分の意見」ってどうつくるの?」

仕事をしていると「自分の意見」を伝えなければならない場面は多々あります。私は意見を伝えるのがあまり得意ではありません。特に事前準備のしていない場面で意見を求められると頭が真っ白になってしまうタイプの人間です。
そんな私が参考になった箇所をまとめてみます。
自分の意見を組み立てる5つのステップ
本書では自分の意見を組み立てるための5つのステップが紹介されています。
問いを立てる
言葉を定義する
物事を疑う
考えを深める
答えを出す
1. 問いを立てる
議論の中ですぐに自分の意見を主張するのは難しいです。そこでまずは問いを立てましょう。問いを立てるとは自分なりに問題を探したり、誰かの発言に質問したりすることです。考えるための目印(とっかかり)ともいえます。
2. 言葉を定義する
自分と相手が用いている言葉が同じでも、お互いの頭の中では違う定義がなされていることは少なくありません。著者は「なんとなく使っている言葉は、なんとなくの思考をつくる」と述べています。双方の認識をズラさないためにも、言葉の使い方を意識するのがこのステップです。
3. 物事を疑う
与えられた条件や前提に対して「本当にそう?」と疑うことステップです。著者は疑う姿勢を身につけることで、より主体的で積極的に議論に参加できるようになったそうです。
4. 考えを深める
このステップでは、あるテーマについて自分の考えを段階的に深めていきます。
5. 答えを出す
最終的な自分の意見(答え)を伝えます。
本書ではそれぞれのステップについて詳細に書かれています。
以降は個人的に学びに感じた部分をご紹介します。
意見がないのではなく、問いがない
よく「特に意見はありません」と言ってしまうことがありますが、果たして本当にそうなのでしょうか。私自身が意見を伝えるのが下手なのでわかるのですが、本当は意見がないのではなく何を言ったらいいのかわからないのです。別の言い方をすると何を考えたらいいのかわからないのです。
よってまずは考えるためのとっかかりが必要であり、それが問いです。
例えば「芸術は美しくなければならないか?」と問われたらどうでしょう。私なら何を言ったらいいのかわからず、黙ってしまいそうです。こういう時はまず問いを立てます。
「ここでいう"芸術"とはなにか?」
「"美しい"とはどういうことか?」
「美しくない芸術は存在しないのか?」
このように問いを立てていくことで、自分が意見を伝えるためにわかっていないことや明らかにしなければならないことが見えてくるはずです。
私のように意見を求められて頭が真っ白になるタイプの人は、まず問いを立てることからスタートするとよさそうです。
言葉を正しくチョイスする
自分の考えを相手にまっすぐ伝えたいなら、言葉を正しくチョイスすることを心がけたいです。そうすることでコミュニケーションのズレを防ぐことができます。
本書ではパートナーから「夕飯はテキトーでいいよ」と言われたので卵かけご飯を出したら「テキトーすぎだろ!」と怒られた夫婦ゲンカの例が紹介されていました。双方の「テキトー」のとらえ方が異なっているとこのような事故が起きます。
少し話は逸れますが、webディレクターも言葉のチョイスは大事だなと思います。
例えば仕事を依頼するとき「来週までにお願いします」では不十分です。こちらが「木曜の午前くらいまでにはできるだろう」と想像していても、相手は「来週までということは金曜日の終業まででいいんだな」と捉えているかもしれません。この場合は「来週〇月〇日木曜日の午前中までにお願いします」といった言葉選びをしなければなりません。
話を戻すと自分の意見をキチンと伝えるためという意味でも、相手の言葉のチョイスにも敏感になる必要があります。「テキトーでいいよ」と言われたら「テキトーってどのレベル?」と聞かなければなりません。
自分の意見を伝えたのに全く的外れだった…という時は言葉のチョイスが誤っている可能性があります。気をつけたいですね。
疑うとは一時停止すること
求められた意見に対して与えられた条件や前提を「本当にそう?」と疑うことが重要であると書籍全体を通じて述べられています。
哲学の世界において「疑う」とは、一時停止の状態を意味するそうです。何を停止するかというと、答えを出すことや判断することです。
疑うことは議論を中断させたり混乱させたりする行為だと思われるかもしれませんが、決してそうではないと著者は述べています。素朴な疑問から誰も気づけなかった視点が見つかることもあります。
書籍で紹介されていた疑うときのテクニックは以下の3つです。この視点を意識することで、自分の意見がうまくつくれていないときでも議論に参加することができます。
正当性があるか疑う(例:それって本当に正しい?)
他のアプローチがないか疑う(例:これが最善の解決策なのか?)
あえて強調して疑う(例:〇〇であれば必ず△△であると言えるか?)
日本人は場の空気を乱すことを恐れがちなので(私もそう)こういった疑問を投げかけるのは勇気がいることだと思います。それでも自分の意見がうまくつくれないときは、疑うことから始めてみてもいいかもしれません。そこから思考や議論がスタートできるかもしれないので。
「私は〜思います」を捨てる
著者は意見を伝えるとき、断言することを心がけてほしいと述べています。
それは自分の意見を決めつけるためではありません。自分が考えて出した意見に自信を持つためです。
「私は〜思います」は自信がなく、煮え切らない感じがしてしまいます。
あとそもそも誰かの発言は全部「その人が思っていること」です。なのでわざわざ「〜思います」と伝えなくていいわけです。
意見を伝えるときは、あくまでもその時点での自分なりの思考の結果だと割り切って、大胆に言い切るようにする。自分の答えに責任を持って堂々と主張する。
そんな伝え方ができると自分の意見をつくることに自信が持てて、それ自体もつくりやすくなるのかもしれませんね。
以上、「自分の意見」ってどうつくるの?の読書録でした。
冒頭にも書いたように、私は自分の意見を伝えることが得意ではありません。それは「何を言えばいいのかわからない」「何を考えたらいいのかわからない」状態に陥っていたことが本書を読んでわかりました。
まずはとっかかりとなる問いを立て、言葉を定義し、疑い、そして堂々と意見を伝える。この一連のプロセスを常に意識し、自分の意見を伝えられるようにしていきたいと思いました。
書籍内ではそれぞれのプロセスについて、より詳細に解説されています。興味のある方はぜひご一読くださいませ。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
