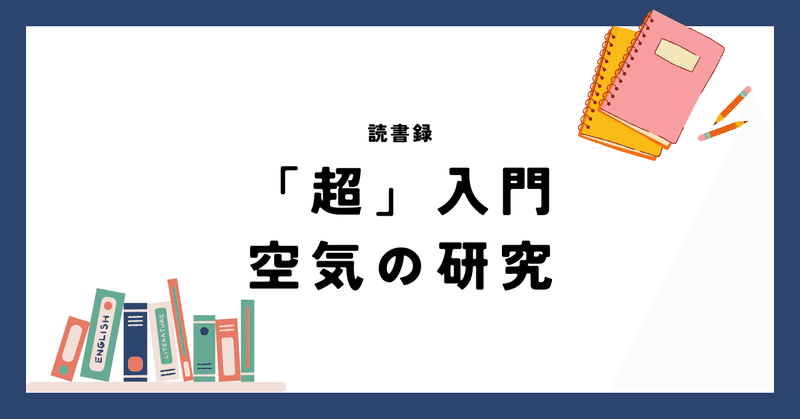
#36 「「超」入門 空気の研究」
今回の読書録は「「超」入門 空気の研究」
X(Twitter)でオススメされていた1冊。
仕事に活かそうというモチベーションではなく、シンプルに「空気を読む」の"空気"って改めてナニモノなんだろう?と気になって買いました。
実際に読んでみると非常におもしろかったです。結果的に仕事にも活かせそうな内容でしたので、そのあたりを中心にまとめてみます。
空気とは"ある種の前提"である
まずはそもそも論から。
空気を読むの"空気"とはある種の前提であると著者は述べています。
空気を読む→前提を読む
空気をつくる→前提をつくる
空気に支配される→前提に支配される
「〇〇の時は××するよね?」「みんな〇〇しているからアナタも〇〇するのが普通」「〇〇は間違ったことだから××するのが当たり前」
空気(前提)とは暗黙の了解のようなものです。
空気の最大の弊害は"不都合な現実を隠蔽する"こと
空気の最大の弊害は意図的に前提を押し付けて、都合よく現実の一部を隠すことです。前提と現実にギャップがあっても、現実を無視させるわけです。
前提とは違う可能性を考えさせない
合理性や現実を無視させる
集団の問題解決力を破壊する
このように全員がおかしいと思っていても、おかしいと言えない雰囲気を作る。少しでも前提から逸れるようならば、嫌がらせや攻撃といった弾圧を受ける。
例えば、戦艦大和は撃沈されるとわかっていたのに「出撃せざるを得ない」前提がありました。上席たちはその前提(空気)で部下を支配し、結果的に全員が撃沈されるのであれば出撃しないという正しい思考プロセスを歩めなかったのです。
改めて"空気"って怖いなと思いました。自分がこうした雰囲気を作っていないか気をつけたいものです。
空気の固定化は集団の問題解決力を奪う
空気の固定化とは、例えば「この病気の治療法はAである」という判断に固執してしまうことです。
仮にAに対する反証する事実や症例、新たな患者が生まれても、多くの人はAという前提を変えられません。現実が誤りを指摘しても訂正できないのです。
これは仕事にも通ずると思います。例えばwebサイトの制作フローも「このプロセスが正しい」と固執すると、もっといいやり方や可能性を探そうとしなくなる、場合によっては新たな提案を排除しかねません。新しいツールが登場してもトライできず、今までの方法論にしがみつく。
そうならないためにも、常に自分たちの判断や手法を見直す意識が大切です。空気を固定化させない流動性やしなやかさを持ち続けたいですね。
ヒヨコにお湯を飲ませない
空気の研究の第1章では飼っているヒヨコにお湯を飲ませてすべて殺してしまった老人の話が紹介されています。「寒いときはお湯を飲むと温まって体にいい」という人間側の話を、違う生き物のヒヨコに当てはめたことで起こった悲劇です。
これが示唆しているのは、自分が正しいと信じることが相手にとっては間違っている場合があるということです。自分が正しいと思うことが相手にも正しいと信じる。相手を自分と同一視してしまう。自分の心と外部(現実)を区別できていない状態ともいえます。
日々のコミュニケーションにおいてもこういった悲劇は起きかねません。ヒヨコにお湯を飲ませない人であらねば。
〇〇しか知らないことは、〇〇をまったく知らないことである
「〇〇しか知らないことは、〇〇をまったく知らないことである」というのは例えば以下のようなものです。
自社しか知らないことは、自社をまったく知らないことである
社内しか知らないことは、社内をまったく知らないことである
国内市場しか知らないことは、国内市場をまったく知らないことである
これも非常に気をつけなければ、と思いました。
自社以外を知らない=他社との比較検討ができず、客観性を持って己を正しく把握できません。必要なのは他社と比較しその共通点や相違点を知ることで、相対的に自社を理解することです。
webサイト制作における戦略策定でも大事なポイントだと思いました。この理論でいうとクライアントのことしか知らない状態では、クライアントを本当の意味で理解できないわけです。クライアントと同業他社を比べることで、相対的にクライアントの強みや課題が見える。
余談ですが私は最近、社外の人と会ったり交流したりするようにしています。その理由の1つが相手と私との違いを知ることで、自分のことをより深く知れるからです。また同業者の業務内容を聞くことで、自社の良いところや不足しているところに気づくこともあります。
積極的に自分たち以外を知りにいく。大事です。
以上、「超」入門 空気の研究の読書録でした。
日本人は"空気"に敏感であると聞きます。その真偽はともかく、空気がもたらすデメリットは非常に大きいことがよくわかりました。
まわりを空気で脅かさない、まわりから脅かされない人でいられたらと思いました。
他にも"空気"に関する事例や示唆がたくさん紹介されていました。気になった方はぜひお買い求めください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
