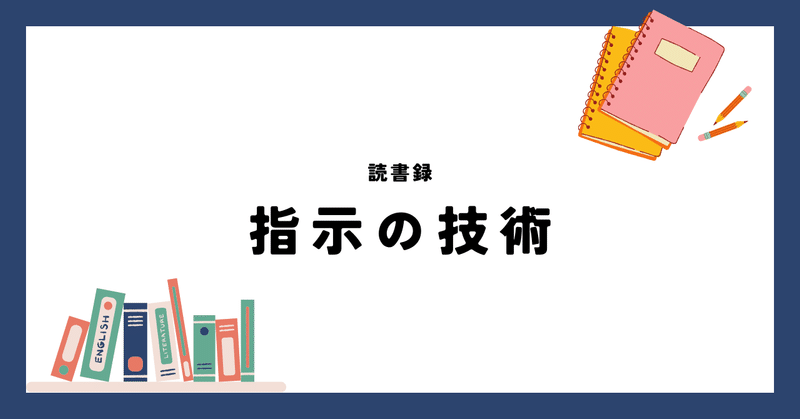
#32 「指示の技術」
今回の読書録は「指示の技術」
著者の土居さんは公立小学校の先生です。タイトルにもあるように、子ども(生徒)の聞く力や行動する力を育てるための指示に関する書籍です。
なぜ私がこの書籍を紹介したいかというと、webディレクターの仕事にも活かせるところがたくさんあったからです。対象が子どもであれ大人であれ、他者に何かをお願いする上で大事にしなければならないポイントは同じですよね。
というわけでこの読書録では、webディレクターの仕事にも応用できそうな部分を中心にご紹介していきます。
指示は"端的に、具体的に"
早速ですが技術のお話。
指示は「端的に、具体的に」出すことが重要です。
ここでいう「端的に」とは、短くはっきりと伝える"言い方"のことで、「具体的に」とは量や数字といった"内容"のことです。
どちらも備わって初めてわかりやすい指示になると著者は述べています。
この逆は「あいまいな指示」です。
例えば…
上のほうを注意してください
どこでもいいので書いておいてください
これくらい余白をあけてください
上のほう?どこでも?これくらい?
何をどの程度行えばいいのかわからず、言われた側は混乱してしまいます。
これはwebサイト制作の現場でもよくあります。ディレクターの皆さん、デザイナーさんに「ここのフォントサイズをもう少し小さくしてください」と指示したことありませんか?私はあります。
「もう少し小さく」ではなく「2px小さく」と数字を示す。誰がどう聞いてもそうとしか捉えられないように伝えましょう(自戒)。
あとは言い方も大事です。
「えーっと…うーん…」「どうかなぁ…そうだなぁ…」「いやぁ…でも….」のように相手を不安にさせるような言い方はしない。バシッと言い切る。
当たり前のように聞こえますが、忙しくなったり気持ちに余裕がなかったりするとあいまいな指示が出されがちです。
言い切ることと客観的な基準を示すことは常に意識していきたいですね。
指示は「予告」と「確認」が大切
指示において予告と確認は非常に大切です。
予告とは「今からポイントを3つ話します」といった話し手が何についてどれくらいの量を話すのかを伝えて聞き手に聞く姿勢を作ることです。
予習とも言えますね。
確認とは「1つ目のポイントはなんでしたか?」といった伝えた内容の復習です。
ここから先は書籍の中で触れられていませんでしたが、私は指示において予告と確認が大事な理由は、人は長い指示を聞くのがしんどいからだと思います。
webディレクターは1回の会議で誰かに長い指示(複数の指示)を出すことがよくあります。
「AとBとCと…あとDもお願いします」
指示が長いと言われた側は「結局何をしないといけないんだっけ?」と困惑してしまいます。場合によっては途中から聞いていないかもしれません。
こうならないようにするために、まずは聞き手に構えを作ってあげた方がいいでしょう。野球でいうと今からピッチャー(話者)が投げるボールをキャッチするために、キャッチャー(聞き手)がグローブを顔の前にセットするイメージ。
「よし、こい!」と聞き手が心の準備を作れると安心です。
あとは指示した内容は最後にまとめるのも効果的です。
一度の会議の中で1つ目の指示と4つ目の指示を伝えた時間に差があることは少なくありません。最後に「今回お願いしたいことをまとめると、まず1つ目は…」と復習の時間を作れると齟齬やモレもなくなるでしょう。
予告と確認を意識したコミュニケーション。webディレクターとして身につけていきたいと思いました。
自分の指示を疑う
マインドのお話です。
指示に限ったことではありませんが、常に自分の指示を疑うクセはつけたほうがよさそうです。
現状問題ないからといってそれが最善とは限りません。もしかしたら相手はもっと上のレベルで動けるかもしれないのに、過剰に親切すぎる指示をしていることもあります。
学校の例でいうと、子どもは学校へ来たら先生から指示のシャワーを浴び続けています。その指示が低レベルで一方的なものであれば、多くの子どもは受動的になり、自分で物事を考えて行動するようにはならないでしょう。
少し大袈裟かもしれませんが、webディレクターからの低俗な指示は成果物のクオリティをも落としかねません。
「自分の指示によって、まわりの人のレベルを下げていないか?」は心がけていたいものですね。
指示に問いかけを入れる
「〜してください」「〜しましょう」と、指示は話し手から聞き手の一方通行になりがちです。
子どもの成長が目的であれば、子どもに考える余地を与える「問いかけ」を指示に入れることで、一方的なものではないものへと変化させましょう。
例えば避難訓練後、「次はもっと素早く整列するようにしましょう」と伝えたいとします。これをそのまま伝えるのではなく「自分の避難訓練は何点でしたか?3点満点でつけてください。2点の人はどうして1点足りないのですか?」と問いかけることで、子どもたちは自ら反省点(例:外でおしゃべりしてしまった)を話し始めます。
子ども自身の口から言わせたほうが、「次はそうならないようにしよう」と決意させることができ、自立へと近づけます。
というのが筆者からのアドバイスです。
これは仕事上でのコミュニケーションでも役に立つと思いました。
基本的に人は「自分で決定したこと」でないと本気になれません。
他人からの言わされ仕事にモチベーションを抱くことは難しいです。
お仕事を依頼したい時は相手にその必要性を腹落ちしてもらい、自らの意思で行動してもらえるのが理想です。もちろん、現実は難しいですが。
ただ少なくとも、相手の口から「私が〜しますね」と言ってもらえるようなコミュニケーションは工夫の余地があると思います。一方的な指示ではなく双方向のやり取りにするためにも、相手に問いかけることは大事ですね。
以上、指示の技術の読書録でした。
指示にもさまざまな考え方やコツがあることを学びました。
たかが指示、されど指示。
webディレクターとしても、2歳の娘を育てるパパとしても、これからいい指示が出せるようになりたいなと思いました。
他にもたくさんの技術やコツが紹介されているので、気になった方はぜひお買い求めください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
