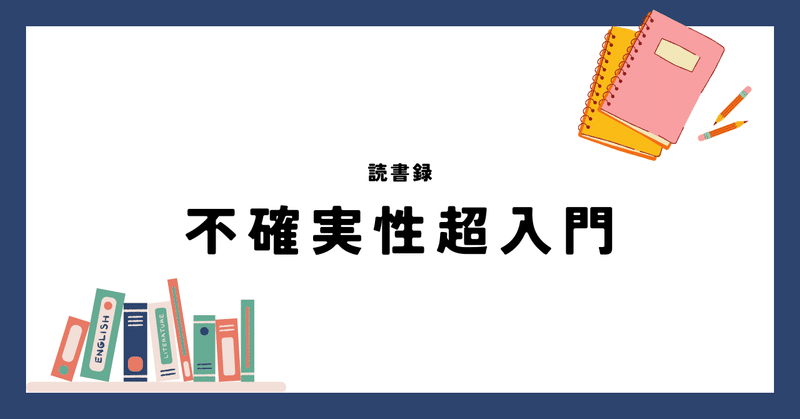
#40 「不確実性超入門」
今回の読書録は「不確実性超入門」
webディレクターとしてプロジェクトの進行管理と向き合い続けて感じることがあります。それは不確実性との付き合い方の重要性です。
育った環境も価値観もリテラシーも立場も異なる人間が集まり、ウェブサイトを作ったり活用したりする。そのためのワークフローや仕組みをどんなに整えようとも、事前準備を怠らずに行おうとも、プロジェクトは思わぬアクシデントに遭遇します。
では私たちはどのように不確実性と付き合っていくべきなのか、そのためのヒントをまとめてみようと思います。
予測できないことを予測で対処するな
著者曰く、予測できないことに予測で対処しようという考え方は間違えています。
この本では金融投資の例がいくつか登場するのですが、どんなにカリスマ的な投資家や金融投資の専門家でも予測は当たりもしますし外れもします。めちゃくちゃ当たり前です。
しかしいざ実践となると、人は予測が当たらないことを問題視します。投資とは不確実なものであるとわかっていながらも、「なぜこんなに重要なデキゴトを予測できなかったんだ」と憤慨する人はいます。私も証券会社に勤めていた頃、同じようなことを実際に言われた経験があります。
冒頭にプロジェクトは不確実性との向き合い方が大事だと書きました。予測できないことに対して予測で対処しようとしない。このスタンスを忘れてはいけないと思いました。
ただこれは「予測をするな」という話ではありません。予測は大事です。次に何が起こるかを予測しないと打ち手が講じられません。
重要なのは予測で対処しないことです。ではどうすればよいのでしょうか。
重要なのは再起不能になるほどの致命傷を負わないこと
不確実な世界ではうまくいくこともあればうまくいかないこともあります。この世界を生きる上で重要なのは、うまくいかないときに再起不能になるほどの致命的な損失を被って、次にうまくいくかもしれない機会を失わないことだと著者は述べています。要は死なないことです。
ここにリスク管理の本質があります。リスク管理とはリスクを起こさないことではありません。リスクが起きても致命傷を負わないように準備することです。
投資家でいえば投資で大きな損失を被って全財産を失わないことです。全財産を失えば再チャレンジできません。
企業でいえば大規模な設備投資に失敗して倒産しないことです。倒産してしまったら再チャレンジできません。
webディレクターでいえばなんでしょうか。例えばプロジェクト終盤で経営陣からちゃぶ台返しにあって、デザインを1から作り直しになり、どうがんばっても公開日に間に合わない…こんな事態は避けなければなりません。
どの段階で何を経営陣から握っておけば公開日に間に合うのか。ここのコントロールこそがリスク管理です。デザインをひっくり返らないようにすることではありません。
これに通ずる話はX(Twitter)界隈で有名な「反脆弱性」という本でも出てきました。社内のエース社員が急に退職する。受注目前であった大型案件が社長の鶴の一声で失注する。こうした想定外のことが起きたときのためにも、組織にはそれらを対処できるだけの"しなやかさ"を持つことが大事であると紹介されていました。
リスク管理について改めて自分の中で深く腹落ちできた気がします。肝に銘じたい。
自己正当化の欲求に囚われない
人はいったん何かを判断したり行動したりすると、そうしていなかった場合には決して抱かなかったはずの理屈に囚われてしまいがちです。
例えば株式を買うとき、「ちょっと上がりそうだな」という軽い気持ちで買うことはあります。
ただ一度その株が下がり始めると、途端に人は自己正当化のスイッチが入ります。「この株は本当は良い株だ」「今は下がっていても将来は大化けするはずだ」と新しい理屈を後付けしてしまうのです。これは買った当初は抱くことがなかった理屈です。
そしてこの理屈に囚われ続けると、下がり続ける株式をいつまで経っても手放せず、損失がどんどん拡大していく様子を指を咥えて見るしかない羽目になりかねません。
自己正当化は決して悪い面ばかりではありません。この欲求があるからこそ多少の紆余曲折や障害にもめげずに、自分は間違っていないと信じ、前に向かって突き進めることもあります。結果的には素晴らしい道が切り開かれることもあるでしょう。
しかし上記の例のように自己正当化の欲求によって、人は客観性や合理性を失うこともあります。
ここのバランス感覚は気をつけなければなりませんね。
小さな失敗を認める勇気が大切
今まで見てきたように、この世界には100%確実なことはありません。将来におけるすべてのことは確率的に捉える必要があります。不確実性に対処する原則は一回一回の結果ではなく、長い目で見たトータルの結果でその成否を判断することです。別の言い方をすれば、大きな失敗を避けるためには、小さな失敗を許容することが大切です。
多くの投資のプロがひとつの投資判断がうまくいかなかったときは損失を早めに確定させて、傷口を広げないようにすることが鉄則だと説いています。大きな失敗をしないためにも小さな失敗を許容し、長い投資生活のトータルでは負けないようにしているのです。
ただそのためには一度「自分の過ちを認める」必要があります。ここが難しいところです。一回一回の勝ち負けにこだわったり負けを認められないプライドが邪魔したりするため、アマチュア投資家はこの原則を守れないのです。
先ほども書いたように不確実性の世界では、致命傷を負わないことが大事です。死にさえしなければ、何度でもトライできます。大きなチャンスが巡ってくるのを待つこともできます。
そのためには小さな失敗を認める勇気が大切です。
なかなか難しいことですが、周りを守るためにもそんな勇気を持てる人でありたいなと思いました。
以上、不確実性超入門の読書録でした。
プロジェクトの進行管理をする立場の人間として、不確実性とは上手に付き合っていきたいなと改めて思いました。
致命傷を負うような事態にはせず、小さな失敗を許容しながら、プロジェクトを前に進められるディレクターでありたいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
X(Twitter)がんばってます。ぜひ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
