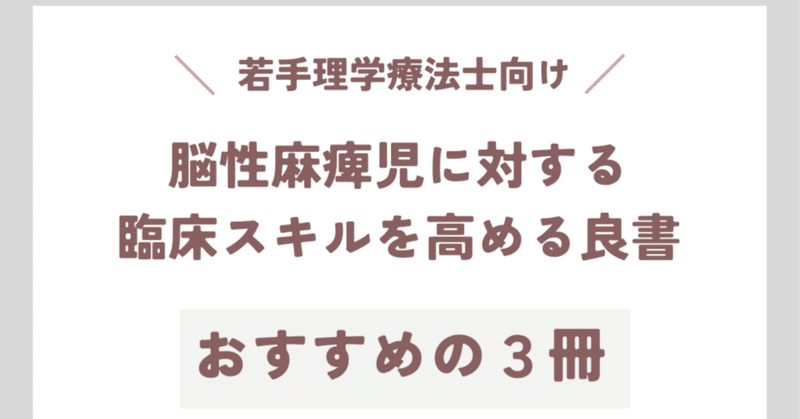
脳性麻痺児に対する臨床スキルを高める良書3選
脳性麻痺児の治療法をより良いものにするために、知識のアップデートが不可欠です。厳選した3冊の専門書を通じて、クリニカルリーズニングと、姿勢ケア、運動スキルの発達促進の方法を深く理解し、あなたの臨床スキルを引き上げましょう。これらの知識を身につけることで、子ども一人ひとりにマッチした効果的な介入が可能になります。
1. 『脳性麻痺のクリニカルリーズニングアプローチ』(2011年)
著者:Karen J. Dodd, Christine Imms, Nicholas F. Taylor、監訳:上杉雅之
1.1『脳性麻痺のクリニカルリーズニングアプローチ』の内容
『脳性麻痺のクリニカルリーズニングアプローチ』は、脳性麻痺児の理学療法にクリニカルリーズニングを適用する方法を解説した専門書です。
本書では、個々の患者に合わせた治療計画を立てることと、患者本人と家族が積極的に関与することを重視しています。
実際のケーススタディを通じて、クリニカルリーズニングを具体的にどのように適用するかを示しています。
本書で解説されるクリニカルリーズニングのステップは以下の8つです。
① 情報収集 - 患者の状況について詳細な情報を集める。
② 問題点の確認と優先順位の決定 - 患者と家族のニーズに基づいて問題点を特定し、優先順位を設定する。
③ 関連理論の確認 - 選択された介入に必要な理論的背景を確認する。
④ 心身機能・身体構造、活動、参加の評価 - 患者の機能状態を評価し、介入の効果を判断する基準とする。
⑤ 関連する環境因子と個人因子の確認 - 患者の生活環境や個人的な特性を理解し、介入にどのように影響するかを検討する。
⑥ 介入計画の話し合い - 患者や家族と共に計画を立て、同意を得る。
⑦ 計画の実施 - 決定された介入を実行し、進行状況を管理する。
⑧ 結果の評価 - 介入の効果を評価し、必要に応じて計画を調整する。
1.2『脳性麻痺のクリニカルリーズニングアプローチ』から得られること
・何となくや思い付きの理学療法から、根拠のある理学療法を実践できる。
・問題点の抜け漏れや優先順位の判断ミスがなくなり、本当に意味のある介入が行える。
・心身機能と身体構造に偏りがちな思考が、生活機能全体を考慮した幅広い思考へと変化する。
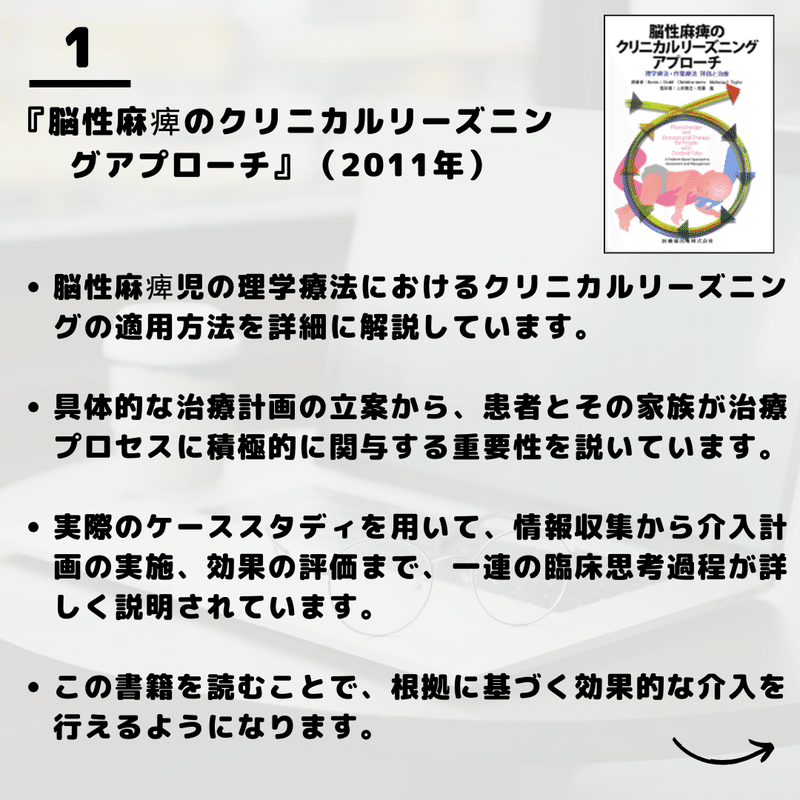
2. 『脳性まひ児の24時間姿勢ケア』(2006年)
著者:Elizabeth Mary Green, T.E. Pountney, C. M. Mulcahy, S. Clarke、監訳:今川忠男
2.1 『脳性まひ児の24時間姿勢ケア』の内容
『脳性まひ児の24時間姿勢ケア』は、子どもたちの姿勢制御の発達を詳細に評価し、その情報を基に理学療法や日常で使用する補装具の選択を最適化する方法に焦点を当てた専門書です。
この本は、特に脳性まひ児の24時間姿勢ケアに必要な理論の解説と、具体的な評価方法の解説、特に生体力学に基づく運動分析を通じて子どもたちの姿勢能力を段階的に評価する方法を紹介しています。
本書で解説される評価は、Chailey姿勢能力発達レベルとして知られ、以下のような特徴があります:
① 背臥位と腹臥位、床上座位、椅子座位、立位といった基本的な肢位における姿勢制御を評価する。
② 姿勢能力の評価は、支持基底面と重心の位置関係、頭部と体幹および四肢のアライメント、頭部や四肢を体幹から分離して動かす能力を中心に行われる。
2.2 『脳性まひ児の24時間姿勢ケア』から得られること
・粗大運動の発達の評価が、ふわっとした感覚的な評価から、わずかな変化さえも正確に読み取れる明確な評価に変わる。
・様々な粗大運動の評価に応用できる姿勢制御と運動学習の要点を理解できる。
・明確な根拠を持って座位保持装置や車椅子の選定と調整を行える。

3. 『親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック』(2015年)
著者:Sieglinde Martin、監訳:山川友康、上杉雅之
3.1『親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック』の内容
『親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック』は、脳性麻痺の子供たちの運動スキルの発達に焦点を当てた本です。
本書では脳性まひ児の発達を支援するため理論と、発達を促進するための具体的な練習や環境設定の方法を解説しています。
本書の主な内容は以下の通りです:
① 粗大運動の発達 - 粗大運動時の筋活動とその発達プロセスを解説し、子どもがどのようにして運動スキルを獲得していくかを示しています。
② 運動学習の促進 - 神経可塑性や学習の促進に影響を与える要因について説明し、効果的な練習方法を解説します。
③ 脳性まひ児の運動と知覚の障害 - 運動制御の異常や感覚認知の問題など、脳性まひに関連する障害について詳しく述べます。
④ 理学療法の方法 - 脳性まひ児を対象とした理学療法の具体的な治療方法を解説します。
3.2 『親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック』から得られること
・子どもの将来の運動発達が具体的にイメージできるようになる。
・単調になりがちな動作練習の内容が多彩になる。
・運動発達に関する家族へのアドバイスがわかりやすく明確になる。

まとめ
脳性麻痺児の理学療法に役立つ3冊の専門書について紹介しました。
『脳性麻痺のクリニカルリーズニングアプローチ』(2011年): この書籍は、脳性麻痺児の理学療法におけるクリニカルリーズニングの適用方法を詳細に解説しています。具体的な治療計画の立案から、患者とその家族が治療プロセスに積極的に関与する重要性を説いています。また、実際のケーススタディを用いて、情報収集から介入計画の実施、効果の評価まで、一連の臨床思考過程が詳しく説明されています。この書籍を読むことで、理学療法士は根拠に基づく効果的な介入を行えるようになります。
『脳性まひ児の24時間姿勢ケア』(2006年): 姿勢制御の発達を詳細に評価し、その情報を基に理学療法や日常で使用する補装具の選択の質を高める方法に焦点を当てた専門書です。この書籍を読むことで、生体力学に基づく運動分析を用いて、多様な粗大運動の発達を明確に評価できるようになります。さらに、座位保持装置や車椅子の選定と調整を明確な根拠に基づいて行えるようになります。
『親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック』(2015年): 脳性麻痺児の運動スキルの発達と学習に焦点を当てた専門書です。運動スキルの発達を促進する練習や環境設定の方法も提供し、日常生活に取り入れやすい実践的な情報が満載です。この書籍を読むことで、運動発達を具体的にイメージできるようになります。また、単調になりがちな動作練習に効果的に様々な変化を付けられるようになることに加えて、家族へわかりやすくアドバイスできるようになります。
これらの書籍を通じて、小児理学療法士として脳性麻痺の子どもたちを適切に支援する方法が学べます。ぜひ御一読ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
