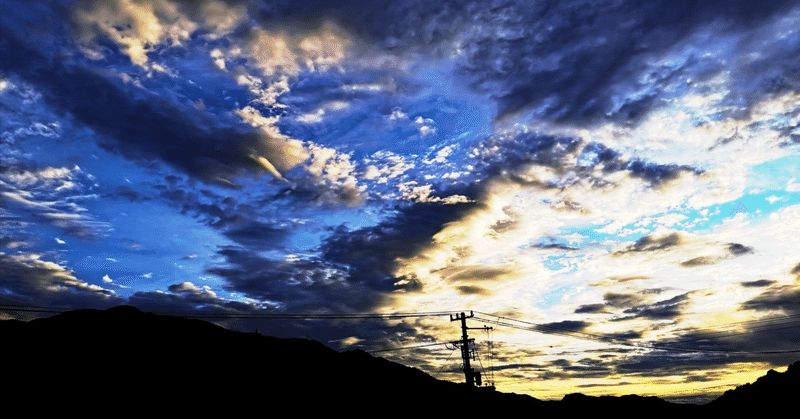
ボランティア行為にはある程度の覚悟が必要かもしれない(2024/02/27)
一昨日・昨日と、二日連続で「災害ボランティア」、「視覚障害者の誘導」といった、ちょっといい人ぶった投稿が続きました。
これらの投稿後に、改めて思ったことがありましたので、書いてみたいと思います。
結論からいうと、タイトル通り、「ある程度の覚悟が必要」と思ったということです。
■災害ボランティアについて
・「いろんな人」が来る
上記リンク先の記事でも触れていますが、ボランティアには実に様々な人が集まってくるようです。独特の価値観や強い自己主張をされる方だったり、コミュニケーションの取り方が難しい方もいらっしゃると思います。共同作業をする機会は少ないかもしれませんが、そういった方と関わることがあった場合に、自分の精神の防衛をできるメンタルコントロールスキルはある程度必要なのかもしれません。
・決して見返りを求めてはいけない
これは、「ボランティアなんだから当たり前だろう」と思う方もいるかもしれません。しかし現実的に考えた場合なのですが、例えば遠方から参加する場合、現地までの移動にかかる交通費・時間や、前泊する場合は宿泊費など、「支援活動」以外の部分で自分のリソースをかなり割くこととなると思います。
実際のところは、マスメディアで取り上げられるような「被災者の被災家屋の片づけのお手伝い」や「炊き出し」、その後に必ずセットで映し出される被災者の方の「ありがたいです」というコメント…という、ある意味(不適切な表現かもしれませんが)輝かしい支援活動だけではなく、被災者の直接目の触れないところで黙々と作業をする活動場所だってたくさんあると思います。
そういった場合、そこにいる人は基本的に皆さん支援者側の立場なので、誰からも労いの言葉をかけられることもなく、その日の作業が終われば解散…という流れなのかなと思います。これを自分に当てはめて考えた場合、正直しんどいかもしれないと思ってしまいました。これはおそらく、自分の無意識下で、「労いの言葉を掛けられるという見返り」を期待してしまっていると思いました。
しかし、私なんぞとは違い、「被災地のために少しでも役立てるなら」との思いで、聖人君子のような心構えで支援に向かわれる方もたくさんいらっしゃるのは承知しています。
良くも悪くも、マスコミで取り上げられる部分はほんの一部です。陽の当たらない場所でも、黙々と作業をして帰るだけという現実をもってしても、行く覚悟はあるのか。また、逆に、失意の底であったり、余裕がなくなっている被災者の方から非難をされないような立ち居振る舞いができるかどうか。
余談ですが、著名人の方が炊き出しを行っている様子がマスコミで報道されるのは、私は悪いことだとは思っていません。著名人の方だからこそ、人目が集まるところで活動していただいたほうが、励みになる方は(全員ではないかもしれないけど)多いと思いますし、支援活動が広まる広報的な役割も担っていると考えています。
■障害者の方への誘導について
災害ボランティアの件とは話は変わります。
視覚障害者の方へ声を掛けさせていただいた記事についてです。
こちらの記事では、視覚障害の方が道に迷われている様子だったので、「何かお手伝いしましょうか?」と、お声がけしたときのエピソードを書いています。
声をかけるとき、そのまま黙っていたら、壁にぶつかりそうだった(実際には白杖があるのでぶつかることはなかったとは思いますが)ので、そういった意味でも声をかけました。少しだけなら時間があったので、例えばすぐ近くの目的地までだったら、ご案内しようという想定で声をかけました。
しかし、実際には、「そもそも目的のお店の正確な名前・場所を本人が把握していなかった」というケースでした。明確に店名や住所などが分かっている場所でしたらご案内も可能でしたが、そもそも目的地の所在が不明瞭という事態だったため、私はそれを調べるまでの時間の余裕はなかった状態でした。
このとき、声をかける前は、自分の中で勝手に「目の前のホテルの入り口を探しているのでないか」と想定していたため、そのホテルの入り口を探しているなら案内しようと思っていました。そして、お声がけしたら実際はお困りごとは違ったうえ、一度声をかけたら、「目的を達成できるまで途中で放棄できない」と思ってしまいました。
*****
過去に、とても急いでいたとき、緩やかな上り坂を手動の車椅子で登っていらっしゃる方を見かけたので、とても迷いましたが、声をかけました。「では、あそこまでお願いします」と言われ、上り坂の頂点までお手伝いしました。短い距離でした。もし、その先までと言われたら、私も困ったと思います。
*****
今まで、街中で障害をお持ちの方が困っていらっしゃったとき、「声を掛けずにスルーは悪いこと。声を掛けるのが良いこと。」と、二択で決めつけてしまっていました。しかし、一度お声がけしたら、ある程度のお手伝いの責務は生じますし、その時点の自分の時間の余裕の具合によって、可能なお手伝いと、難しいお手伝いがあるかもしれません。ですので、声を掛けない人を一概に責めるわけにいかないですし、今後、自分も余裕のあるときしか声を掛けないほうがお互いのために良いのかもしれないとも思いました。
もしくは、お声がけした場合に、自分の可能なお手伝いだったらお請けして、そうではない場合は難しいと伝えるか、代替案を提示するか。
ここまで書いてきて思い出しましたが、「災害ボランティア活動の注意事項」の文書に、難しいお手伝いを依頼された場合は断りましょうって書いてあったと記憶しています。
■結局は承認欲求?
一通り、言いたいことだけただひたすら書いてしまいましたが、自分の無意識の中で「手伝ってあげる私えらい」といったような自己肯定感・承認欲求的な考えが潜んでいることが否定できないと思ってしまいました。各種ボランティアの手引書・指南書では、「(~してあげる)という考え方は改めましょう」、「(支援させていただく)の姿勢で臨みましょう」と記載されているのを何度か見かけました。
まさしくその通りです。なので、災害ボランティアも、障害のある方へのお声がけも、ある程度の覚悟と気概がなければ出来ないことだと思うので、誰でもできることではありませんし、できない(しない)人を責めてもいけないと思いました。これは、実際に行動にしてみないと気付けないことでした。(災害ボランティアは行動したわけではないですが…)
でもでも、最後にやっぱり思うのは、そういった支援活動を行ったあとに、自分で自分を労ったり、そのことで自己肯定感を少し高めたりすることは、内省的には多少はあっても良いのではないかとも思ったりしています。
よろしければサポートいただけると非常に励みになります! いただいたサポートは今後の執筆活動のために大切に使わせていただきます。
