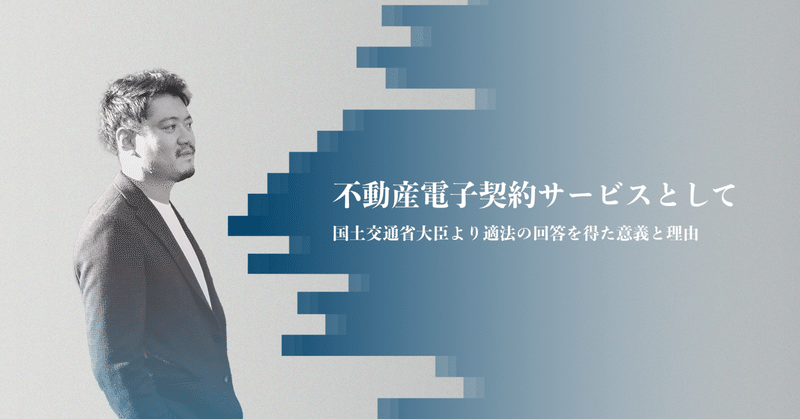
不動産電子契約サービスとして国土交通大臣より適法の回答を得た意義と理由
こんにちは。不動産電子契約サービス『PICKFORM』を運営する株式会社PICK代表の普家です。

この度、グレーゾーン解消制度を利用して、弊社サービスの「PICKFORM」が不動産電子契約サービスとして初めて国土交通大臣より、宅建業法を遵守したサービスであるとの正式な回答をいただきました。(2022年11月25現在)
詳細はこちらのリンクをご覧ください。
(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_fr_000015.html)
この回答をいただくまでに約1年の期間をかけて、国土交通省のご担当者の方と、弊社顧問弁護士を交え、議論を重ねてまいりました。
なぜ、国土交通大臣より回答をいただく必要があったのか、そしてこれは今後の不動産取引が電子化されていく中で不動産業界としてどのような意義を持っているのかをお話しさせていただきたいと思います。
今回、弊社のプロダクトが国土交通大臣の正式回答を得た唯一のプロダクトですので、是非弊社のサービスを使ってください。
というようなポジショントークをするつもりでこの記事を書いたわけではなく、電子契約サービス自体は世の中に数多く存在しますので、自社に適しているものを利用すればいいと私個人は思っております。
不動産業は取引をセグメント分けしていくと、数多くの分類ができ、それぞれ特性が異なりますので、自社がメインとしている取引に見合ったサービスを選ぶべきですし、従業員の数や所在する地域も異なれば、それぞれの会社において適している電子契約サービスが異なってくるのは当然です。
そういったことを前提としたうえで、業界全体として不動産取引の電子化を推進していくなかで、我々電子契約ベンダー側と、利用をする宅建業者側の双方が気をつけなければいけないことや、大事なことを綴っていきたいと思います。
ようやく解禁された電子契約
まず、前提として不動産業界においては一部改正宅建業法が施行された2022年5月18日より、電磁的方法を用いた不動産取引が解禁されました。
正確には、これまで書面による交付が義務付けられていた35条書面(重要事項説明書)及び37条書面(契約書)が、電磁的方法による交付でもOKになったということで、不動産の取引がデジタル化できるようになったということになります。
現状の不動産業界における課題
不動産業界はいわゆるDX化が最も遅れている業界といっても過言ではありません。
お恥ずかしながら、私も長年この業界に身をおいてきましたが、営業マンとして現場の第一線で活動している際には、自分自身のPCも持っておりませんでしたし、PCを使った作業はほぼ何もできませんでした。ExcelやPowerPointさえ使ったことがない。そんなレベルで、やりとりは電話とFAXが基本。メールさえ使わない。お客様にお渡しする資料は全て紙。議事録は手書きで複写式のノートを使って、お客様にお渡しする。そんな状態でした。
もし、この記事をご覧になっている方がIT業界やスタートアップ等に身をおいている方であれば、そんなの信じられない。と、びっくりされるでしょうが、これは何も私や私が当時所属していた会社だけに限ったことではなく、業界全体、全国あまねくほぼこれと等しい状況にあります。
それが不動産業界です。
DX化を進めるうえで、介入余地のある領域は多くあるのですが、その中でも契約領域におけるペインはとても大きいです。
一つの契約において平均177枚の紙が印刷され、印刷→製本→封入の工程では平均90分の時間がかかるというデータもあります。
繁忙期で契約数が多い時には契約関係書類の印刷をするために複合機渋滞が起きる。新人時代は複合機渋滞を避けるために朝早く出社をする。せざるを得ない。
弊社の共同創業者はそんな経験もしたそうです。
とにかく本質的な仕事ではない「作業」に時間も資源も無駄遣いされてきたわけです。
電子契約を利用した不動産取引の可能性
そんな不動産業界において、電子契約サービスはまさに「救世主」だと思います。
宅建業者は「作業」から解放され、これまで無駄な作業に縛り付けられていた人的リソースは生産性のあるものへと移行されることが期待できます。特に、人手不足に悩む地方の小さな町の不動産屋さんにとっては、欠かせないものとなってくるはずです。
また、売買契約においては収入印紙が不要となるので、目に見えてコスト削減にも繋がります。これは都心などで高額物件を扱う不動産屋さんになればなるほど効果が歴然と出てくるはずです。
他にもメリットは多くありますが、この代表的な例を挙げただけでも、合理的に考えると使わない手はない。
不動産電子契約サービスはそういったサービスです。
今はまだまだ業界においては電子契約が黎明期ですので、なかなか紙から電子に移行することがイメージできない。年配の人は使いこなせないのではないか。周りの業者が導入するのを様子見てから使いたい。便利そうなのは分かるけどまだ紙のままでいい。ITに疎いからなんだか使うのが怖い。
こういったネガティブな声を現場でお聞きしますが、ガラケーがスマートフォンにとって変わられたように、紙から電子へと移行していくのは時間の問題ですし、この変化は不可逆ですので、どこかのタイミングであっという間に電子契約が主流になると予想されます。
その取引、本当に大丈夫ですか?「国交省マニュアル」にまつわる落とし穴
電子契約サービスを利用して不動産取引を行う際にも、当然、宅建業法を遵守した形で適法に取引が行われることが、宅建業者には求められます。
2022年4月、改正法施行の約3週間前に、国土交通省より「重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」(以下:国交省マニュアルと記載)が出されました。
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html)
これは、60ページにわたる内容の資料となっており、法律家ではない人間が読み解くには非常に難解な内容となっております。
不動産電子契約を謳うベンダーは、各社この国交省マニュアルに準拠している。完全対応している。といったような形でそれぞれのサービスを一部改正宅建業法施行の5月18日のタイミングで一斉にリリースしました。
これにより、宅建業者側は安心をして電子契約サービスを用いて不動産取引を行える。
そういうものだと思って、サービスを採用して、電磁的方法による不動産取引運用を開始された事業者も多くあったと思います。
しかし、実はここに落とし穴が潜んでいました。
なんと、こうした不動産電子契約サービスを利用して不動産取引を行っても、宅建業法に抵触した形で不動産取引が行われてしまう可能性があったのです。
弊社のサービスも例外ではありませんでした。
取引関係者を守るためにベンダー側が確認すべき事項だと考え、国交省への照会を行う
幸いなことに、弊社の場合には国交省のご担当者様と打ち合わせを重ねており、国交省マニュアルに関する解釈の仕方とプロダクトの妥当性ついて齟齬がないか、タイムリーに確認をできる立場にありました。
顧客である宅建業者様が万が一使用方法を間違えて、宅建業法に抵触する不動産取引を行ってしまう可能性が少しでもあると発覚した以上、サービスを運用すべきではないという判断に至り、断腸の思いではありましたが、プロダクト改修を終えるまでサービスを停止することに致しました。
電磁的方法による不動産取引を行う際にどういった点が問題になり、意図せず宅建業法に抵触してしまうのか。
法令の解釈に誤りがある電子契約サービスによって取引事故が起こり、不動産業界での電子契約サービスの普及が遅れてしまう。
そうした業界にとって好ましくない事態が起きてしまうことを回避するためにも、国土交通省に照会を行い、どのような形であれば宅建業法に抵触しないのか。
国土交通大臣から正式な回答をいただく必要があると考えました。
何が問題だったのか?
では具体的にどこのポイントが宅建業法に抵触する可能性のある問題だったのかと言いますと、主に下記の4点が挙げられます。
1、電子契約で契約を行う関係者の同意書(主体者が誰か)
2、35条と37条の時系列
3、改変防止措置と交付のタイミング
4、電磁的方法による交付をした際の重要事項説明書の原本における考え方
こちらに関して詳しくご覧になりたい方は、国土交通省への申請書及び、国土交通省からの回答書が国土交通省より公開されておりますので、そちらをご覧になっていただければと思います。
宅建業法に則り適法に取引を行うのはあくまで利用者である宅建業者であるということ
宅地建物取引業法に基づいて適法に不動産取引を行う必要があるのは、あくまで宅建業者であるということは電子契約が解禁されたからといって、その責任が電子契約ベンダー側に求められる訳ではなく、当然宅建業者に責任があるものとされます。
しかしながら、まだ黎明期であるからこそ、業界内での認知と知見と経験が整っていないため、先述した問題は起きてしまうものと思われます。
電子契約ベンダー側も自分達が提供するサービスを利用して、利用者である宅建業者が法律に抵触してしまう可能性があることを重く受け止めて、宅建業者に寄り添ったサービスを展開していけるよう心がけていくことが、今後の発展のために不可欠です。
まとめ
1、いよいよ電子契約が解禁されました。
2、不動産業界の活性化をはかる上で、電子契約の導入はとても意義あることなので、不動産取引の電子化を不動産業界と電子契約ベンダー業界で力を合わせて進めていきましょう。
3、そのためには宅建業者が宅建業法を守って正しく電子契約を用いて取引を行いましょう。
4、そして電子契約ベンダー側も正しく宅建業法を理解して、宅建業者に寄り添ったサービスを提供していきましょう
5、今回、電子契約を利用した不動産取引で宅建業法に抵触しないやり方の一つの指針として国土交通大臣が回答を出してくれました。
6、その指針を参考として、みんなで正しく電子契約を運用していきましょう。
上記、かなりラフな言葉でまとめを書きましたが、今後の日本経済の活性化のためにも、巨大産業の一つである不動産業界のDX化は欠かせないものとなるはずです。
衣食住の「住」の部分を担う不動産の仕事はとても尊いものですので、私も微力ながら業界の発展のために力を尽くせればと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
