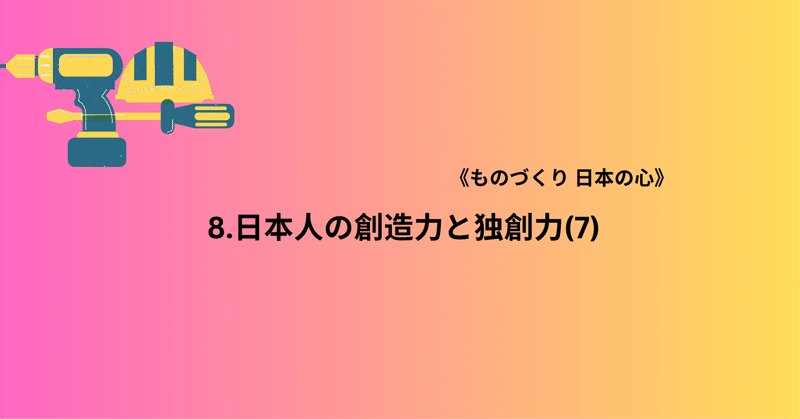
082 打出の小槌と魔法のランプ
データから見れば、文句なしに現代の日本は欧米先進国に匹敵する創造性を持った国といってもいいでしょう。とはいえ、そういわれると、果たしてそんなに私たちは独創的なのだろうか?と一抹の不安も覚えます。
創造力、独創力によく似た能力にもう一つ空想する力があります。この空想力もまた、創造性に大きな影響を持っているのではないかと思います。どこが違うのか広辞苑には以下のように説明されています。
創造:新たに造ること、新しいものを造りはじめること←→模倣
独創:模倣によらず自分ひとりの考えで独特のものを作りだすこと
空想:現実にはあり得るはずのないことをいろいろと思いめぐらすこと
○○力というのは、それぞれを行う力ということですね。「創造」だけに反対語が記されていて、「模倣」と書かれています。模倣の反対が創造ということです。
創造と独創は、自分一人で行うことを除けば、新しいものをつくり出すということは共通しているようです。
そこで空想力ですが、他の2つと大きく違う点は、他の2つが「つくること」を含んでいるのに対して、空想は「思いめぐらすこと」で、独創には現実にありうるかどうか、可能かどうかの制約はないということのようです。現実にないものを作れば創造、独創になり、ものができなければ空想に過ぎないということになります。その意味では、創造、独創の入り口にまず、空想があるということでしょうか。
これまで、日本人はものづくりに際して、スケールの大きさや革新性を優先して作るよりも、コンパクでこぎれいに整備された問題の少ないものづくりを愛する性癖があると紹介しました。それには「空想力」がかかわっているのかもしれません。
研究開発などの際の創造性と独創性の規模を考える出発点として、あり得るかどうかを度外視して、どれだけのスケールで空想できるか、そんなことも重要な気がするのです。
作るという行為は、自分の頭の中でイメージしたものを実現することを目標にして、それにいかに近づけるように工夫・加工する試みだとすれば、日本人が頭の中に描くイメージそのものが、コンパクトなものだということになるのでしょうか。
国語学者の金田一春彦は著書(④『日本人の言語表現』 講談社現代新書)のなかで、
「神話学者松村武雄氏は、日本人の昔話の特色を3つあげ、その第1に、構想の小さなことをあげている」
としてアラビアンナイトと一寸法師の話を比較して紹介しています。
アラビアンナイトに、アラジンの物語があり、そこに「魔法のランプ」が出てきます。
ランプをこすると、魔神が出てきて、その魔神がランプをこすった者の望みをかなえてくれる、というものですが、さすがに大平原の国で生まれた物語です。一度こすっただけで大都会を望み、出現させています。
一方、一寸法師は鬼を退治して「打出の小槌」を手にします。小槌も振れば望みのものを出せるという魔法のランプに匹敵する無限の性能を持っているはずなのですが、この小槌を使って一寸法師が現出させるのは「人並みの身長と、1回分のぜいたくでもなさそうな食事」の2つだけです。
金田一春彦は「何と欲のないことか」と書いていますが、このあたりが日本人の空想力の限界でもあるのではないかと思います。
そこで描かれている一寸法師の人間像が、つまりその程度の夢と希望しかもたない人物ということかもしれません。このスケール感の違いは、ことばとしての表現力にもかかわってくると思います。日本人の誇張からはとても「白髪三千丈]は生まれてきません。
第6章でご紹介した、座礁したオランダ船を引き揚げたきえもんの要求も、帯刀を許されることとオランダの帽子と二本のキセルでした。おなじみの民話で、鶴が命の恩人に果たす恩返しも、自分が織った一棹のきれいな布にすぎません。これまで、そのことに日本人は違和感を持たずに来ました。
創造性、独創性の出発点として、思うだけならば、現実離れした大きなスケールの空想力もほしいところですが、このあたりが日本人の今後の課題ということになるのでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
