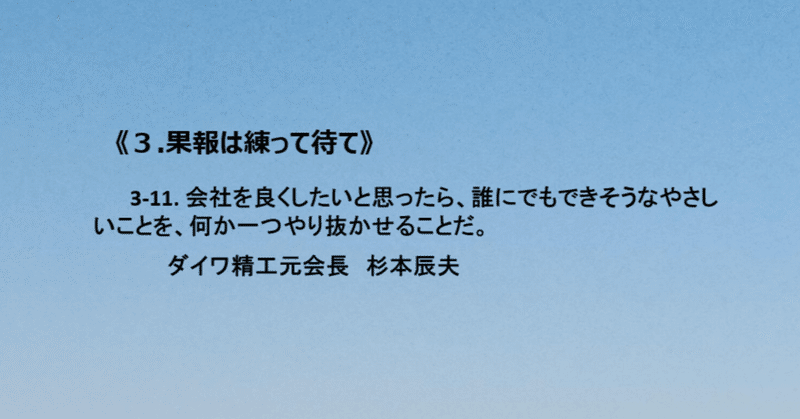
3-11. 会社を良くしたいと思ったら、社員を育てること。それには、誰にでもできそうなやさしいことを、何か一つやり抜かせることだ。
ダイワ精工元会長 杉本辰夫
やさしいことを完璧にやることが会社を良くする……という意見はダイワ精工のトップだった杉本辰夫も語っている。
杉本の言い方はこうである。
会社を良くしたいと思ったら、社員を育てること。それには、誰にでもできそうなやさしいことを、何か一つやり抜かせることだ。
あれこれ欲張って、気がつくはしからやらせようとするやり方は、一見いかにも効果がありそうで、結局、何にもならないことが多い。
ここで杉本が言う「単純なこと」というのは、たとえば時間厳守である。
「訪問した会社で、時計が狂っているようだったら、会社が危ないぞ、と私ははっきり言うことにしている。時間が決まっている会議に多くの人間が遅れてくるようでは救いがたい。一時が万事で、そういう会社は、よく見ればいいかげんなところがたくさんあるものだ」
そんな会社は、いいかげんなところをそのままに、TQCが効果的だと聞けばTQCを導入し、リエンジニアリングの時代だと言えばリエンジニアリングになびき、やれ新規事業だ、インターネットだ,DXだ……と飛びつく。そんな企業に成功した例は少ない。
それよりも、何か一つの地道な体質改善策に徹底的に取り組んだ企業は、大きな効果を上げている・・・というのは、東芝時代に、TQCの分野で広く活躍していた杉本の言い分だけに説得力がありそうだ。
TQCであろうと、リエンジニアリングであろうと、どれも経営を良くするための入り口にすぎない。一つの入り口から入って効果がすぐに出ないからといって他の入り口を覗けば、それまでの活動もすべてがゼロリセットされて、水の泡ということになりかねないのである。
これは会社だけでなく個人にも通じる。
英会話を少しやり、パソコンを少しやり、専門の勉強を少しやり……結局何もモノにできなかったという、よくある話に似ている。人はどうしても、少し高級なことに目が行くから、そこに向かって走りがちだ。
一つのことにじっくりと取り組んでやり切ること、それも当たり前でだれでもできそうなことに取り組んでやりきること、それによって生まれる胆力、それが経営を良くする。それも、誰でもできる単純なことから取り組むのがいいというのは、耳を傾ける価値がありそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
