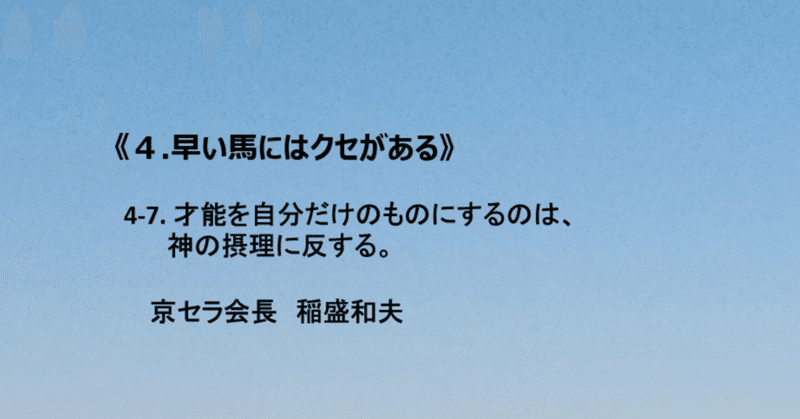
4-7. 才能を自分だけのものにするのは、神の摂理に反する。
京セラ会長 稲盛和夫
常識的な人間には、新しい発想や発見はできない、ということがよくいわれる。新しい発想を持った人は変わった人が多い。そうした特別な才能を持った人間は、それを社会のために役立てるべきだというのが京セラの稲盛和夫である。
昭和29年、通信機メーカーだった富士通は画期的な信頼性の高いリレー式の電子計算機を作って産業界をあっと言わせた。
そのリレー式計算機の開発をリードしたのは池田敏雄で、コンピュータの世界では天才的技術者として知られた人であった。池田は、夕方になると会社に出て来ると、ズボンを脱ぎ、ステテコ一枚になって仕事を始めたという。その奇行ぶりは、長い間、富士通社内では語り草となっていた。
天才という点では、稲盛もまた同様である。
独創的なファインセラミックスの技術開発で、わずか28人の京都の片隅にあった小さな会社を大メーカーに育てた稲盛は、若手経営者たちの育成に細やかな気配りや人情をみせる。と同時に、相手の頭を叩かんばかりに大喝し、納得するまで叱責をやめない厳しさもある。
稲盛のこの二面性は、若手経営者たちには魅力になっているようだが、常識人には測れない個性を持っているからこそ、独創的な仕事を成し遂げることができたと言える。
同じことを稲盛は、また別の言い方で言っている。
「創造的な研究は、狂の世界に入り込める人間でないとできない。クリエイティブな人間には知的バーバリズムとか、無頼性が必要だ」。
稲盛は、日本人の中には異端な発言、異端な発想を認めてくれる土壌がないものだから、サイエンスでも政治でもテクノロジーの世界でも、クリエイティブなものが出てこないと嘆く。
それを改めないと、本当に世界をリードする日本にはなれないと言うのである。
稲盛は経営者として第二電電(現KDDI)の経営に参加したり、若手経営者の育成塾を始めたり、いわゆる社会的な役割を積極的に果たそうとする経営者の一人である。
表題の言葉はこのあと、
「与えられた才能は社会のために使わなければならない」
と続く。
稲盛が会社を創業した時、基盤になったのは稲盛の独創的な発想・技術であった。
しかし、稲盛はその自分の技術的な才能を、決して自分一人のために生かそうと考えていたわけではない。理想的な会社を作ることを夢見て創業しているのである。
のちに稲盛は、
「私が第二電電を始めた理由の一つは、きれいな正しい心を持てばどんな事業でも成功できることを社員に実証して見せたかったこともある」
と語っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
