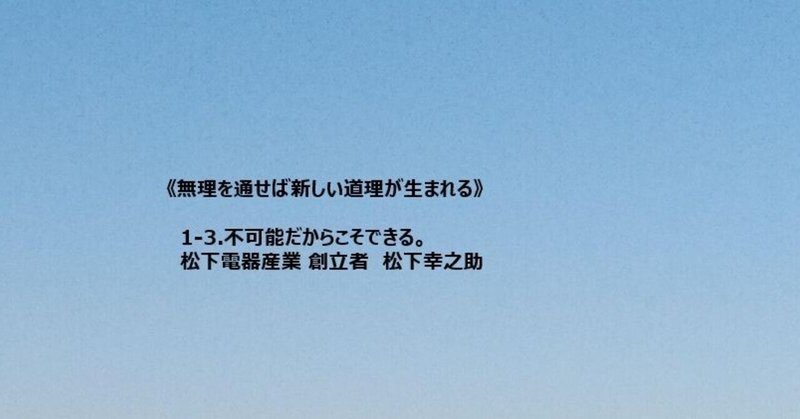
1-3.不可能だからこそできる。
1-3.不可能だからこそできる。
松下電器産業 創立者 松下幸之助
禅問答のようなこの言葉は、松下幸之助語録の中でも有名なものだ。
昭和36年頃、カーラジオを納入していた松下通信工業は、トヨタ自動車から即日5パーセント、半年以内にさらに15パーセント、計20パーセントの値引きを要求された。当時の利益率は3パーセントで、20パーセントも下げれば、17パーセントの赤字である。これを聞いた松下幸之助は、さんざん考えた末に、これを断るのではなく、何とか値下げに応じようということで、以下のように社員たちに伝えた。
「性能は絶対に落としてはいけない。デザインも先方の要求に応じて変えてはならない。この二つを維持する限り、こちらとしては全面的に設計変更してもいいのだから、20パーセントを引いてもなお適正な利益が出るように根本的な設計変更をしよう。完成するまでは一時的に赤字が出ても仕方がない。日本の産業を維持発展するための公の声だと受け止めよう」
これを受けて松下通信工業は全社一丸となって改善に取り組んだ。そうすると、しばらくして20パーセント値引きしても利益が生まれるようになった。
大幅な値下げの要求に直面して、頭から不可能と考えるのではなく、どうしたらできるかと考えた。そして抜本的な改革に取り組んで実現してしまった。不可能を可能にするのも、考え方一つというわけである。
同じような発想はTDKにもあった。TDK代表取締役・生産技術センター長の増島 勝は言う。
「低い目標より高い目標のほうが、実現するのはやさしい」(増島 勝)
増島は同社のコストダウンの先頭に立って、たとえばビデオテープの市場価格の急速な下落にもドラスチックな対策を次々と繰り出して最終的にはコストを70%削減して市場をリードし見事に耐えてきた。ミソは目標の立て方にある。
売り上げ増大や生産性の向上、コストダウンなどの活動で目標を設定する場合、現状を出発点にして少しずつ目標を高くしてゆくのが普通である。たとえば、売り上げの5パーセント増大とか、現状から10パーセントコストを下げるなどという目標の時は、「現状」を前提にして改善を進めてゆく。
しかしこんな低い目標では、かえってなかなか目標を達成できない。なぜなら、現状を前提にするとは、言い換えれば、与えられた方法、与えられた設備、限られた範囲の活動で、予算もほとんどない状態での改善だから、たとえ5パーセント、10パーセンといった低い目標であっても、なかなか実現しないのである。
ところが、目標が一挙に30パーセントということになると、誰しも現状からの延長ではとうていダメだと考える。ゼロからまったく新しい発想、ドラスチックな活動で取り組もうとする。だから目標達成の可能性は非常に大きくなるというのである。それが実現するのならば、予算もそれなりに使えることになろう。
同社では、この考え方をベースにコストダウン活動を展開し、ビデオテープ工場では最終的にコストを3分の1に削減してしまった。大きな成果を得る秘訣は、高い目標を目指し、ゼロから大胆な改革を考えることなのである。
来島ドックの元社長・坪内寿夫も「低い目標より高い目標のほうが達成しやすい」と、同じことを言っている。
来島ドックでは、造船作業の工程、工数を半期で一挙に50パーセント引き下げようという「五〇作戦」が、しばしば行われた。普通なら10パーセントというところを、坪内は50パーセントと主張した。その理由を坪内は、
「10パーセントという低い目標では本当のやる気は起こらない。いきなり50パーセントと言われると、これは大変だ、必死にやらなければ達成できないぞ、と一瞬にして意識改革ができる」(坪内寿夫)
と言っている。
同じようなことだが、増島も少し言い方を変えて、こう言っている。
「最初に非常に難しいことに挑戦すると、次にねらったちょっと難しいことはやさしくなる」 (増島 勝)
たとえば、精密加工技術の開発に当たって、現在1ミクロンの精度まで加工できる技術があり、0.1ミクロンの加工技術を身につけたい時に、0.1ミクロンを目指すのではなく、0.01ミクロンの技術開発を目指せば、0.1ミクロンの技術は比較的簡単に獲得できると言うのである。
0.1ミクロンの技術を身につけるにもかなり努力や工夫がいる。0.01ミクロンはもっと大変である。しかし、0.01ミクロンという目標になると抜本的な対策を考えて、本腰入れて取り組まねばならない。0.01ミクロンを実現するのはなかなか容易ではないが、追求していく過程で見てみれば、0.1ミクロンは簡単にクリアできるようになる……というわけである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
