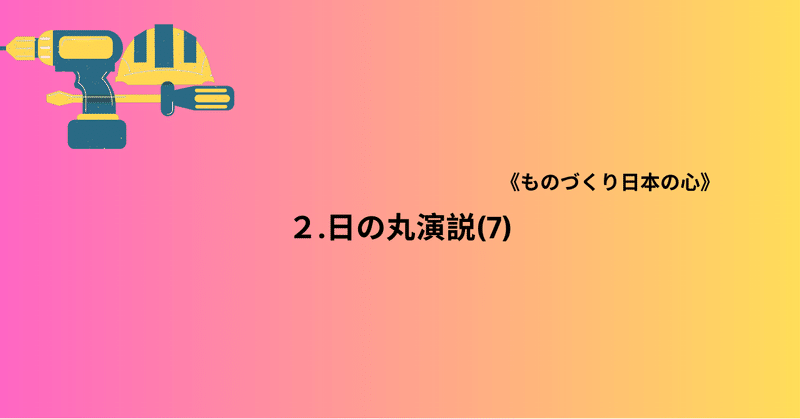
028 文明の最高点に到達せんとする
伊藤は次のように続けます。
我国民は、読むこと、聞くこと並に外国に於て視察することに依り、大抵の諸外国に現存する政体、風俗、習慣に就き一般的知識を獲得したり。今や外国の風習は日本全国を通じて諒解せらる。今日我国の政府及び人民の最も熱烈なる希望は、先進諸国の享有する文明の最高点に到達せんとするに在り。この目的に鑑み、我等は陸海軍、学術教育の諸制度を採用したるが、外国貿易の発展に伴うて知識は自由に流入せり。
日本は、アメリカとの修好通商条約を結んだあと、イギリスやロシア、オランダ、フランス、など5か国と修好通商条約を結んだことで、外国との貿易が開始され、諸外国の政治・風俗・習慣についての情報が入って来るようになりました。
そうしたことから、諸外国の事情はよく理解している。そして、各国の風習なども日本全国に知らされていると述べた後、伊藤はこの視察を通して、日本は何をしようとしているのかを、「今日我国の政府及び人民の最も熱烈なる希望は、先進諸国の享有する文明の最高点に到達せんとするに在り。」と明確に述べています。
つまり、先を進む欧米先進国に追い着き、トップに並びたい、といっているのです。当然、おいつけると思っているのでしょう。圧倒的な差を自覚している中で、この自信はどこからくるのでしょうか。
我国に於ける改良は物質的文明に於て迅速なりと雖(いえど)も、国民の精神的改良は一層遥かに大なるものあり。我国の最も賢明なる人々は、精密なる調査の結果、この見解に於て相一致す。数千年来専制政治の下に絶対服従せし間、我人民は思想の自由を知らざりき。物質的改良に伴ふて、彼等は長歳月の間彼等に許されざりし所の特権あることを諒解するようになれり。尤もこれに伴ふ内変は一時の現象に過ぎざりき。我国の諸侯は自発的にその版籍を奉還し、その任意的行為は新政府の容るる所となり、数百年来鞏固に成立せし封建制度は、一箇の弾丸を放たず、一滴の血を流さずして、一年以内に撤廃せられたり。かくの如き驚くべき成績は政府と人民との合同行為に依り成就せられたるが、今や相一致して進歩の平和的道程を前進しつつあり。中世紀に於ける孰(いず)れの国か戦争なくして封建制度を打破せしぞ。
此等の事実は、日本に於ける精神的進歩が物質的改良を凌駕するものなることを立証す。
我が国にとって、西欧の物質文明の導入は大きな成果を上げているが、我が国の国民にとっては、それよりも、精神的な改良効果の方が、はるかに大きくて重要であり、このことは多くの人間の認める所となっている、と述べ、物質的な改良とともに、長い間許されなかった精神的な自由さも得た。そして、諸大名は、自主的に版籍を奉還し、数百年続いた封建制度は、一箇の弾丸を放たず、一滴の血を流さずに撤廃された、と語ります。
数百年来の鞏固な封建制度が1年もかからずに撤廃され、国民と政府の協力で、平和の裡に国づくりが進んでいる。世界に、戦争無くして封建制度を打破した国は他にあるだろうか。この事実から、日本という国は、物質的な進歩をはるかに凌駕して、精神性という点では進んだ国である……と伊藤博文は誇らしげに訴えているのですね。
政権交代にあたっては、鳥羽伏見の戦い、彰義隊との上野戦争、戊申戦争、函館戦争……などがあり、多くの血が流されました。しかし、肝心の江戸城の開城、大政奉還、版籍奉還までは一滴も血を流さずに話し合いで行われました。伊藤はこのことの意味を訴えたかったのでしょう。
先進国から多くを学び、早く追いつきたいと言いながらも、教えてください……と卑屈になるのではなく、無血革命を実現した精神性の高さはどうだ!と逆にアピールしています。なんとプライドに満ちたことばでしょうか。
このあたりは、2度にわたるイギリス、アメリカへの留学で感じた思いをぶつけたものでしょう。留学で欧米の個人主義や物質的な利益を優先する風潮を知り、その結果、逆に我が国の文化が持つ精神性の高さが世界的にも誇れるものであることを発見した、そんな伊藤博文の経験がここに出ています。
彼我を冷静に比較できるところは、とても31歳のものとは思えません。
又我が女子を教育することに依り、我等は将来の時代に於て今より一層優秀なる智能の涵養を庶幾(しょき:切望する)するものなり。この目的を以て、我国の少女等は既に勉学の為め貴国に来りつつあり。
この視察団の一つの特徴は、多くの男子に交じって、5人の女子留学生がいたことです。しかも、8歳、9歳、12歳、15歳、16歳と全員が若い。なかでも津田梅子(帰国後に女子英学塾、後の津田塾大学を創設)は数えで8歳、満でいえば6歳という幼さでした。その彼女たちも先進国の英知を学ぶことで、「今より一層優秀なる智能の涵養を庶幾する」と大きな期待を背負っていたのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
