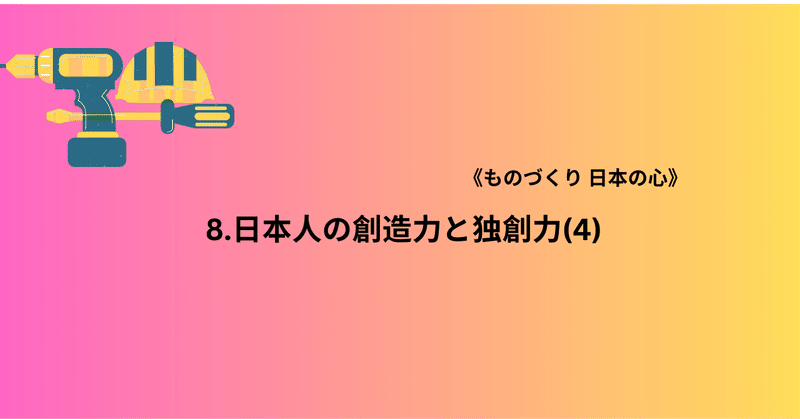
079 独創を拒む「新規製造物禁止令」
江戸時代には、こうした禁令がたくさん出されています。ぜいたく禁止令などもいくどか出され、庶民はそうした制約の中で、着物でも贅沢禁止で、派手な柄の表がダメなら裏地に凝るなど、抜け道を作って楽しんできました。
わたしたちが自由な発想で工夫するというよりも、むしろ与えられた制約のなかで工夫を凝らして解決策を見出すことに喜びを見出すような性向を身につけるようになったのもうなずけます。
中国では、「上に政策あれば下に対策あり」と庶民の処世術・知恵を揶揄するようなことばがありますが、これはむしろ日本の技術そのものが残された難しい条件の中で生き延びるために知恵を発揮して工夫してきた結果でもあるのと考えるのが正しいのかもしれません。
贅沢や浪費を禁止した「奢侈禁止令」が最初に出されるのは、1716年吉宗が紀州藩から抜擢されて将軍になり、課題であった幕府の財政再建に取り組みはじめてからです。
江戸幕府が始まって、戦争がなくなり、世情が落ち着いてくると、各藩では新田開発を奨励し、税収がふえ、藩の財政も潤います。町人が町に溢れ、余った金が巡って社会が活気に溢れて、爛熟した元禄文化(1688年~1704年)が花開きます。
やがて新田は開発されつくします。しかし、バブルで膨らんだ支出はそのままです。浪費が過ぎて破たんした幕府や各藩の財政を再建するため、幕府は奢侈禁止令をだします。このパターンは江戸時代を通じて、何度か繰り返されることになります。
吉宗の時代に、奢侈禁止令と同じように出された禁止令の一つに、新規の工夫を制限する令があり、これが、その後の江戸時代後半の経済・産業を停滞させた一つの要素になったのではないか、というのは、「4.第3章 豊かに広がるものづくりの世界」の円周率の計算の項でもご紹介した『日本史再発見』(朝日選書)の著者板倉聖宣です。
バブルで膨らんだ元禄期の後、反動で停滞が続き、1716年に吉宗によって財政再建が行われます。そんななかで1720年に出された条例が、「新規製造物禁止令」です。
新規製造物禁止令とは、後でつけた呼び名で、「徳川実記」には「今日、寺社奉行・町奉行・勘定奉行・勘定吟味役の輩に仰せ下さるは・・・」として、以下のような触れが出されたと伝えられています。
「いま世上に売り買うよろずの品物、何一つ備わらぬこともなきに、なお多く造りださば、人びと身のほどに越えて買い求むるようになり、自ずから家資窮乏し、ついには国の衰えとなるべければ、米穀・薬物のほか衣服・調度のたぐい、こと新しく製し出すはいうまでもなく、たとい有り来れるとも、物数増益することなきようにすべし」)。
どういうことかと言えば、穀物・薬・衣類・調度品など新しいものを作り出してはならぬ、よそから持ってくるものは、数を増やしてはならぬと指示しているのです。大阪で「きつねうどん」が評判だからといって、それを江戸に持ち込んではならぬ、というわけです。どうしても、という場合には、「役所に訴え指揮に任すべし」と徹底しています。
同様の指令は江戸時代を通じて都合7回も出されているようですので、禁止令を出しても効き目も根本的な解決にはつながらず、何度も出すハメになっています。それだけ庶民の面白がり、ぜいたく意欲はパワフルで、抑えられてもやまぬ力を持っていたようです。幕府も指示を何度も出すということは、かなり本気だった、つまりは財政がそれだけひっ迫していたようです。こうしたお触れで、新田開発も止められ、経済は大きく停滞することになりました。
50年後の1776年に、平賀源内がエレキテルの実験などを行っていますが、これも直後の1787年の寛政の改革で倹約令、緊縮財政、さらには蘭学までをも否定し、新規開発は大きく制約を受けることになりました。
こうした相次ぐ禁止令が、国民にマインドコントロールのように働き、研究・開発意欲を減退させてきたことは想像に難くありません。以来、「変わったことをしない」、「新しいことはしない」という自己規制の意識が、教育やしつけを通して、わたしたちのなかにしみついてしまっているのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
