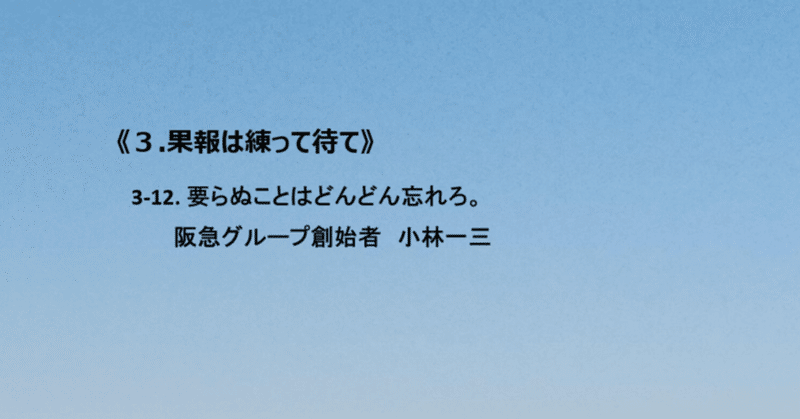
3-12. 要らぬことはどんどん忘れろ。
阪急グループ創始者 小林一三
平凡なことを毎日きちんとやる人のことを、阪急電鉄・阪急百貨店の創始者小林一三は「平凡の非凡」という言い方で表現している。
平凡なことを毎日きちんとやれる人、一日の仕事の後片付けが見事で、その人が急死してもすぐ誰かが受け継げるほどの状態に保っている人を、「非凡」と言っている。
小林一三は阪急電鉄を起こし、ターミナル駅の百貨店を考案し、食堂を上の階に作り、食後に客が下の階の売り場に寄って買い物を促すという「シャワー効果」と呼ばれる仕組みを作った経営者である。その食堂でカレーライスをメニュに加え、日本に洋食ブーム、カレーライス・ブームを作ったのも小林一三だ。
都心に直結する鉄道を敷き、路線の先に住宅地を作り、住宅地から都市の百貨店に誘客するという仕組みを考案したり、宝塚を成功させ、東京宝塚劇場などを始めとする東宝グループを一大チェーンに育てた、まれにみる事業家である。
小林一三は、明治6年に山梨に生まれ、三井銀行で社会人としてスタート。34歳で阪急電鉄の前身である阪鶴鉄道・箕面有馬鉄道に入社すると、以後は天才的な商才を発揮して大衆のニーズをいち早くつかみ、鉄道、百貨店、劇場、レジャーランド……と事業を広げていった。
「良い品をどんどん安く」……かつては中内功が多用したダイエーのキャッチフレーズとして知られるこの言葉も、劇作家志望でもあった小林が阪急百貨店の開店に際して作ったキャッチフレーズだった。当時、百貨店は安く売ることを目玉に始められたのである。
その小林一三をダイエーの中内功は、
「われわれが何をやっているといったって、小林さんが50年も前にやったことを真似しているだけです。電車を引いて、その先に宝塚を作り、沿線を開発して住宅を販売し、ターミナル駅に百貨店を作って食堂に客を呼ぶ。全部小林さんが始めたことです」
と言い、関西商法の神髄に触れる思いだと絶賛している。
小林の発想で驚かされるのは、すでに昭和の初めに、海外生産の重要性を訴えたり、中央集権ではなく地方分権にしないと日本の国は活性化しないと喝破していた点である。
ところで小林は、多くの事業に携わりながら、のちには商工大臣までも引き受ける。さぞかし多忙で八面六臂の活躍で、時間が足りなかったであろうと想像されるが、小林は、
「私は多忙な体である。相当に体も動かすし、頭脳も使わなければならない。しかし、かといって、仕事に追われて弱るなどということはない」
と語っている。
凡人はなかなかこうはできない。仕事をテキパキと処理する小林のコツはこうだ。
「多忙な人に2つの型がある。一つは、要らぬことは片っ端から忘れてしまい、要領だけをかいつまんで頭に入れておく人。もう一つは細大漏らさず覚えている人で、これなどは特別記憶の良い人でなければできないことである。私などは、要らぬことは努めて忘れるように心がけている」
これが小林流仕事術であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
