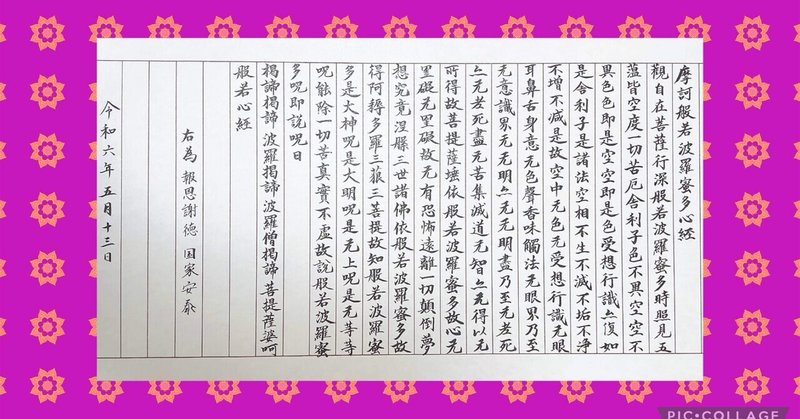
【続いてる写経 1498日め】『大吉原展』、”背景”は至って真剣だった
鑑賞後のもやっと感が強かった『大吉原展』。
開幕前からの炎上事件の記事やら、それに対する東京藝術大学大学美辞術館側の広報、さらに今回展覧会の学術顧問である田中優子先生のご著作『遊郭と日本人』にも目を通して見ました。
「『大吉原展』開催にあたって:吉原と女性の人権」という資料
展覧会の一般公開前に、プレスに対して田中先生による「『大吉原展』開催にあたって:吉原と女性の人権」という資料が出されていたそう。
大事な内容なので全文引用。
本日から開催する「大吉原展」は、吉原を正面からテーマにした展覧会としては初めてなのではないかと思います。もちろん、本日ご覧いただく喜多川歌麿の浮世絵などは、浮世絵展として展示されたことはありますが、それを吉原というテーマのもとに、遊女の姿や着物、工芸品、吉原という町、そこで展開される年中行事、日々の暮らし、座敷のしつらいなどを含めて、一つの展覧会に集めたことは、今までありませんでした。
なぜかというと、吉原の経済基盤は売春だったからです。吉原を支えた遊女たちは、家族のためにやむを得ずおこなった借金の返済のために働いていたわけで、返済が終わらない限り、吉原を出ることはできませんでした。そのことを忘れるわけにはいきません。これは明確な人権侵害です。ですから、吉原をはじめとする「遊廓」という組織は、二度と出現してはならない場所です。
江戸時代に「人権」思想はありませんでした。そして明治以降、解放令が出されたにも関わらず遊郭は1958年に売春防止法が実施されるまで存続しました。その後も現在に至るまで、日本社会に売買春が存在する理由の一つは、吉原をはじめとする各地の遊廓が長い間存在し続け、それが、「女性」についての固定観念を作ったからだ、と認識しています。
この展覧会では、吉原の町を満たす人々の声や音曲や唄が聞こえてきそうな賑わいを、絵から感じ取って欲しいと思います。一貫して丁寧に描き込まれているのは着物です。遊女たちは決してその身体を描かれるのではなく、むしろまとっている文化に絵師たちは注目しています。当時の人々が遊女たちの毅然とした品格に対して、ある種の敬意を持っていたことも、感じとって欲しいと思います。
また、遊廓は書や和歌俳諧、諸道具、舞踊や音曲や生け花などの集積地でもありました。多くの文化人が集い、膨大な絵画や浮世絵、文学、各種の書籍などを生み出す場となりました。「吉原芸者」という一流の芸人たちも育ちました。遊女と芸者は正月、花見、灯籠が並ぶお盆、音曲と踊りがひと月の間毎日披露される祭などの年中行事を実施していました。吉原は日本文化の集積地だったのです。そこを拠点に、さらに狂歌や戯作など多くの文学が生まれ、出版されました。江戸時代の出版文化を支えた一つの拠点になったのです。
遊廓を考えるにあたっては、このような日本文化の集積地、発信地としての性格と、それが売春を基盤としていたという事実の、その両方を同時に理解しなければならない、と思っています。そのどちらか一方の理由によって、もう一方の事実が覆い隠されてはならない、と思います。本展覧会は、その両方を直視するための展覧会です。
ところで、この4月からは「女性支援法」が施行されます。これは、売春女性を「更生させる」という従来の考え方から、女性たちを保護するという「福祉」へ、制度の目的を変える法改正です。しかし女性が人権を獲得するには、それだけでは足りません。女性だけが罪を問われることは、一方的すぎます。北欧やフランスでは、「買春行為」をも処罰の対象とする法律が制定されています。日本もまたその成立を目指すべきだと思っています。
私はこの展覧会をきっかけに、そのような今後の、女性の人権獲得のための法律制定にも、皆様に大いに関心を持っていただきたいと思っています。
「大吉原展」開催にあたって:吉原と女性の人権
田中優子(本展学術顧問)
ご著作『遊郭と日本人』にも上記と同様の主張がありました。
”遊郭”が現代までもたらした負の側面
田中先生によると、江戸時代から373年間続いた”遊郭”の存在が、
・男性上位で権力やお金で女性を意のままに扱えるという固定概念を作り上げた
・男女間の賃金格差や、女性の職業における選択肢が少なく、非正規労働者の割合が高い遠因にもなっている
いうのです。
確かにそうかもしれない…。
浮世絵などに残された”遊郭”の様子があまりにも能天気で華やかなため、そこがそもそも売買春の場であり、女性蔑視や人権無視によって成立していたことを失念してました。
また、最近では『鬼滅の刃』の舞台になるなど、フィクションでもあでやかな場として描かれるため、現代においても”遊郭”のダークな側面は脇に追いやられ、ある種退廃的かつ魅力的なイメージが固定化されてつつあるようにも思います。
当時でも現代においても、”遊郭”が”日本文化の集積地”であったことが、実態は後ろ暗い場所であったことを覆い隠しているとも言えます。
これは反省しなければ。
結局のところ、遊郭の二面性を表現したかった監修した田中先生やキュレーターさんの思いと、
展示できる作品、商業面のバランスが整わなかった。
ゆえに、遊郭の明るい側面に偏らざるを得なかった。
そんな風に思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
