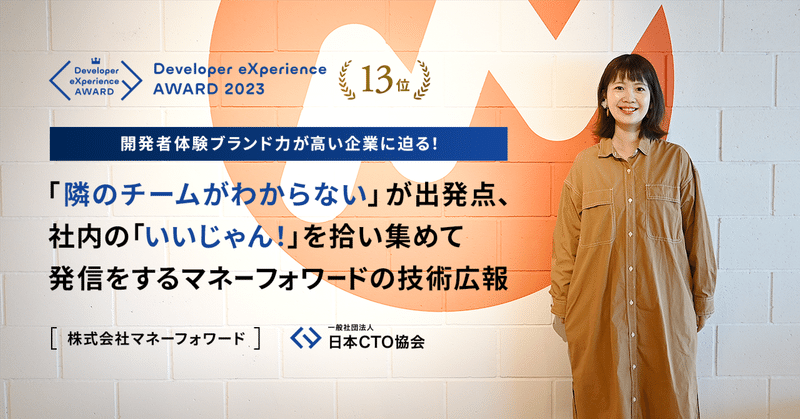
開発者体験ブランド力が高い企業に迫る! -「隣のチームがわからない」が出発点、社内の「いいじゃん!」を拾い集めて発信をするマネーフォワードの技術広報-
皆様こんにちは。日本CTO協会 コンテンツチームです。
「開発者体験ブランド力が高い企業に迫る!」シリーズの4本目は「株式会社マネーフォワード」のインタビュー記事です。
「開発者体験ブランド力が高い企業に迫る!」シリーズとは:
日本CTO協会が2022年より実施・発表を行なっている「開発者体験ブランド力調査」のランキング入賞企業に日本CTO協会がインタビューを行い、記事化したものです。
本コンテンツでは各企業の
・技術広報チームの目的とそれに対してのKPIの考え方、読んだ方に向けてヒント
・開発者体験向上に向けた技術広報の取り組み
・開発者体験とは
について記載されています。
開発者体験ブランド力調査とは
【開発者体験ブランド力調査のコンセプト】
「開発者体験発信採用広報活動の指標・羅針盤をつくる。」
・認知度コンテストにならないこと
実際のソフトウェア開発者が所属するエンジニアの技術的な発信などを通じて、開発者体験がよいイメージをもったことを起点とする。
・日本CTO協会の会員企業への恣意的調査にならないこと
採用サービス複数社からメールマガジンなどで回答者を募り、当協会から直接関係者に回答を募らないこと。
・技術広報活動の指針となる詳細を持つこと
職種や年収層、チャネルの効果や具体的な印象などを調査に盛り込むことで、ランキングだけではわからない影響を知れるようにすること。

レポートについては、日本CTO協会の法人企業にのみ公開を行っております。
本コンテンツは2023年より日本CTO協会内で企画されたため、2023年の開発者体験ブランド力調査ランキング入賞企業の順位が高い順にお声がけし、コンテンツ化を行なっております。
※本記事の内容は、全て取材時のものです。
株式会社マネーフォワードについて
株式会社マネーフォワードは 「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をミッションに、すべての人のお金の課題解決を目指し、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』やバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』などを提供しています。
https://corp.moneyforward.com/
今回はエンジニアリング戦略室 エンジニアエンゲージメントグループ 福場さんにマネーフォワードの開発者体験や技術広報についてお伺いしました。
株式会社マネーフォワード エンジニアリング戦略室 エンジニアエンゲージメントグループ 福場 麻美 氏
2022年8月に株式会社マネーフォワードにエンジニア採用広報として入社。「社内外のエンジニアとのエンゲージメントを強化する」をミッションに、カンファレンススポンサーやイベント企画、テックブログ運用やメディアリレーションなどを担当。集合写真・銭湯・ラジオ・宝塚が好きです。

技術広報だけではなく、所属エンジニアの様々なチャレンジを支援するエンジニアエンゲージメントグループ
ー福場さんのお仕事について教えてください
福場氏:
エンジニアリング戦略室エンジニアエンゲージメントグループに所属しています。エンジニアリング戦略室は、会社の成長をサポートするために、エンジニア組織をエンパワーすることをミッションとした部署です。その中にあるエンジニアエンゲージメントグループは、主に2つの活動をしています。
社内向け:エンジニアのワークエンゲージメント向上
社外向け:社外のエンジニアと深いつながり構築
社内向けについては、「マネーフォワードで熱中して働ける」「成長できる」「働きがいがある」という体験をつくるために、所属しているエンジニアの様々なチャレンジを支援する、そういう機会そのものをつくったりしています。
社外向けは、例えばイベントやカンファレンス、取材などの発信を強化していくことで、マネーフォワードの魅力を伝えていく活動です。
エンゲージメントグループは私と、エンジニアのバックグラウンドがあるメンバーとの2名体制です。

ーエンジニア戦略室には、福場さんが所属するエンジニアエンゲージメントグループとは別の役割・機能もあるのでしょうか?
福場氏:
エキスパートグループというものがあります。例えばGo、iOS、Androidなどの言語やプラットフォーム単位で、その分野のエキスパートたちが集まり全社的な施策や方向性、社内トレーニングなどを横軸連携するための仕組みです。
全員、実際にサービスを開発している部署に所属していて兼務でエキスパートグループでも活動しています。現場の課題感をもって、全社的な取り組みを行っています。
まずは「ありのままを捉える」のが大事、マネーフォワード流・開発者体験のつくりかた
ーマネーフォワードでは開発者体験について、何か取り組みなどを行っていますでしょうか?
福場氏:
前提として、開発者体験は、エンジニアがサービス開発をするプロセスの中で感じるものです。当然、人によって感じ方も様々ですので、「マネーフォワードとしての開発者体験は●●だ」と定めることはできません。
そこで、開発者体験がどのようになっているのか、「ありのままを捉える」ことが重要になってきます。そのために開発者体験サーベイというものを行いました。これについては、VP of Engineeringの高井が「開発者体験サーベイ、めっちゃよかったんで、おすすめです」というブログを書いています。こうした調査をもとに、より良い状態にもっていくことは大事だと考えています。
会社としては、開発者が熱中して仕事ができるような環境を整えたいと考えています。このため、開発プロセスやワークフローに、それを妨げるような原因がないか把握し、それらを改善するために開発者体験サーベイを活用しました。サーベイではPCのスペックが充分か、開発環境は効率的か、ソースコードやドキュメントの品質、集中して開発できるか、など各項目について開発者の感じていることを聞きました。具体的なことを聞くことができたので、この開発者体験サーベイはすごく有益だったと感じています。

ーエンジニア組織のビジョンはありますか?
福場氏:
「お金を前へ。人生をもっと前へ」というのが会社のミッションで、それを実現するためにテクノロジーやデザインの力を最大限に活用しよう、そしてユーザーに価値を届けようという想いは、全社としても大事にしています。
そのため、エンジニア組織もプロダクトにフォーカスした組織作りを目指していますね。
あと、エンジニア組織には「Let’s make it!」という掛け声があります。
ー掛け声の「Let’s make it!」は、いつ頃に生まれたのでしょうか?
福場氏:
もともとは2018年に本社オフィスが新しくなったときのコンセプトが「Let’s make it! (共に創り、実現しよう!)」だったんです。それが自然発生的に色々な場面で利用されるようになっていました。昨年「マネーフォワードの開発マインドを表しているフレーズがあるといいよね」ということになり、改めてエンジニア組織としても「Let’s make it!」を大事にしていこうとなりました。マネーフォワードのエンジニアといえば「Let’s make it!」と思い浮かべてもらえるようになると嬉しいです。

組織急拡大にコロナ…「うちのチームにある良いナレッジを、隣のチームに向けて発信する」ところからスタートした技術広報
ー技術広報を大事にされているのは、なぜでしょうか?きっかけのエピソードなどがあれば教えてください。
福場氏:
きっかけは、2020年頃の急激な組織拡大だったと思います。ちょうどコロナが蔓延して緊急事態宣言があった年です。
マネーフォワードは、元々スモールチームで権限委譲をして、スピード感を持って開発するのを大事にしていたのですが、コロナ禍と組織急拡大が重なるという状況で、「隣のチームが何をしているのかわからない」という課題が発生してしまいました。エンジニア同士の横のつながりも弱くなってしまい、エンゲージメントが下がってしまったと聞いています。
それを改善するために、「良いナレッジを、隣のチームに届くように発信しよう」と、もう1人のチームメンバーが技術広報に就任し、取り組みを始めました。
それがきっかけで、月に1度社内のエンジニア全員が参加する勉強会、Engineering All Handsや、ブログでのナレッジ発信などを強化しました。
ーエンジニアエンゲージメントグループが設立したのも、その頃ですか?
福場氏:
部署ができたのは2022年です。
私が入社したタイミングで、社外への発信もより強化していくようになりました。
入社して、社内のことを知るうちに「マネーフォワードは、新しい技術を積極的に取り入れていたり、面白い取り組みを数多く行っているのに、社内ですら、あまり知られていないことが多いな」と感じました。
例えば、金融機関などのサービスと連携し、口座の入出金情報などのデータの取得を行うアカウントアグリゲーションの技術は、日本でもトップクラスだと思います。他にも、本当にいい取り組みがたくさんあるのに、社内の人たちがお互いをあまり知らなくて、「もったいない」と思ったんです。だから、社外に向けた発信も大事ですが、まずは社内向けの活動・インターナルコミュニケーションを強化しましょうということからスタートしてます。
ーまさに「エンジニアエンゲージメント」ですね。今のお話を聞いて、このグループ名がしっくりきました。
福場氏:
私は中途入社ですが、同期が数十名いるので本当に組織が急成長していて「お互いを知る機会を増やす」というのが、重要でした。
ー社内への活動は、どういったところからスタートしたのですか?
福場氏:
「お互いに頑張ってコミュニケーションしてください」と呼びかけるよりも、仕組みをつくっていくのが重要かなと考えたので、先ほども話したEngineering All Handsで、新入社員紹介をしたり、プロダクトの最近のアップデートを共有したり、技術トレンドを紹介するように設計しました。あとは毎月エンジニアとしてよい振る舞いをした人に贈るLGTM賞という賞をEngineering All Handsで紹介したりもします。
最初の頃は、発表者がなかなか見つからず苦労したのですが、最近は海外メンバーも積極的に発表してくれたりと、英語での発表も多くなってきています。
ー目標設定などは、どのようにしていますか?
福場氏:
全社の目標から落とし込んで、グループのゴールやアクションを決めています。内容によっては私たちだけでは難しいこともあるので、現場エンジニアや採用担当の方などと、チームを組みながら進めています。
あと、技術広報のような中長期的な取り組みが必要なものは、採用担当やエンジニアが「やりたいけどできない」ことも多いので、私たちが周りに中長期の技術広報施策の重要さを理解してもらうような活動をすることも大事だと思っています。
先ほど海外メンバーの話もしましたが、マネーフォワードはエンジニア組織の4割以上が外国籍のメンバーなので、グローバル向けの発信強化も行っています。今までマネーフォワードを知らなかった英語圏の人たちに、知るきっかけを提供したくて、英語ブログの開設をするなど環境整備をしています。

ーグローバル化をしていくうえで、課題などはありますか?
福場氏:
グローバルタレントへのアプローチ方法が、正直なかなか見えてこないという課題はあります。国内にいる外国籍の方と、海外にいる外国籍の方でも、やり方は全然違いますし、手探りで進めている状態ですね。
ー社外向けの技術広報で目指している姿はありますか?
福場氏:
国内に関しては、「プロダクトづくりに真摯に取り組み、ユーザーに支持されて、組織も成長している」という姿を伝えていけるようにしていきたいです。
マネーフォワードは実は50以上のプロダクト・サービスを提供しており、トラフィックやデータもかなり多いですが、社外の方たちにはまだよく知られていないと思います。「様々な取り組みに挑戦している」「新しい技術を使っている」「グローバル人材も増えている」という部分は、もっと伝えていきたいですね。
その機会をしっかりつくるというのが、技術広報の大事な仕事だと思っています。
ー最後に、技術広報へのこだわりを教えてください。
福場氏:
私は、マネーフォワードの様々な取り組みを、みなさんに知ってもらうことをミッションにしています。これをするためには、「私自身が社内のことをよく知っている」というのが一番大事です。そのため、誰よりも社内のエンジニアの取り組みを知っているようになろうと思っています。社内の「それ、いいじゃん!」をたくさん集めて、それを発信して、社内外にマネーフォワードの情報をたくさん届けていきたいです。
ーありがとうございました!
