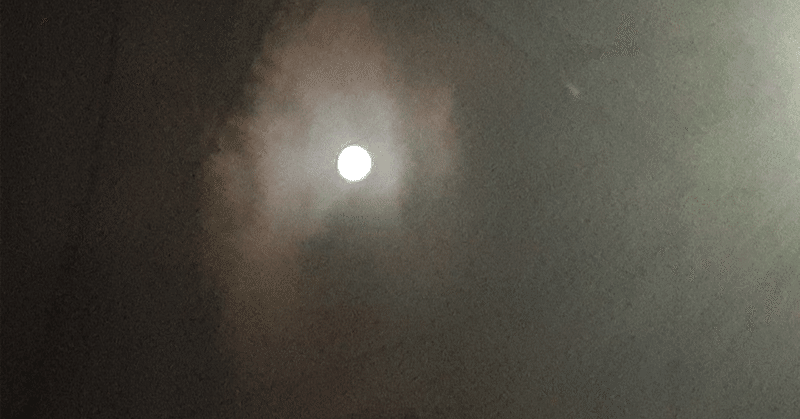
「意識変容の現象学」成果報告会 雑感
北海道大学「人間知×脳×AI研究教育センター」の研究成果報告会にZoomで参加。内容に踏み込みすぎるのはアレなので雑感だけ書いとく。
セッション1:時間論
まず、意識と時間は深く結びついているという視点が、それで良いのかと感じるところ。ベルクソンは最近流行りだけどもさ。
主観的時間から考察しても「脳の構造がそうだから」という枠組みがわかるだけな気がする。主観的時間は脳にある神経ネットワークが電気的刺激をトリガーとして伝送されていくという一連の物理的な現象に起因して生じた前後関係に依存して実感できるものであって、時間そのものに言及できるものでは無いんでないかと。客観的な時間が一方向性を持っているように観測できることのほうが不思議だとぼくはおもう。
圏論。何年か前に長浜バイオ大学での圏論の研究会みたいなやつに行った時の講師をしていた先生だった。圏論は理解のサポートをするツールとして有用だと思う。掘り下げると難しいけど。
セッション2:精神疾患での意識変容
サリエンスという捉え方を知らなかったので、面白かった。ざっくり言えば注目の対象になる顕著さ。生物的にみれば、興味をそそるもの(注目の対象)と自分に害をもたらす可能性があるもの(回避の対象)がある。そのサリエンスをアフォーダンスとして捉え直すと。このあたりの入力と出力が同一視可能な双方向循環式フィードバック制御が恐らく意識の要なんだろうなあ。
精神疾患との関係については、自由エネルギー原理におけるエネルギー最小化の機構がトリガーとなってサリエンスの暴走が起きるんじゃないかなあという推論をした。自分も仕事柄、精神疾患の人と日々関わっているけど、サリエンスから逃れられなくなる、目を逸らす制御が難しい状態にあると感じる。身体にはどのように実装されているんだろう。目を逸らせない時の入れ込みの深さは統合失調症が強く、目を逸らす制御の困難さは自閉スペクトラムとか強迫性障害あたりのほうが強そうだなあと思った。何をどこまで同一視して良いものなのかわからないけど。
質問の最後のほうで「統合失調症では、自分対世界みたいな過度に一般化された構図になっているのでは」という話があって、それはすごく面白い視点だなと思った。一般化が要因の一つにはなってそう。
以上、仕事に使えそうな話や発想が得られて、良い休日でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
