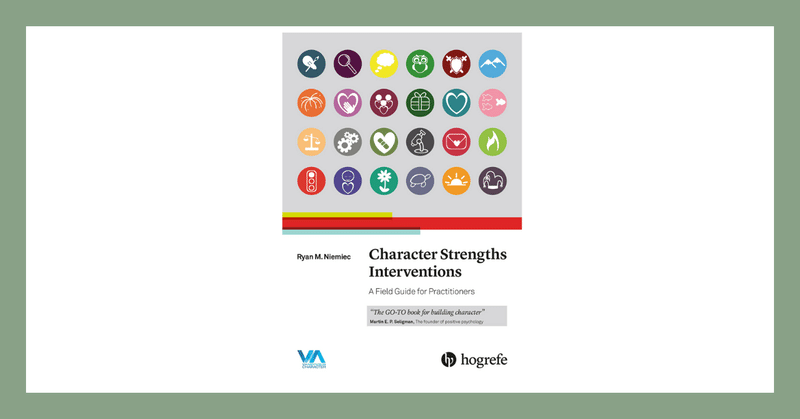
書籍『Character Strengths Interventions』を読み解く #4(第2章前半)
こんにちは。紀藤です。本日もシリーズ「書籍『Character Strengths Interventions』を読み解く」をお届けいたします。
今日のお話は、「シグニチャーストレングス(特徴的な強み)」ついてdesu
。特徴的な強みは個人における「中核的な強み」とも言われ、強みの活用の理論において、外せない概念の一つです。
ということで早速、その内容を見てまいりましょう!
(前回までのお話はこちら↓↓)
第2章 シグニチャーストレングス(特徴的な強み):研究と実践
特徴的な強みは、ポジティブ心理学で研究され、実践されている概念の一つです。この強みが使いやすい理由として、
・自分のスタイルを変える必要がない
・すぐにメリット(利益)を感じられる
・科学的な裏付けがある
・欠点に焦点を当てるアプローチが当たり前の人にとって、斬新でユニーク
などが挙げられています。
「特徴的な強み」とは何か
では、具体的に「特徴的な強み」とは一体どのようなものなのでしょうか?
その定義などについて、見ていきましょう。
特徴的な強みの「定義」
VIA分類の原典である『Character Stregnths and Virtues』(Peterson&Seligman, 2004)では、「特徴的な強み」について次のように述べます。
<特徴的な強みとは>
・”個人が所有し、称賛し、頻繁に行使する、ポジティブで個人的な特性”
つまり、特徴的な強みとは「個人のアイデンティティや自分が何者であるかという概念と結びついており、(自分という文脈と)切り離して考えることができない」ものである、ということです。
特徴的な強みの「基準」
そんな「特徴的な強み」は、以下のような基準を、すべてではないにせよ、ほとんど満たすものであると述べます。
<「特徴的な強み」を考える基準>
・所有感と信頼感がある(「これが本当の私だ」と感じる)
・使っているときワクワク感がある
・初めて実践するとき、その強みが急速に身につく
・新しい使い方を見つけることへの憧れがある
・力を使う必然性を感じる(「私を止めてみろ」感)
・力を使い果たした後は、疲れるよりもむしろ爽快感がある
・それを中心とした個人的なプロジェクトの創造と追求がある
・喜び、活気、熱意、ときに恍惚感さえある
ちなみに、ポジティブ心理学の研究者の間では、「個人のトップ5の強み」を特徴的な強みとしてターゲットにすることが慣例になっているようです。(別研究では「人には3~7個の特徴的な強みがある」や、「特徴的な強みは他の強みよりもVIAスコアが有意に高い」という視点や発見も述べられています)
特徴的な強みを「見極める質問」
さて、上記の「基準」と照らし合わせても、実際のところ、どれが自分の特徴的な強みなのかよくわからない・・・、という場合もあると思います。
特徴的な強みであるかどうかの最も重要なポイントは、(繰り返しになりますが)「その人にとって中核的、または不可欠なものとみなされているかどうか」です。
よって、以下のような質問を考えると、自分の特徴的な強みかどうかを見極めることに繋がると述べられています。それは、このような質問です。
<特徴的な強みを「見極める質問」>
「その強みは、あなたという人間にとって、必要不可欠なものですか?」
「この強みのリストのうち、どれがあなたという人間にとって、最も核となるものですか?」
「もし自分のその強みがなかったら、どんな人生になるでしょうか?」
「もし自分のその強みが、自分の中から引き抜かれてしまったらどう感じるか?」
私の例で恐縮ですが、上記の問いについて考えてみました。
たとえば、私のVIAの上位5つは『向学心・社会的知性・スピリチュアリティ・感謝・好奇心』です。そして考えてみるわけです。
「自分の『向学心』という強みがなかったら、自分の人生がどうなるか想像できるだろうか?」「・・・いやいや、ありえない。想像もできないし、全く自分ではなくなってしまう気がする」と思えます。
他の上位の強み『好奇心』『スピリチュアリティ』『社会的知性』も同様に”もしなくなったら「まったく自分らしくない」と感じます。つまり、これらの強みは私にとっての「特徴的な強み」となります。
一方、中位の強みである『大局観』『審美眼』などはなくても、「まったく自分らしくない」とまでは思いません。つまり、自分にとっての特徴的な強みでは”ない”と思われます。
特徴的な強みの研究
また「特徴的な強み」を活用した、様々な研究について、本章では紹介されています。
その中でも、もっともよく引用されている研究の一つとして、577名の成人を対象にした二重盲検法のランダム割当実験です。介入群と対照群を分けて行った調査が紹介されていました(研究の内容はこちらの記事に、元の論文を紹介しています)
同じような研究を、カナダ、オーストラリア、イギリス、中国などでも再現されており、対象者についても青少年から高齢者まで変えても同じように幸福度や抑うつなどに影響があることがわかりました。
その他、「特徴的な強み」を活用した様々な成果
・心理的疾患のおける介入効果(ポジティブ心理療法)
・キャリアカウンセリングにおける介入効果
・ビジネスにおける介入効果
・教育における介入効果
・軍における介入効果
・その他の介入効果
について、本書執筆時点までに明らかになっている主要な論文の発見について、全体像を紹介されていました。(この網羅性はすごかったです・・・)
まとめと個人的感想
さて、今日は第2章の前半「特徴的な強み」について、その定義や基準を中心に、その内容のポイントをお伝えしてまいりました。
改めて読んでみて思ったのが「性格的強みの分野における、世界のトップランナーがまとめている内容は、網羅性もわかりやすさもすごい・・・」でした。
特に、第2章の一つの節でまとめられている「文脈における特徴的な強みの研究」のパートでは、その論文の網羅性から、本当に全ての論文に目を通されてきている方なんだ、とその遠い背中を感じたパートでもありました。(とはいえ、そこで紹介されているものの一部は私も読んだことがあるものもあり、強み論文100本ノックの成果も感じました)
ということで、次回は「第2章:特徴的な強みの活用」についてお伝えしてまいりたいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
