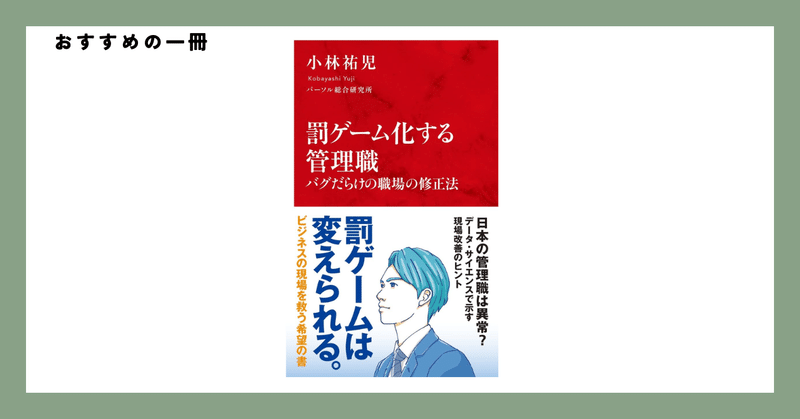
おすすめの一冊『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』
こんにちは。紀藤です。本日はおすすめの一冊をご紹介する「今週の一冊」のコーナーです。今週の一冊はこちらです。
<おすすめの一冊>
『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』
小林 祐児 (著)/インターナショナル新書
https://amzn.asia/d/hQxgbAL
「罰ゲーム化する管理職」という記事
2023年の年末、日経ビジネスで「罰ゲーム化する管理職」という特集が組まれた雑誌が本棚にならびました。いくつかの管理職研修に関わる中で、管理職の方にインタビューを通じて、そのタイトルが非常にリアルに感じられて、気になっていたのでした。
「管理職罰ゲーム」というのは、「管理職に元気がないという問題以上に、罰ゲームのごとく厄介な課題が発生し続け、管理職に降りかかる状態」と言えるようです。ご紹介の書籍から引用すると、現役の管理職からの声に、次のようなものが聞かれと述べます。
「朝から晩まで会議ばかりで、夜からしか自分の仕事ができない」
「メンタルヘルスの不調で、常に部下が欠けている状態で働いている」
「ハラスメントと言われるのが怖くて、部下を叱るのが怖くなった」
「会社から女性活躍と言われても、女性側にはその気が無くて困り果てている」
「若手社員がみな指示待ちの姿勢で、主体的に動いてくれない」
実際に、会社の状況はそれぞれではありますが、「罰ゲーム化する管理職」と言われ、そして雑誌で特集を組まれるということは、日本企業における構造的な問題が潜んでいるようにも思われます。
では、一体それが何なのか? そのことについて著者がデータを元に、そう呼ばれる原因を検討し、その上で方向性を提唱示しているのが本書となります。
本書の構成
本書の構成は、4章に分かれて解説されています。
第一章「理解編」では、「罰ゲーム化の現在を概観」しています。
会社組織における管理職の役割と負荷の現状、ならびに日本経済のマクロトレンドや時流を確認しています。ここを読むことで「うちの会社だけではなく日本中で起きている」ことがわかります。
第二章「解析編」では、「管理職の何が大変なのか」をデータを通じて掘り下げています。心理的負担、業務負担などミクロのデータで読み解いていきます。
第三章「構造編」では、「罰ゲーム化がなぜ発生し、放置されるのか」が考察されています。ここでは内部構造に注目されており、特に「なぜ日本でこの問題が起こるのか」という日本の特殊さ(終身雇用・年功序列以外の表面的なもの以外を含めて)が語られています。
第四章「修正編」では、「罰ゲームを止めるために何ができるか」という提案がされています。具体的な4つのアプローチがあり、経営・人事向けに役立つ内容となっています。
罰ゲーム化する構造 -3つのループ-
第三章にて、罰ゲームと呼ばれるようになる構造的な理由が図示されています。ポイントをお伝えすると、以下3つです。
1つ目が、「人事の個別対処グループ」と呼ばれるものです。組織の問題を現場にいる個々の管理職に帰責させていく、という状態です。そして会社が管理職に変わってもらおう、とスキルトレーニングを行います。しかし、実際は構造的に管理職に負荷が集中しすぎている状態もあるため、根性論ですべてを管理職の原因としてよいのか、というのを検討する必要があります。
2つ目が、「現場のマネジメントグループ」です。負荷が大きくなった際に、現場管理職が部下の行動管理を厳格に行うことでマイクロマネジメントとなると、結果として部下の指示待ちや批判的行動を増大させてしまう、という現象が起こります。すると、ますます業務量は増え、管理職が携わる場面も増え、というループが起こることになります。
3つ目が「管理職人材不足グループ」です。業務量が増加し、部下の育成に手が回らなくなり、自分でプレイヤーとしての業務を行うことになります。それを見ていた部下が、「管理職になりたくない」とし、ますます管理職不足に拍車がかかる、という構造です。

問題解決の4つの方向性
第四章では、実際にどのような解決方法があるのかについて、4つのアプローチが示されていました。
1つ目が、「フォロワーシップアプローチ」です。
ピープルマネジメント領域のスキルを、管理職だけではなくメンバーにも伝えるというアプローチです。
管理職がコーチング研修等で問いかけが上手になっていくら「いい球」を投げられるようになったとしても、メンバー側が自ら育とうとする気持ちがなければ、効果が限定的になることは想像に固くありません。キャッチボールは投手も捕手もどちらもレベルアップする必要があります。
2つ目が「ワークシェアリング・アプローチ」です。
これは、管理職がメンバーやリーダーに権限委譲をしていくというアプローチです。つまり、適切に任せていき、管理職の仕事を適切に手放していくアプローチです。
3つ目が「ネットワーク・アプローチ」です。
管理職同士の「信頼しあえる」社会関係資本を作るというアプローチです。
これは私も思うのですが、マネジャーは孤独になりがちです。その中でマネジャー研修などでその課題を共有しあえると、その時間そのものが価値が生まれる場面を見てきました。管理職同士の横のつながりを意図的に作っていくことも重要なアプローチと考えられます。
4つ目が「キャリア・アプローチ」です。
健全なえこひいき型の選抜育成、スペシャリスト型の管理職育成と述べられています。日本はオプトアウト型(基本は管理職になるレールに載せられていく)という伝統的なキャリアがありましたが、海外のオプトイン(参加したい人が手を上げて参加をする)ように、必要な人に教育をし育てていくことが重要ではないか、と述べられていました。

まとめと個人的感想
豊富なデータを元に考察されており、系統だって整理されることで「何が罰ゲーム化させてしまうのか」について問題を認識する上で、とても勉強になる一冊でした。
上記でお伝えした要因以外にも、法的な「管理監督職」と「管理職」が混同されていること(権限や経営の関与がないのに管理職という冠がつけられて残業支給などがなくなる等)、日本文化的な背景、たとえば年功と年輪的な序列(何年入社など)がコミュニケーションを複雑にしていることや、初対面の人に対する信頼度の低さ(新たな関係を開拓するのが苦手な国民性)などにも触れられているのも、興味深いものでした。
本書で語られているように、管理職にまつわる課題を「管理職の根性論」で片付けずに、そう思わせる要因を切り分けることで、自社でそういった話が出ていた場合、それはどこに原因があるのかを検討するための補助線になるように思います。
また、現在「ジョブ型」への移行が注目される中で、そのような考えや仕組みをどのように取り入れて機能させるかを考える上でも、本書で語られている内容は参考になると感じた次第です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
