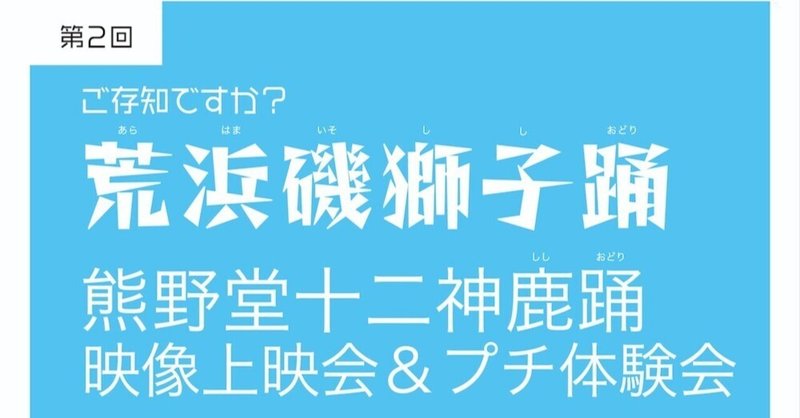
第2回 ご存知ですか?荒浜磯獅子踊 熊野堂十二神鹿踊映像上映会&プチ体験会|2024.05.12
先日5月12日、仙台市若林区荒浜の海岸公園センターハウスで開催された「第2回 ご存知ですか?荒浜磯獅子踊 熊野堂十二神鹿踊映像上映会&プチ体験会」に参加してきました。

先月4月14日に執り行われた熊野本宮例祭で奉納された熊野堂十二神鹿踊の記録映像を来場者で見て、その後に映像を見ながら身体を動かしてみるという内容でした。
前回の第1回の勉強会で荒浜磯獅子踊は名取市の熊野堂十二神鹿踊と同じ系統ということを聞いていたので、僕も気になって見に行っていました。その時の記録映像も今回皆さんとシェアさせてもらいました。
荒浜磯獅子踊を復活するにあたって、まずは熊野堂十二神鹿から演目を習い、踊り、囃子、それに含まれる意味などの基本を覚えて荒浜磯獅子踊として分家させてもらう感じの流れになってきているようで、とても素晴らしいことだなと思います。

あたりを見渡すと、雄勝で一緒に囃子をやっている横笛奏者の山下さん、先日の大須八幡神社、白銀神社の例大祭で神輿を担ぎにきてくれた一ノ瀬さん、福島大の音響の先生、からだとメディア研究室の方々、仙台鬼剣舞同好会の方々と多方面でお世話になっている方々が集まってきていました。
今回の会にも熊野堂十二神鹿踊保存会代表の板橋さん、囃子で篠笛をされている渡辺さんも来ていただいて映像を見ながら(2周目)演目の名前や解説をしてくださいました。
また、海辺の図書館の方(三浦さん)がブルーシートとボイド管で手作りした練習用の試作太鼓を見せてくれました。なるほど。見た目より低い音が鳴っていました。

確かにこれなら予算をあまりかけずに練習用の太鼓を数を揃えることができそうですね。ブルーシートとボイド管は盲点だったので、何かの時に自分も参考にさせてもらおう。
また他の方が、聞いた囃子を譜面を起こしてキーボードで弾いてみたり、基本の口唱歌を共有してくれたりと、各々が手探りで触れていこうという気持ちが溢れていてとても活気を感じました。とても良いと思いました。


映像を見ながら身体を身体を動かす意欲のある方々もとても多く、これは面白くなっていくだろうなぁとワクワクしていました。僕は山下さんの後ろについて一緒に笛の稽古をさせてもらいました。
(四倉+山下さんコンビは雄勝町胴ばやし獅子舞味噌作愛好連のお囃子組でもあります)

例祭で実際の演舞も見ていたので通り、入羽はある程度旋律は見えてきたのですが、雌鹿隠しの構成がどうしても掴めず。
熊野堂十二神鹿踊の渡辺さんもいらっしゃっているので山下さんが色々と尋ねてくれていると、決まった回数で回している訳ではないとのことで、どうやら踊り主導であるのかなと。今度の機会に熊野の方の練習会にもお邪魔させてもらってお話をもっと詳しく聞きながら、踊りを見て(できれば覚えて)掴んでいきたいなと、山下さん。

熊野堂の渡辺さんとお話していて、荒浜のこのような取り組みと交流を持てていることに対して本当に良く思ってくださっていました。
”これから、熊野堂と荒浜の人たちと交流を続けて、荒浜の人たちも鹿踊(獅子踊り)を覚えたら熊野の手伝いをできるよになったら嬉しいし、これからの民俗芸能の在り方なのかもしれない“
と、仰っていたのが印象的で。というか、本当100%同意です。

来場者の方で音楽をやっている方とお囃子の話をしている時に、何に合わせれば良いのか(リズム的な意味)、旋律も繰り返しだと思うんだけどなぁとという話が出ていていました。
基本的に踊りがあるものは踊りが主導だけれど、だけれど踊りももちろん囃子を聞いていて踊っているので、お互いが合わせあって演目に向かっている感じ。それを何度も稽古して繰り返していくうちに曖昧さから独特のグルーヴ感が生まれてくるものが、その土地の芸能の空気なのかな。
と思うので、そういう話をしたり。
なんというか、結論から述べると、根本的に形を作ってなぞるだけでは満足できない(笑)
形をなぞれるところが入口で、その先にある無形のものを大切に、というのが僕が持っているお祭や郷土芸能の感覚で。
その話をして改めて考えさせられることもありました。
時間をかけて練り上げていく、その為に集まる、もしくは集まるから練り上がっていく、そういうのが郷土芸能、民俗芸能の時間感覚なのかなと、個人的にはそう思っています。
もちろん、上手にできてかっこ良いにこしたことは無いですが(むしろ、未だに上手にできるようになりたいという気持ちでいっぱいです笑)
普通の演奏での現場は、譜面や音源を渡されて一回リハしてハイ本番〜!という感じがよくありますし、集中して合理的に楽曲を覚えるスキルは必須とは思います(僕は苦労しますが笑)
ただ、郷土芸能の方向性はそういうところでは無くて、もっと曖昧なところなのかなと思ったり。そこから生まれる空気に魂が宿っているというか。そして、その空気から逆に暮らしや生活が見えてきたりと。
もちろん、練習を疎かにはしてはいけませんが。
ご先祖、先輩、先達から伝わってきた空気、自分がその空気に“成れて”、それを伝えて、そのまた伝えた人がその空気に成れて、もしくは進化させて、そしてまたそれを伝えて、、、というところまで見えて初めてマスター・・・というより
気がついたら伝え紡ぐ糸の一本になれた、という感覚が理想なのかな。
もちろんそこは人それぞれだと思いますが、個人の表現だけの話ではなくて、自分以外の様々な要素を尊重しあい受け入れ合い、時間をかけて合わせあって醸成して成り立っていく芸事であって、願いが込められて神事・仏事になっていっているのかなと。
合わせ合う、ってそう考えると、いただきます並に深いなと思いました。
これも、所謂「和の心」というところでもあるのかな。
今回も色々な方々と交流すると、普段言葉にしていない感覚を改めて見直すきっかけになったり、教えていただいたりで、本当色々と刺激になって勉強にもなりました。
普段感じている感覚を文字にすると、なにやら気難しそうな感じになってしまいますね・・・(笑)
熊野堂十二神鹿踊の方は、これから秋の例祭に向けて練習が始まるとのこと。機会を見つけて見学にもいきたい。
第1回のレポート
熊野本宮例祭での熊野堂十二神鹿踊の記事
前回の記事:
記事や、活動が面白いと思ってくださったら是非サポートお願いします。活動費に使わせていただきます!
