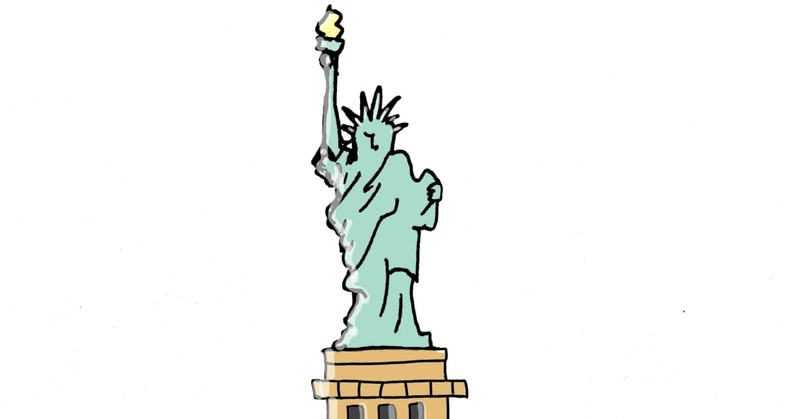
血と暴力の国、アメリカの歴史 #33
ことしはアメリカ大統領選挙の年だ。
前大統領が再び候補になって、「もしトラ」だとか「ほぼトラ」なんて云われたりしている。
前回の選挙で不正があった、などとフェイクを撒き散らし、大衆を煽って議会を襲撃させ民主主義を破壊しようとした張本人が、ふたたび大統領へ返り咲こうとしている。
流石にヤバいんじゃないか。
それでなくてもアメリカはひょっとしてヤべえ国なんじゃないか、と云う考えが僕の内で年々強まっている。
そりゃ中国だってロシアだってイスラエルだって北朝鮮だって、日本でさえヤバい国だとおもうけれど、アメリカへは盲目的に追従しすぎなんじゃないか。それでだいじょうぶなのか。
アメリカと云う国のヤバさの正体を知りたくて、というわけでもないが、偶々手に取った中野博文『暴力とポピュリズムのアメリカ史』(岩波新書 新赤版2005)を読むと、なぜトランプのような輩が現れ、なぜ彼が支持されるのか、その背景をある程度までナットクできる。
僕は、二十世紀に入ってからのアメリカ史は『映像の世紀』などでそこそこ親しんできたが、それ以前の、建国から南北戦争へ至るまでの歴史は殆ど知らず、この本ではじめて学ぶことも多かった。
共和党と民主党の、主張や支持者のイデオロギー的な部分が、昔と今とで逆転しているのがややこしい。
まあ日本も、保守と云われる政党を主に若いひとが支持していたり、革新(左派リベラル)政党は高齢者に支えられていたり、と云った逆転現象が政治をややこしくしているけれど。
アメリカ建国の背景には暴力がある。
ヨーロッパ列強の植民地だった彼らは、自らの土地と権利を、自らの手で勝ち取らねばならなかった。
ひとりひとりが武器を手に取り、ミリシア(民兵)を組織し、戦って勝ち取る。
暴力が建国の精神、ナショナル・アイデンティティの一部になった。
アメリカ人には(と、主語をデカくしてしまうのは気が引けるが)遡っていくとその根底に、暴力の血が流れているのかもしれない。
アメリカに限らず、国の歴史とは戦争の歴史であるが、こと彼の国に関しては、建国から今に至るまで、ひっきりなしに戦争をしている。
暴力と云う文脈で考えると、この好戦的なお国柄もある程度ナットクできてしまう。
話は暴力からさらに進んで、ポピュリズムへ向かう。
アメリカでは、国民ひとりひとりが武器を手に取り、自ら国を作ることこそ、民主主義の精神そのものである。
政府が間違っていれば、民衆が武力を背景に立ち上がって誤りを正す。
勝てば官軍、正義は我にあり、だ。
これはアメリカに限った話だろうか。
明治維新や、戦前日本の軍部の暴走を思い浮かべる。
全然別の国の話なのに、どこか似ている。
余談だが、歴史を学ぶ面白さは、この類似のハッケンにあるようにおもう。
国を(または新しい社会や価値観を)作っていくとき、暴力を用いるのは、或いは仕方のないことなのかもしれない。
重要なのは、それを如何に制度化したり手放したりできるか、だ。
我が国は敗戦後、GHQ=アメリカのマッカーサーの主導で、いちどは武器を手放しかけたが、結局はおなじアメリカの戦争に巻き込まれ、再軍備へ転換した。
それが今また、じわじわと肥大化しつつある。
アメリカでも軍隊の制度化ははかなりうまくいっているように見えるが、精神として根づく暴力は、稀に暴走する。
その僅かな綻びが、議会襲撃のような取り返しのつかない事態を引き起こすこともあるから、武器=暴力はやはり厄介である。
アメリカは歴史の浅い国で、建国から今に至るまで徹底してリアルで、ほかの国と異なり神話の入りこむ余地がない。
そんな国が、どこよりも過剰に宗教を奉っている(ように見える)のも面白く、今度は彼の国の信仰の歴史も学びたくなった。
Amazonで見る👇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
