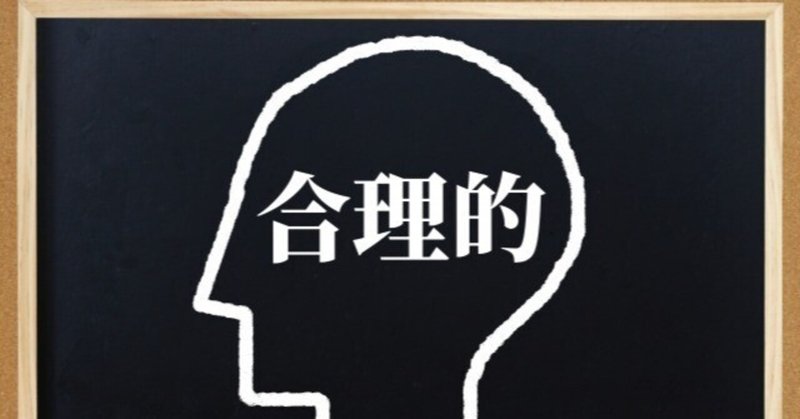
一見すると合理的に見えるやり方の中に見え隠れする非合理性を洗い出す:みずほ銀行に勤めている◯年前の私へ(西新宿支店編3)
「大丈夫!やがて、非合理的なやり方は時代と共に廃れていく」
転勤すると、どうしても、前の職場と今の職場との比較が生まれます。特に銀行の場合、全社的な手続きや従うべき規程は同じであっても、支店が違うと、仕事の進め方ややり方で様相が変わることが多いです。
西新宿支店に転勤して、驚いたことの一つが営業会議の資料に青焼きコピーを使っていることでした。
もしかすると、青焼きコピーと言っても、若い人はピンと来ないかもしれませんが、今でもたまに建物の古い図面や設計図で見かけるぐらいで、ほとんど目にしません。
前の支店では普通にコピー機で資料をコピーしていただけに、私などは青焼きコピーの資料を見た時に、(ガリ版印刷で作っていた)「小学校の学級新聞か!」と思わずツッコミを入れそうになりました(笑)。
青焼きコピーを使っていた理由はコストが安いことです。
しかしながら、普通のコピー機と違って、以下のようなデメリットがありました。
(1) 印刷するのに時間がかかる
(2) 印刷したものが読みづらい
(3) なんとなくちゃちいので、扱いが雑になる
毎月の営業会議は朝から行われるのですが、当日は担当者が印刷機の前に行列を作り、開始時間が近づいてくる中、「(前の人の印刷が)まだ終わらないのかなぁ」とイライラしていたのを覚えています。
もちろん、ムダな経費を削ることは必要です。けれども、ムダな経費を削るための目的は利益を増やすためです。
この場合、部分最適でなく、全体最適で考える必要があります。
資料を印刷する際の費用だけで考えれば、「普通のコピー>青焼きコピー」。
けれども、常に青焼きコピーを使うことで
(1) 売上につながる営業時間が減る
(2) 印刷に余計な時間がかかる
(3) 雑に扱われて情報共有が徹底しない
(4) 社員のモチベーションが下がる
といったことを勘案すると、総合的に見て、売上が減ったり、人件費などの費用が増えたりして、印刷代を減らした分をカバーできずに、かえって利益が減る可能性もあります。
ペーパーレスを進めようとしている今からすると、「そんな時代もあったんですね」と終わってしまうかもしれません。
けれども、現在においても、そのこと単体で考えたら合理的であっても、会社全体から見ると、非合理的なこともあるのではと思います。
ある会社では会社のクレド(企業全体の従業員が心がける信条や行動指針)をお金をかけて作成し、全社員に配っています。
もし、全社員に徹底したいクレドをコストが安いからとしって、青焼きコピーを使って配布していたらどうでしょうか?
おそらく、印刷費は削減できても、そのクレドは社内に浸透せず、中長期には会社の業績アップに寄与しません。
皆さんの会社で一見すると合理的だけれど、実は合理的とは言えない「青焼きコピー」に相当するものは何でしょうか?
ちなみに、西新宿支店でも、在籍期間中に営業会議の資料を青焼きコピーで印刷する風習はなくなりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
